人気blogランキングへ*クリックお願いします。
ハーレー用のキャブレターでCV、HSR、FCRなど殆んどに加速ポンプがついていますが、SUには見当たりません。
まず何故加速ポンプが必要なのか考察してみましょう。

これは一般的にケイヒンバタフライなどと呼ばれ、エボの初期までずっと使われていた固定ベンチュリーのキャブレターの簡単な構造図です。
アイドリングでは吸入空気を最大に制限しているので、スロットルバルブ(バタフライバルブ)の前ではほとんど負圧はないのでメインジェットからのガソリンの流入はありません。それだけではアイドリングは不可能なので、スロットルバルブの僅かに開く部分に設置してあるスローポートから、パイロットスクリューで計量されたガソリンが吸入されます。
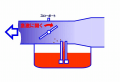
スロットルバルブが急激に開かれると、エンジン回転数もまだ低く全般的に負圧が低くなってしまい、スローポート周辺の負圧もなくなりメインジェットからもガソリンは吸入されません。
早く加速したい気持ちとウラハラにA/Fがとんでもなくリーン(薄い)になってしまいます。
アクセルが一定のときの空燃比が14:1~16:1なのに対し、加速をしたいときは8:1前後の濃い空燃比が必要になります。
アクセルをどんなに捻っても、この状況ではハーレーは加速してくれないのです。

こういった状況を救うために、加速ポンプからガソリンを水鉄砲のように出してやって辻褄を合わせてやるというシステムですね。
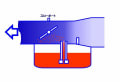
この図は加速ポンプとは関係ありませんが、アクセルが一定の場合やそれに準じた状況では、アクセル開度やエンジン回転数に応じた負圧によってメインジェットで計量されたガソリンが吸入されます。

さていよいよSUの番ですが、CVの祖先であるためあらゆるところ原始的ではあります。
ピストンはドームの中を摺動しているのでサクションチャンバー(負圧室)の密閉度は低いし、ピストン自体も大きく重いので安定した素早い動きは望めません。
ところがタブンに逆説的ですが、スロットルバルブが急激に開かれてもピストンが機敏に上がらないため、ジェットニードルの付近は負圧が高くガソリンの吸入が行われて息つきは発生しません。
ダンパー?
古いタイプのSUキャブはドームの頭のキャップにダンパーが付いています。メーカーのリベラの説明ではオイルは入れるなと書いてあります。潤滑用にWD40をスプレーするだけとなっています。
昔ワタシが乗っていたベレGのSUにはオイルが入っていた覚えがあるので、ハーレーについたSUのダンパーにオイルを入れてみた事がありますが、ピストンの動きが抑えられすぎたようで加速ポンプの吐出量が多すぎるのと同じに黒煙がでてしまいましたね。

左がSUのピストンとドーム、右がCVのサクションピストンです。
CVのはゴム製のダイアフラムにより摺動部を密閉して、しかもピストン自体を小さく軽くしてレスポンスを改善しています。
しかしそのために加速ポンプが必要になっていますね。
ハーレー用のキャブレターでCV、HSR、FCRなど殆んどに加速ポンプがついていますが、SUには見当たりません。
まず何故加速ポンプが必要なのか考察してみましょう。

これは一般的にケイヒンバタフライなどと呼ばれ、エボの初期までずっと使われていた固定ベンチュリーのキャブレターの簡単な構造図です。
アイドリングでは吸入空気を最大に制限しているので、スロットルバルブ(バタフライバルブ)の前ではほとんど負圧はないのでメインジェットからのガソリンの流入はありません。それだけではアイドリングは不可能なので、スロットルバルブの僅かに開く部分に設置してあるスローポートから、パイロットスクリューで計量されたガソリンが吸入されます。
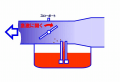
スロットルバルブが急激に開かれると、エンジン回転数もまだ低く全般的に負圧が低くなってしまい、スローポート周辺の負圧もなくなりメインジェットからもガソリンは吸入されません。
早く加速したい気持ちとウラハラにA/Fがとんでもなくリーン(薄い)になってしまいます。
アクセルが一定のときの空燃比が14:1~16:1なのに対し、加速をしたいときは8:1前後の濃い空燃比が必要になります。
アクセルをどんなに捻っても、この状況ではハーレーは加速してくれないのです。

こういった状況を救うために、加速ポンプからガソリンを水鉄砲のように出してやって辻褄を合わせてやるというシステムですね。
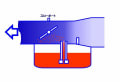
この図は加速ポンプとは関係ありませんが、アクセルが一定の場合やそれに準じた状況では、アクセル開度やエンジン回転数に応じた負圧によってメインジェットで計量されたガソリンが吸入されます。

さていよいよSUの番ですが、CVの祖先であるためあらゆるところ原始的ではあります。
ピストンはドームの中を摺動しているのでサクションチャンバー(負圧室)の密閉度は低いし、ピストン自体も大きく重いので安定した素早い動きは望めません。
ところがタブンに逆説的ですが、スロットルバルブが急激に開かれてもピストンが機敏に上がらないため、ジェットニードルの付近は負圧が高くガソリンの吸入が行われて息つきは発生しません。
ダンパー?
古いタイプのSUキャブはドームの頭のキャップにダンパーが付いています。メーカーのリベラの説明ではオイルは入れるなと書いてあります。潤滑用にWD40をスプレーするだけとなっています。
昔ワタシが乗っていたベレGのSUにはオイルが入っていた覚えがあるので、ハーレーについたSUのダンパーにオイルを入れてみた事がありますが、ピストンの動きが抑えられすぎたようで加速ポンプの吐出量が多すぎるのと同じに黒煙がでてしまいましたね。

左がSUのピストンとドーム、右がCVのサクションピストンです。
CVのはゴム製のダイアフラムにより摺動部を密閉して、しかもピストン自体を小さく軽くしてレスポンスを改善しています。
しかしそのために加速ポンプが必要になっていますね。




































