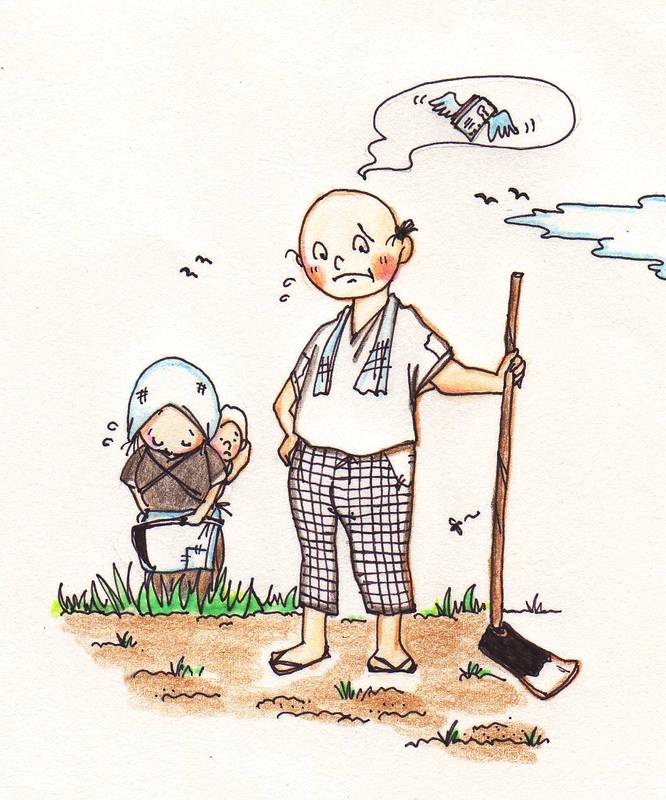 現在、加古川市内の中学生がつかっている歴史教科書(大阪書籍)に、次の記述があります。
現在、加古川市内の中学生がつかっている歴史教科書(大阪書籍)に、次の記述があります。
「・・・政府は、まず土地を所有する権利を認めて、田畑の売買を自由にしました。
次いで、1873(明治6)年から、全国の土地の面積やよしあしを調べ、土地の値段である地価を定めました。
土地の所有者には地券をあたえ、土地の3%にあたる額を地租として、貨幣で納めさせることにしました。
これにより、土地についての税金の負担と集め方は、全国一律となりました。
これを地租改正といいます。・・・江戸時代の年貢の総量と同様になるように計算されており、全体として農民の負担は軽くなりませんでした」
その後、各地で地租改正に反対する激しい運動がおこり、これに押された政府は明治10年に地租を地価の2.5%に切り下げています。
このようすを、二俣村にみましょう。
地租、しめて947円21銭6厘(明治14年1月)
二俣村 戸数 64戸
人口 350人
一 田、 39町2反5歩 地価3万482円93銭4厘
地租762円5銭8厘
一 畑、 16町2反1畝27歩 地価5537円45銭6厘
地租138円44銭1厘
一 宅地、2町9反5畝13歩 地価1867円97銭5厘
地租46円70銭
一 藪地、1反3畝13歩 地価78銭2厘
地租1銭7厘
一 土砂捨場、13歩 地価9厘
厘位未満
合計反別、 58町5反1畝11歩 地価3万7889円11戦6厘
地租947円21銭6厘
外に無税地反別7町9反8畝20歩、及び堤防敷地5反4畝21歩
二俣村には、明細帳等の古文書が残されていないため、詳細は分かりませんが、教科書にあるように、税金は江戸時代とあまり変わらず収穫の5割程度が税であったと想像されます。
この記録は『播磨地種便覧』(明治15年12月発行)からの数字です。その前書きに、「一、戸数・人口は明治14年1月御調ヲ以載ク」の注意書きがあります。
だとするなら、明治14年当時、二俣村の人口は350人・戸数64戸の集落でした。当時の風景が浮かんでくるようです。


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます