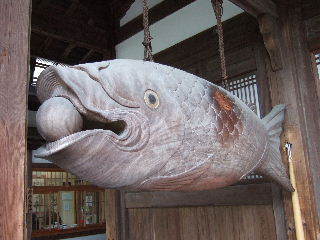木は楽器にもよく使われます。ご存知の方も多いと思いますが、日本伝統の楽器・琴は桐で作られています。
昔から、「山奥にひっそりと生え、清らかなせせらぎの音を聴いて育った桐が最高の琴になる」と言われていたそうです。でも、これは多分ウソ。私の知る限り、キリは川が流れるような谷筋ではなく、陽当たりのいい斜面に生えています。せせらぎの音と琴の音色をダブらせたつくり話でしょう。

(京大宇治キャンパスの「材鑑調査室」には琴も置いてありました)
私たちが知っている琴は、実は中国からもたらされたもので、形は少し違いますが、中国や朝鮮半島にも桐製の琴があります。それ以前には「和琴(わごん=やまとごと)」と呼ばれる日本独自の琴があったようで、正倉院に10張り残っています。
おもしろいことに、この和琴は日本固有の木・ヒノキで作られているそうです。ある本に「ヒノキでバイオリンを作ったら和風の音がした」と書いてありましたが、ヒノキ製の琴やバイオリンの音を聴いてみたいものです。
去年の夏、ある百貨店が開催した「伝統工芸展」に琴や三味線の製作実演販売コーナーがあるというのでデジカメ片手に行きましたが、おじさんが一人で店番しているだけでした。でも、800万円もの琴や、100万円近い三味線のバチ(象牙製)が並んでいたのにはビックリしました。どの世界にも高価な逸品というものがあるんですね。
昔から、「山奥にひっそりと生え、清らかなせせらぎの音を聴いて育った桐が最高の琴になる」と言われていたそうです。でも、これは多分ウソ。私の知る限り、キリは川が流れるような谷筋ではなく、陽当たりのいい斜面に生えています。せせらぎの音と琴の音色をダブらせたつくり話でしょう。

(京大宇治キャンパスの「材鑑調査室」には琴も置いてありました)
私たちが知っている琴は、実は中国からもたらされたもので、形は少し違いますが、中国や朝鮮半島にも桐製の琴があります。それ以前には「和琴(わごん=やまとごと)」と呼ばれる日本独自の琴があったようで、正倉院に10張り残っています。
おもしろいことに、この和琴は日本固有の木・ヒノキで作られているそうです。ある本に「ヒノキでバイオリンを作ったら和風の音がした」と書いてありましたが、ヒノキ製の琴やバイオリンの音を聴いてみたいものです。
去年の夏、ある百貨店が開催した「伝統工芸展」に琴や三味線の製作実演販売コーナーがあるというのでデジカメ片手に行きましたが、おじさんが一人で店番しているだけでした。でも、800万円もの琴や、100万円近い三味線のバチ(象牙製)が並んでいたのにはビックリしました。どの世界にも高価な逸品というものがあるんですね。