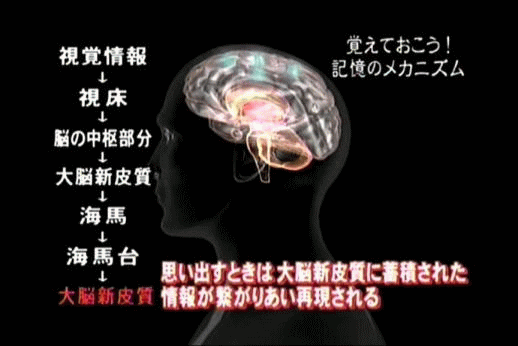
現 在のところ、記憶についてすべてが解明されているわけではありません。また、事柄の記憶と技の記憶では記憶するメカニズムが違うと考えられています。比較的よく解明されている事柄の記憶のシステムを見てみましょう。
目、耳、鼻、口、皮膚などの感覚器(五感)から収集された感覚情報は、大脳新皮質(考えて判断をする、話をするといった高度な知的活動をつかさどる部位)へ送られて分析されます。次に大脳辺縁系(食欲や睡眠などの本能的活動や喜怒哀楽の情動をつかさどる部位)にある海馬に送られます。この海馬で情報が記憶として一時的に蓄えられる(数分程度の短期記憶)と同時に、情報は海馬周辺の記憶回路と呼ばれる神経細胞に送られ数日間記憶が保持されます(近時記憶)。そして、再び大脳新皮質(前頭葉など)に送り返されて数か月から一生の間保持されることになる(長期記憶)のです。すべての情報が長期記憶として蓄えられるのではなく、記憶するプロセスの中で多くの記憶はふるい落とされていきます。医療ニュースより、引用、
ヒトの記憶の仕組みをもっと詳しく説明すると、短期記憶などは「海馬」が関わっている。長期記憶などは「大脳新皮質」という大脳皮質の回りに2mm状の細胞に「円錐形のコラム」という細胞が一個のコラムに200万個の細胞が並んでいる。ここに記憶されるのである。
まず、ヒトの記憶は「五感」感覚器官から外的情報が脳に送られる。今回は視覚からの情報記憶で説明致します。
視覚→視床→脳の中枢部分(前頭葉46野)→大脳新皮質→海馬→海馬台→大脳新皮質の順番で記憶して行くのです。
眼で見た記憶情報が何であるか前頭葉で計算、判断されます。次に知性や理性に関わっている「大脳新皮質」に一端記憶され、次に短期記憶を司る「海馬に記憶」されます。その次に海馬の下にある「海馬台」を経由してまた、大脳新皮質に戻り長期記憶となるのです。
但し、自分の概念によって、これは必要だから覚えないといけないと感じれば、長期記憶に記憶され、記憶として残りますが、あまり重要でない記憶情報は海馬で、1週から10日程度で記憶が消えてしまいます。
今度、思い出すときは、大脳新皮質に蓄積された記憶情報が繋がりあい再現されるのです。
高齢者になって、この思い出し、記憶の引き出し能力が低下して、人の名前が思い出せない、分からないと自覚するのは、ニューロンネットワーク(脳細胞)の死滅と伝達速度の低下によるものです。
高齢者でも記憶力は低下しないことが我々の研究でも分かっております。但し、その記憶情報を引き出す能力が低下するので、「記憶力が低下したと勘違い」するのです。
現に60歳近い男性が円周率計算の暗記記録に挑戦し、10万桁近い数字を暗記し、世界記録を昨年樹立した。
この男性は千葉の市原市に在住している普通のサラリーマンである。
日々、暗記をするために努力しているからである。思い出し、記憶の引き出しにも工夫があり、物語風にして数字を暗記している。
普通、私達が短時間に記憶できる数字は7桁である。だから、1週間は7日、電話番号も局番を除けば7桁、郵便番号も7桁である。
他にも、ラッキー7という数字が縁起良いとされるのも、この記憶に関係しているからである。
現在の子供達の記憶は、視覚優位の記憶のため、大脳新皮質に記憶されず、海馬(短期記憶)に関わる細胞に記憶されている。だから、1週間もすると忘れていることが多いのである。漢字の書き方もパソコンなど利用すると書き順を覚えず、すぐに変換してくれる。これでは記憶が出来ないのである。また、英語などの言語は文法より、ヒヤリングが重要なのである。つまり、五感をフルに活用しながら記憶し、何度も繰り返し覚えて行く(記憶)して行くことが重要となる。これらの記憶方法が大脳新皮質に記憶され、長期間忘れない記憶となり「学力」と結びつくのです。
いくら、教科書をまる暗記して、学校のテストが出来ても、正しい記憶方法をしていないと社会に出て困ってしまうのである。
確かに人は好きなことをしていると暗記力にも関係してくる。嫌々覚えるより、快感を持って覚えた方がより一層大脳新皮質に記憶されて行く、つまり、勉強が好きだとなると学校のテストの成績も良いわけです。
逆に勉強が嫌いだからと言って学校の成績が悪いから「頭が悪いのではないことをご理解下さい」。決して学校の成績で頭の良さは比較できない。
幾ら高学歴でも、高収入でも皆70歳近くなれば高齢者になり、高学歴も、社長さんであっても全く関係なくなる。つまり、健康体が一番であり、健康脳に繋がり、何時までも若々しく居ることが一番である。
脳が若いことは記憶力も然り、思い出し能力が高い証拠でもある。
まず、思い出し記憶を高めるためには、好奇心を持って、思い出せないときにはすぐに諦めずに「思い出すまで頑張る」このことがニューロンネットワークの繋がりを活性化し、脳の伝達もスムーズにしてくれる。同時に運動性ニューロンなども活性化し、反射神経なども良くなることが分かっている。まずは脳の訓練からである。難しいと思う本にも挑戦し、苦手と思う計算にもチャレンジする。この前向きな取り組みが脳には重要なのである。五感を駆使し、脳に色々な情報(記憶)を送り、それを引き出す(思い出す)鍛練を繰り返すことである。このことで記憶力はアップするのである。自分は駄目だと決めつけず、今年はチャレンジだと思い、何か一つでいいから「苦手」にチャレンジすることで、脳は鍛えられる。
すぐに諦めたり、落胆すると脳も同時に衰えてしまう。だから、好奇心は脳へのご褒美なのです。筋肉と同じで脳もトレーニングが重要な要素なのです。五感教育研究所、主席研究員、荒木行彦、
目、耳、鼻、口、皮膚などの感覚器(五感)から収集された感覚情報は、大脳新皮質(考えて判断をする、話をするといった高度な知的活動をつかさどる部位)へ送られて分析されます。次に大脳辺縁系(食欲や睡眠などの本能的活動や喜怒哀楽の情動をつかさどる部位)にある海馬に送られます。この海馬で情報が記憶として一時的に蓄えられる(数分程度の短期記憶)と同時に、情報は海馬周辺の記憶回路と呼ばれる神経細胞に送られ数日間記憶が保持されます(近時記憶)。そして、再び大脳新皮質(前頭葉など)に送り返されて数か月から一生の間保持されることになる(長期記憶)のです。すべての情報が長期記憶として蓄えられるのではなく、記憶するプロセスの中で多くの記憶はふるい落とされていきます。医療ニュースより、引用、
ヒトの記憶の仕組みをもっと詳しく説明すると、短期記憶などは「海馬」が関わっている。長期記憶などは「大脳新皮質」という大脳皮質の回りに2mm状の細胞に「円錐形のコラム」という細胞が一個のコラムに200万個の細胞が並んでいる。ここに記憶されるのである。
まず、ヒトの記憶は「五感」感覚器官から外的情報が脳に送られる。今回は視覚からの情報記憶で説明致します。
視覚→視床→脳の中枢部分(前頭葉46野)→大脳新皮質→海馬→海馬台→大脳新皮質の順番で記憶して行くのです。
眼で見た記憶情報が何であるか前頭葉で計算、判断されます。次に知性や理性に関わっている「大脳新皮質」に一端記憶され、次に短期記憶を司る「海馬に記憶」されます。その次に海馬の下にある「海馬台」を経由してまた、大脳新皮質に戻り長期記憶となるのです。
但し、自分の概念によって、これは必要だから覚えないといけないと感じれば、長期記憶に記憶され、記憶として残りますが、あまり重要でない記憶情報は海馬で、1週から10日程度で記憶が消えてしまいます。
今度、思い出すときは、大脳新皮質に蓄積された記憶情報が繋がりあい再現されるのです。
高齢者になって、この思い出し、記憶の引き出し能力が低下して、人の名前が思い出せない、分からないと自覚するのは、ニューロンネットワーク(脳細胞)の死滅と伝達速度の低下によるものです。
高齢者でも記憶力は低下しないことが我々の研究でも分かっております。但し、その記憶情報を引き出す能力が低下するので、「記憶力が低下したと勘違い」するのです。
現に60歳近い男性が円周率計算の暗記記録に挑戦し、10万桁近い数字を暗記し、世界記録を昨年樹立した。
この男性は千葉の市原市に在住している普通のサラリーマンである。
日々、暗記をするために努力しているからである。思い出し、記憶の引き出しにも工夫があり、物語風にして数字を暗記している。
普通、私達が短時間に記憶できる数字は7桁である。だから、1週間は7日、電話番号も局番を除けば7桁、郵便番号も7桁である。
他にも、ラッキー7という数字が縁起良いとされるのも、この記憶に関係しているからである。
現在の子供達の記憶は、視覚優位の記憶のため、大脳新皮質に記憶されず、海馬(短期記憶)に関わる細胞に記憶されている。だから、1週間もすると忘れていることが多いのである。漢字の書き方もパソコンなど利用すると書き順を覚えず、すぐに変換してくれる。これでは記憶が出来ないのである。また、英語などの言語は文法より、ヒヤリングが重要なのである。つまり、五感をフルに活用しながら記憶し、何度も繰り返し覚えて行く(記憶)して行くことが重要となる。これらの記憶方法が大脳新皮質に記憶され、長期間忘れない記憶となり「学力」と結びつくのです。
いくら、教科書をまる暗記して、学校のテストが出来ても、正しい記憶方法をしていないと社会に出て困ってしまうのである。
確かに人は好きなことをしていると暗記力にも関係してくる。嫌々覚えるより、快感を持って覚えた方がより一層大脳新皮質に記憶されて行く、つまり、勉強が好きだとなると学校のテストの成績も良いわけです。
逆に勉強が嫌いだからと言って学校の成績が悪いから「頭が悪いのではないことをご理解下さい」。決して学校の成績で頭の良さは比較できない。
幾ら高学歴でも、高収入でも皆70歳近くなれば高齢者になり、高学歴も、社長さんであっても全く関係なくなる。つまり、健康体が一番であり、健康脳に繋がり、何時までも若々しく居ることが一番である。
脳が若いことは記憶力も然り、思い出し能力が高い証拠でもある。
まず、思い出し記憶を高めるためには、好奇心を持って、思い出せないときにはすぐに諦めずに「思い出すまで頑張る」このことがニューロンネットワークの繋がりを活性化し、脳の伝達もスムーズにしてくれる。同時に運動性ニューロンなども活性化し、反射神経なども良くなることが分かっている。まずは脳の訓練からである。難しいと思う本にも挑戦し、苦手と思う計算にもチャレンジする。この前向きな取り組みが脳には重要なのである。五感を駆使し、脳に色々な情報(記憶)を送り、それを引き出す(思い出す)鍛練を繰り返すことである。このことで記憶力はアップするのである。自分は駄目だと決めつけず、今年はチャレンジだと思い、何か一つでいいから「苦手」にチャレンジすることで、脳は鍛えられる。
すぐに諦めたり、落胆すると脳も同時に衰えてしまう。だから、好奇心は脳へのご褒美なのです。筋肉と同じで脳もトレーニングが重要な要素なのです。五感教育研究所、主席研究員、荒木行彦、


























