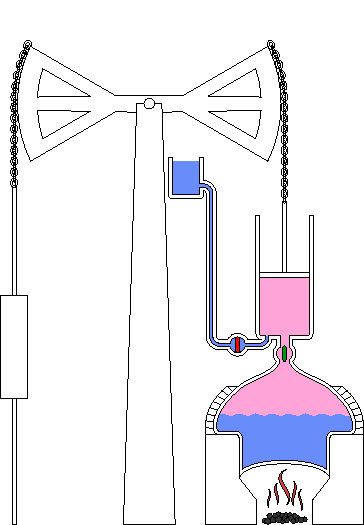画像はttp://mostadvancedengine.com/より転載
画像はttp://mostadvancedengine.com/より転載
一見、普通のVツインのバイクだが、シリンダーヘッドに注目してほしい。
 ご支援の応援クリック いつもありがとうございます。
ご支援の応援クリック いつもありがとうございます。
実験用エンジンをみるとDOHCのようにも見えるが、よく見るとヘッドが異常に小さいのに気が付く。
バイクのエンジン部分のアップ。
ヘッドカバーが外れた画像があるのだが、なぜか小さくて分からない。
V8エンジンのでは大きな画像があった。
これを見て実用化は近いと思うが、それはまず自動車用ではなく、天然ガス燃料の発電機が中国に出荷される予定(された?)であるし、中国との合弁で量産をする計画もあるようだ。
COATES INTERNATIONALのサイト(ttp://mostadvancedengine.com/)を見ると非常に野心的に思え、家庭用発電機から、バイク・自動車・トラック・大型発電機・レース用エンジンまで視野に入れ、陸上スピード記録にも挑戦する予定らしい。
ロータリーバルブにはシングルとダブルの2種類があり、シングルでバルブの内部がマニホールドを兼ねる構造では外形が大きくなり、バルブ開口面積は大きくできる反面、シール性や潤滑に問題が大きくなるかもしれないが、このCSRVではダブルのバルブを球状にしたところがミソであると思われる。
従来のポペットバルブは、バルブをシートに押し付ける方向に燃焼圧力が掛かるため、シール性の面では有利であるが、往復運動するために高速回転では大きな加速度が掛かるから、正確な作動をさせるには強いスプリングを使って機械ロスを犠牲にするか、デスモドロミックのような複雑なメカニズムにせざるを得ない。そして開口面積を稼ぐとなるとビッグバルブにするか数を増やすのだが、構造上、バルブの傘とバルブシートの隙間を使うことになるので、大きくすればするほどシリンダー壁との距離が近くなり”カーテン効果”による効率の低下もあるから、充填効率を上げるのは難しい。
ロータリーバルブはポペットバルブと利点と問題がちょうど逆になり、傘が邪魔にならないから開口面積がそのまま利用でき、充填効率の面では非常に有利になるが、シール性と潤滑がトレードオフの関係にもなりやすく、バルブシートにあたる部分とバルブの密着度を上げれば熱膨張のことも考えて、更に潤滑が難しくなる。
実用化の目処が立ったからには、その辺りも解決したに違いないと思うが、今後に注目したいところだ。
 ご支援の応援クリック いつもありがとうございます。
ご支援の応援クリック いつもありがとうございます。