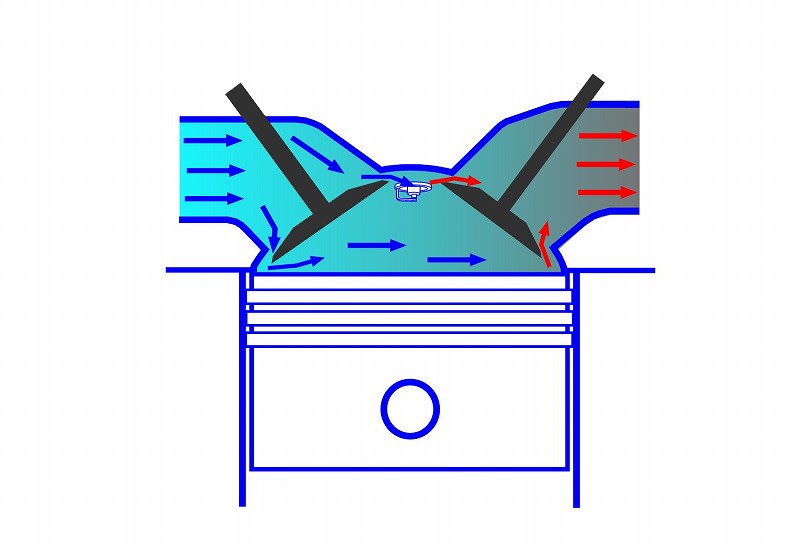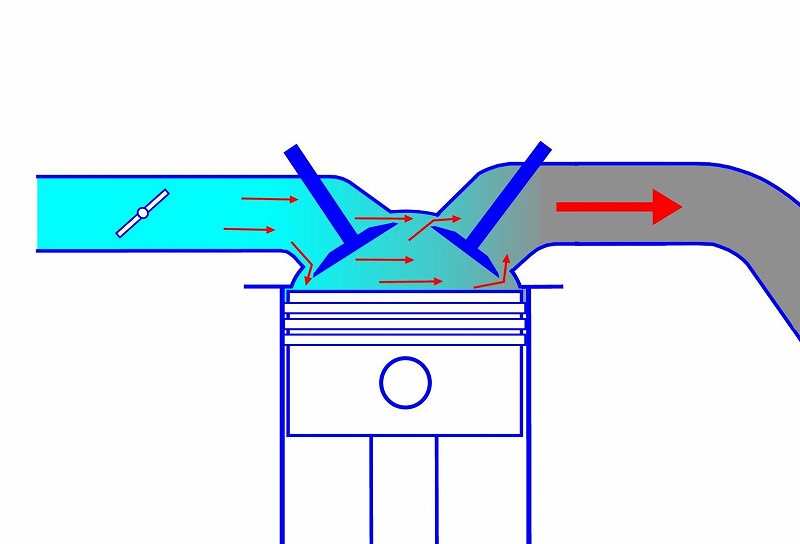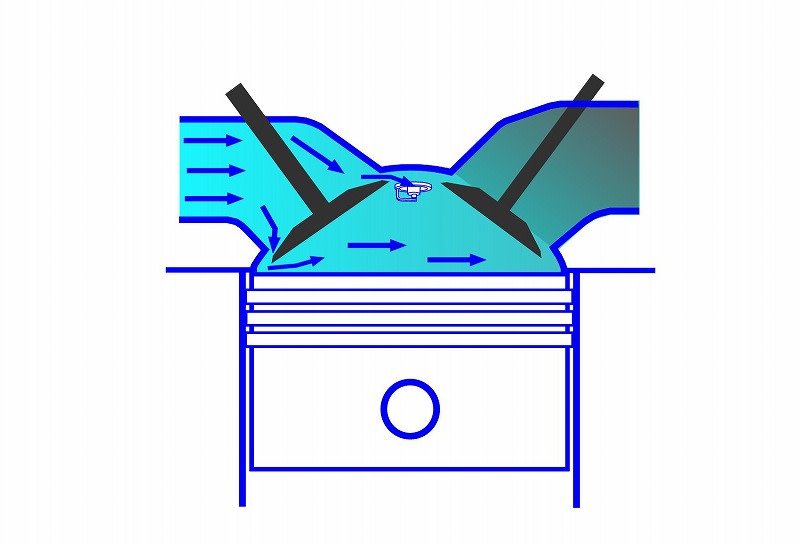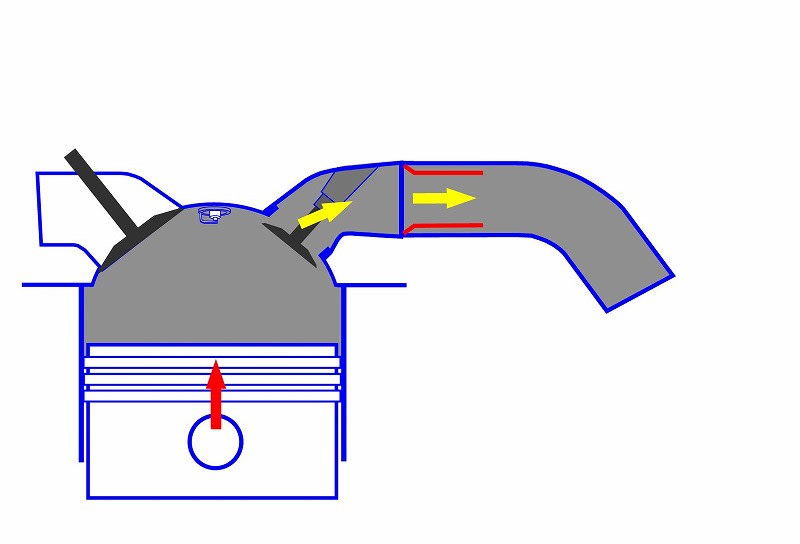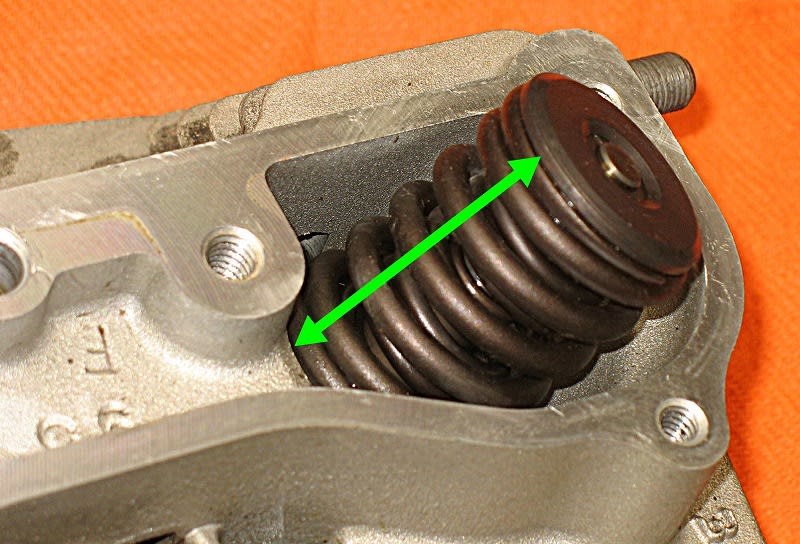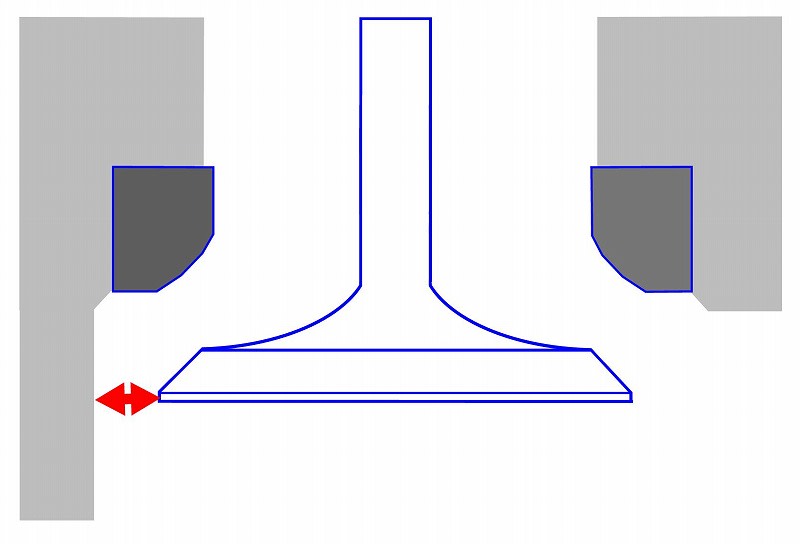さて、このタイトルも21世紀!?になってしまいました。今朝から雨がバシャバシャ降り、「海の日」というより「雨の日」のようです。地球の温暖化が進むと梅雨は長引くのだそうです。
昨日のF1レースを見て感慨深いものは、圧倒的に強いフェラーリとルノーです。アチコチで言われているのはサッカーワールドカップの決勝戦を彷彿とさせる戦いですが、考えてみれば今年はフェラーリとルノー以外は勝利していませんね。
昨シーズンではチャンピオンになったアロンソと同じ7勝をあげたライコネンも、今年は勝てる感じさえありませんし、前評判の高かったホンダも更に下降線を辿っています。
100年前に始めて行われたGPレースではルノーが優勝していますから、今年は更に総合優勝のために焦点を合わせているでしょうし、フェラーリも100年前の仇もとりたいし、シューマッハの最後の花道を飾るために30億円!の追加予算を用意したとのことです。
強いチームはなんといってもミスがないと言っても良いほど少なく、トラブルによるリタイアもありませんね。これも歴史の長さによるものなのか?
前置きが長くなりましたが、F1のエンジンは8気筒で2400CC、20000回転が可能で750馬力です。リッターあたりで約300馬力です。楕円ピストンは禁止されていますが、もし許されればリッター400馬力くらいまでいくかもしれません。
ワタシが過去に製作したレーサーでは、スズキインパルス400をGSXR400のピストンを使い480CCにして、96馬力を絞り出したのが最高です。リッター200馬力です。
コレはデビューレースが当時始まったネイキッドのオープンクラスで、富士スピードウエイという高速サーキットでホンダビッグ1などをブッチギリで勝利しました。
リッター200馬力も割と簡単で、量産エンジンをベースにカム以外はすべて量産部品を加工して使い、カムも市販のGSXRで一番高速型のプロフィルをコピーしたものです。雑誌の最高速チャレンジ企画でも矢田部で260㎞/hを達成し、カウルなし400ベースモデルの部門では暫らく歴代トップの座を維持していたものです。
自慢したいわけでなくココで何が言いたいかというと、57㎜のボアと47㎜のストロークでは4気筒でも480CCにしかなりませんけど、火炎伝播速度やピストン速度の心配もしなくてすみます。(これは逆説でそのためのショートストロークであり、マルチシリンダーです)こうしたショートストロークのエンジンに比べ、ロングストロークのエンジンでは吸気も排気もガス流速度の変化が大きく、幅広い回転域ではそのコントロールが難しく、大きいピストンは音波の発生源が大きいので、やはりコントロールが難しいものになります。
競争の幅に制限を設ける意味でF1にも気筒制限があるのは、同じ排気量でシリンダーの数が多ければ多いほどパワーが大きくできるように見えますが、実際には複雑さがフリクションロスや重量が大きくなるのでとても比例関係にはなりません。
ハーレーダビッドソンのエンジンでは、誰も絶対パワーやスピードを求める人はいませんが、相対的なシアワセは誰でも欲します。88より96も然りで、今回の変更が必然なのか営業的なのか想像の域を脱し得ませんが、88のボアストローク比がハーレーにしては異例な1.06であり、今回のストロークアップによる1.16がエボまでの1.21に近づいたのはある意味自然でもあります。
ボアストローク比はエンジン設計にとって、要であり基礎でもあります。パワーを追求するエンジンでは充填効率を何処で求めるかの元であり、フィーリングを追求するエンジン(ハーレー以外にはあまりナイかも)では他の要素との妥協点を探る意味で、変更は大きな冒険にもなり得ます。現に88エンジンのフィーリングは論争の的にもなったし、96歓迎論の大きさも・・・・。
前置きが思わぬ長さになってしまい、「マフラーの容量」シリーズのまとめを切り出そうと思っていましたが、今日はこれまでです。このまとめには苦慮しておりましたが、シリコンバレー在住のus05 1200rさんから、マタマタ資料とご見解を提供いただきまして、ここで感謝申し上げます。