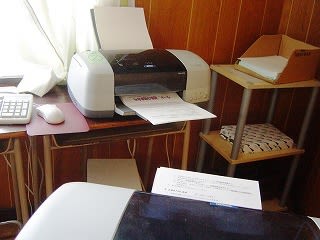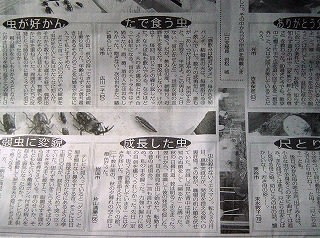朝ウォーク。梅雨に似合わない晴れた空。川沿いは気持ちよい風。川は薄茶色のにごり水。紫陽花の葉の水滴が涼しい。みんな昨日の雨のせいだろうか。
歩きながら、今日の予定変更を思いついた。
家を建ててから13年、フローリングへのワックス塗りは毎年1、2回欠かさずに行ってきた。が今年は雑用が重なり、1ヶ月以上遅れている。梅雨の晴れ間、私流天気予報は申し分ない。今日はワックス塗りをやろう、そう決めた。
その準備のため部屋の物を移動する。ワックスを塗ると同じように大変な作業になる。子供のころ夏休みに経験した大掃除を思い出す。
慣れた流れでワックスを塗る。汚れも取れる。塗りむらがないか見直しながら塗る。20分もすると汗拭きの時間もばかにならない、そう思いながら塗り続けた。
汗をかいただけの値打ちがある、仕上がりを眺め、自己満足しながら1時間半の作業を終えた。家内は嬉しそにご苦労さま、と差出した琥珀色の液体はビールならぬ冷たいお茶だった。
ワックス使用上の注意に30分以上乾燥させることとある。さらに厚く塗るなと有るが、暑いときにするなとは書いてなかった。
(写真:少しは若さを取り戻したフローリング)