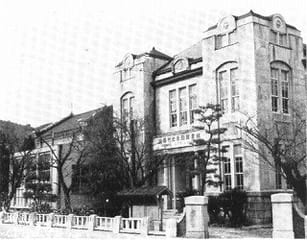神社の鳥居の下に立つと、2本の柱が威厳を保っているとも思えないのに、ここからは神域という思いは子どものころから変わっていない。それは進歩していない証なのか、あるいは自然に具わった敬いなのかも知れない。
いま有名な神域は観光コースに組み込まれ、訪れた人で門前町は賑わっているという。かって高い信仰心からお参りした民で栄えた町の賑わいは、物語の世界だけになったのだろうか。こんな変遷を鳥居はどう眺めているだろう。
そんな鳥居も明日からは少し楽にして欲しい。そう明日から日本国中の神々が出雲大社に集まり神サミットが開かれる。出雲以外の国々には神が不在となるため「神無月」、出雲は「神在月」になると説はいつ生れたのだろう。
神の数は「八百万(やおよろず)」という。1の鳥居に2の鳥居などと数えると、いったい鳥居は幾千万基あるのだろう。ここらで鳥居といえば、観光メッカにはなっているが厳島神社や太鼓谷稲荷の朱丹の大鳥居は群を抜いている。
道沿いのゴミが投げ捨てられる場所に小さな手作りの鳥居を設けたら不法投棄がなくなった、という話があちこちである。どんな人にも鳥居への敬いの気持ちがあり、鳥居は心ある人を守ってくれる。氏神様の1の鳥居を見上げながら、今日の無事をお願いする。
(写真:注連縄は古く御幣がちぎれても神域をまもる鳥居)