2007年11月08日の山梨日日新聞によると 情報通信産業の山梨県内への誘致策などを協議してきた「県情報政策アドバイザー会議」(議長・甕昭男テレコムエンジニアリングセンター理事長)は7日までに提言書をまとめ、横内正明知事に提出した。との事です。
この件については2007年5月10日にこのブログで「情報政策アドバイザー会議」の第1回会議に関連して書いていました。その後の情報は確認していませんが半年で結論が出たようです。提言を読まないうちにコメントするのはいけないと思いますが、山梨県情報ハイウェイに関しては正直言ってツッコミどころ満載なのですが、この情報ハイウェイ活用問題は最初のスタートから間違えてしまった、どうも横内知事の責任ではないと思えるのです。むしろ困難な後処理と再構築をせねばならないのでアドバイザー会議を設置されたのだと、私には思えます。県庁ホームページから無秩序な発信が続いていることから見えるように山梨県庁にはCIO(最高情報責任者)の役割を果たしている人がいないように思えます。
(山梨日日新聞記事) 県が整備した光ファイバーによる高速情報通信基盤「情報ハイウェイ」の有効活用や、情報通信企業の立地を支援するための補助制度の創設などを提案している。
提言は「山梨ICT(情報通信技術)戦略に向けて」と題し、県の情報化を全国トップレベルに引き上げるための施策を例示。このうち、優先的に取り組むべき事項として、情報ハイウェイを東京都や静岡、長野県と接続するとともに、現在は都内や大阪府内に集中しているインターネットエクスチェンジ(プロバイダーなどの接続ポイント)を県内に整備する必要性を示した。
また、ICT化を担う人材育成を産学官連携で進めることを提案。最新技術を習得するため、先進企業への派遣や国外企業、大学との連携も示した。
良いタイミングだと思います、11月15日~17日は山梨テクノフェア&マルチメディアエキスポ2007が開催されます。提言の公開がこれに間に合って欲しいです。
平成19年11月7日の山梨県知事記者会見記録では、以下の内容が掲載されています。
●「山梨県情報政策アドバイザー会議の提言について」
(知事) 情報政策アドバイザー会議の提言がまとまりましたので、発表させていただきます。
本県の情報通信産業の振興を図るということは、私の公約にも入っている大きな課題であります。情報通信分野では本県ゆかりの方々で、大変活躍しておられる方々が何人もおります。そういう方々にお集まりをいただいて、情報政策アドバイザー会議というものを5月に設けまして、今日まで4回開催いたしました。皆さんお忙しい方々ですから東京事務所で開催をして、私自身も興味のあるテーマでありますので参加をいたしました。
今回、その提言として取りまとめられたものであります。内容は、また詳細については、情報政策課の方から説明があると思いますけれども、内容の前に、別紙というのがついていますか、メンバーですが、これをご覧いただきたいと思います。甕(もたい)さんという方はテレコムエンジニアリングセンターの理事長さん、この方は、かつての郵政省の通信部長をおやりになった方ですね。山梨大学のご出身で、山梨県の情報政策についてかねてから色々とアドバイスをいただいている方であります。それから日銀の国際局長をしておられる、元甲府支店長の出沢(いでさわ)さん。それから、今は協和エクシオの副社長をやっておられますが、この間までNTTドコモの副社長をしておられた石川さん、この方も山梨県のご出身で、山梨大学のご出身の方です。それから山梨大学の教授の新藤久和先生。それから日本電気の執行役員専務の広崎膨太郎さんという方。この方は特に山梨県のご出身ということではないんですけれど、日本電気は甲府日本電気があり、山梨県には大変ゆかりがあるということがありまして、甕理事長の紹介で入っていただいたわけであります。他にオブザーバーとして、総務省の総務審議官、電気通信関係・郵政通信関係の総元締めをしておられる鈴木さん、山梨県のご出身の方であります。それから北村さんという中央コリドー高速通信実験プロジェクト推進協議会ということで、長く中央道沿線に高規格の光ファイバーを敷いて高速通信実験をやろうという計画がありますけれども、それを推進しておられる方です。それから山梨大学の研究支援・社会連携部長の田中さん。それからデジタルアライアンスと言いまして、県が敷設をいたしました情報ハイウェイの管理をしている会社がありますが、その社長をしている鈴木さん。そんなメンバーで議論したところであります。
提言の内容につきましては、本県の情報化を全国トップレベルに押し上げて、「情報満載都市やまなし」を実現するということでありまして、具体的には、基盤インフラの整備・情報通信基盤の整備ですね、それから情報通信産業の集積、公共・民間アプリケーションの連携、人材育成の四つの視点から施策の方向性が示されているところであります。
そこで、これらを効果的に推進していくために、優先的に取り組みを進める事業としてリーディングプロジェクトというものを位置づけております。その内容としては、基盤インフラ・高度情報化拠点の整備と情報ハイウェイの利活用、産・学・官の連携強化、情報通信産業の集積を促進する支援制度の充実などについて提言をしております。
この提言に示されたプロジェクトにつきましては、今、策定作業を進めおります「行動計画」の中に具体的な事業として盛り込んでいくと同時に可能な限り来年度予算にも反映をしていきたいと考えております。
このA3版に概要版がありますけれども、山梨県の状況としては情報通信産業は、必ずしも高い水準にあるわけではありません。確か情報通信産業の従事者というのは、全国の0.3%くらいでしたか、全国的に見ても情報通信産業の集積というのは大変弱い県であります。そういう背景があって、しかし、左側に山梨県の状況というところにありますように、県における取り組みとしては、平成18年に民間にも開放している情報ハイウェイというものが運営されておりまして、これは各県に比べても自慢することができるものであります。
したがって、県内のハードウエアとしてはかなりしっかりしたものが、ギガネットワーク、ギガレベルのしっかりしたものができているということであります。
そして三番目にありますように、情報産業の振興策として、現在は製造業等の立地については企業立地奨励金がありますけれども、情報産業については特に企業誘致についての支援制度がないという状態であります。そういうような背景の基で、右側に参りましてリーディングプロジェクトと書いてありますけれども、こういうような施策を推進することによって、山梨県の情報化を全国トップレベルに押し上げていきたいということであります。
まず、基盤インフラ・高度情報化拠点の整備と情報ハイウエイの利活用の推進では、地域IXの整備、地域IXはご存知と思いますが、インターネット・エクスチェンジですね。その拠点であります。今、みんな東京に一旦行って、また戻ってくると。こういうネットワークになっていますから、東京と山梨県の間のインターネットの通信が、なんらかの事情で不都合が生じますと、山梨のインターネットが活用できないような状態になるということから、できるだけ地域、地域でインターネットのエクスチェンジを、交換の拠点を作って行く必要があるということで、地域IXの整備があります。
それから、高度情報化拠点の整備ということで、どこかに高度情報化のための拠点的なものを一つしっかりとしたものを作る必要があるということであります。
それから、情報ハイウェイの有効活用ということで、ギガネットワークの情報ハイウェイがあるわけですから、これをできるだけ民間に活用してもらうということでありまして、例えば、本県のいくつかの工業団地に立地している企業については、高速インターネット通信が必要なわけです。しかしながら工業団地によっては高速通信ができないところがあるんです。それは情報ハイウェイに接続すればできるようになるんですね。そういうことも含めて、情報ハイウェイをできるだけ活用していく方策を進めるべきだということであります。
それから、産・学・官の連携強化とありますが、産・学・官、山梨大学を始めとする学と、そして県庁と、そして産業界というものが連携していくということでありまして、とりわけ人材育成のために協調していったらどうかということであります。山梨大学は中国の浙江大学と提携を結んでおりますけれども、そういう所との提携の中で高度なICT人材を育成をするというようなことを産・学・官で連携していったらどうかということであります。
次に、情報通信産業の集積を促進する支援制度とありますけれども、先ほど申しましたように、情報関連産業の立地については支援制度はありませんので、製造業の立地奨励金に準ずるような支援制度を設けたらどうかということであります。
最後に推進体制として、フォーラムを開催すると同時に、推進室を設置してはどうかという提言であります。詳細については後ほど、情報政策課の方で説明をしてもらいますけれども、こういう提言がされまして、これをできるだけ実現をすることによって、本県の情報化を更に推進していきたいと考えております。以上であります。
この件はいずれホームページの方でまとめるつもりですが、記者さんによる質疑応答は以下の通りとなっています。
<質疑応答>
(記者) 提言の中にいくつか、県に対して実現して欲しいというものもあると思うんですが、例えば情報ハイウェイの低廉価格での提供であるとか、先ほど知事もおっしゃいました支援制度の充実、また推進室の設置などがあるんですが、そのことについて改めて、今、提言を受けて知事としてどのようにお考えなのか教えてください。
(知事) 先ほど申しましたように、山梨県が作った情報ハイウェイのネットワークは全国的にも誇ってもいい、ギガレベルの容量の大きいものなんですね。だから、これをできるだけ民間の人にも活用してもらうということが課題なんです。
先ほど申しましたように工業団地の中には、これにアクセスできなくて、依然として高速インターネットも使えないという工場があるわけです。これがまた企業立地に制約になっているということもありますので、この情報ハイウェイの民間のアクセスを促進していくということが必要だと思っております。
それは県として支援措置も考えなければいけませんけれど、まずはこういうものがあるということのPRをよく民間企業にして、知らない人が多いものですから、民間企業でもっと企業間の取引ですとかにこういうものを使うようにPR活動をまずやることが大事だと思っております。
(記者) 支援制度の創設とか、推進室の設置についてはどうでしょうか。
(知事) これは予算レベルの問題ですから、今の段階でそれをやりますということまでは、私としてはまだ申し上げるのを差し控えさせていただきたいと思います。そういう提言がなされております。これは誠意をもって対応していかなければならないと思っております。
情報産業が山梨県では集積の程度が非常に低いですね。例えば、情報通信産業のソフト系のIT産業の事業所の数というのは、山梨県は181箇所、全国が35,957箇所ですから、(全国の)0.5%程度でしょうか。隣の長野県あたりは632あるとか、富山県でも288とか、石川県でも390と、比べても、県が小さいということもありますけれども、情報産業の集積が低いという状況であります。
他方で、新聞などでも最近取りざたされておりますけれども、いわゆるデータセンターと言われるものについては、かなり東京の中心部から郊外へ、更には地方へ分散しようという動きが具体的に出てきています。そういうものの受け皿として、山梨県というのは大いにあり得るわけで、そのための何らかの支援方策というものは考えられてもいいのではないかと思っております。
 11月7日、甲府富士屋ホテルで開催された「山梨総合研究所創立10周年記念事業 明日の山梨考えるフォーラム&メッセ」において、NPOなどが出展しているメッセに「ミュージアム甲斐ネットワーク」のブース(というかテーブル)があったのです。時間がなくてリーフレット一枚を入手しただけで私はフォーラム会場に入ってしまったのですが、このリーフレットの画像は 湯村の杜 竹中英太郎記念館のページ に掲載されています。リストを見ると「ネットワーク発進!」時の参加は104館になっています、竹中英太郎記念館はもとより 山梨市の横溝正史館 も含まれています。
11月7日、甲府富士屋ホテルで開催された「山梨総合研究所創立10周年記念事業 明日の山梨考えるフォーラム&メッセ」において、NPOなどが出展しているメッセに「ミュージアム甲斐ネットワーク」のブース(というかテーブル)があったのです。時間がなくてリーフレット一枚を入手しただけで私はフォーラム会場に入ってしまったのですが、このリーフレットの画像は 湯村の杜 竹中英太郎記念館のページ に掲載されています。リストを見ると「ネットワーク発進!」時の参加は104館になっています、竹中英太郎記念館はもとより 山梨市の横溝正史館 も含まれています。 先日の記事に書いたように、公式サイトは未だテスト段階のようですから、今後はリンク集なども充実してくると思います。竹中英太郎記念館の館長さんが日記にお書きになっているように、スタンプラリーも始まっています。景品がボールペンではなくもっと永く記念になる物だと良いのにという気もしますが、私はスタンプ4つを確保できる美術館など訪問予定を組んでいます(^o^)
先日の記事に書いたように、公式サイトは未だテスト段階のようですから、今後はリンク集なども充実してくると思います。竹中英太郎記念館の館長さんが日記にお書きになっているように、スタンプラリーも始まっています。景品がボールペンではなくもっと永く記念になる物だと良いのにという気もしますが、私はスタンプ4つを確保できる美術館など訪問予定を組んでいます(^o^)









 ちょっと早目に出たのですが、「事例発表(13:30~)」に間に合えばよいと途中ブランチでゆっくりしているうちにハッと気が付いた、てっ!メッセがあるじゃん、これは早い時間から始まってるのではないか、それを見学した後で13時半からフォーラムだ! 急いでホテルに向かいましたが時間が迫っていてメッセを覗いた程度でフォーラム会場に入りました。
ちょっと早目に出たのですが、「事例発表(13:30~)」に間に合えばよいと途中ブランチでゆっくりしているうちにハッと気が付いた、てっ!メッセがあるじゃん、これは早い時間から始まってるのではないか、それを見学した後で13時半からフォーラムだ! 急いでホテルに向かいましたが時間が迫っていてメッセを覗いた程度でフォーラム会場に入りました。 事例発表に入る前に主催者挨拶、来賓の祝辞があり、ここで横内正明知事も出席されて祝辞を述べられました。
事例発表に入る前に主催者挨拶、来賓の祝辞があり、ここで横内正明知事も出席されて祝辞を述べられました。

 『分権時代、地域の決断~連携・協働・自立に向けて~』 と題するシンポジウムはお馴染み伊藤洋先生のコーディネイトでパネリストの方々の濃いお話が聞けました。平川南さんの「甲斐」とは「交(かひ)」、すなわち東海道と東山道とを交わらせる役目を大和朝廷から与えられた土地というのが語源であるとの話は目からウロコの思いでした。確かに県立博物館のテーマの中に昔から外との交流が盛んだったという特長が描かれていたように思います。
『分権時代、地域の決断~連携・協働・自立に向けて~』 と題するシンポジウムはお馴染み伊藤洋先生のコーディネイトでパネリストの方々の濃いお話が聞けました。平川南さんの「甲斐」とは「交(かひ)」、すなわち東海道と東山道とを交わらせる役目を大和朝廷から与えられた土地というのが語源であるとの話は目からウロコの思いでした。確かに県立博物館のテーマの中に昔から外との交流が盛んだったという特長が描かれていたように思います。 山梨総合研究所の渡辺利夫理事長は伊藤先生からの問いかけとして、東アジアから見た山梨という事を話されました。私は甲府に来て最初のインターネットサーチで山梨総合研究所の存在を知り、そこに渡辺利夫先生のお名前を見て驚いたのですが、じかにお話を聞くのは初めてです。中国や韓国から見た山梨は自然が豊かな土地ということだそうです。意外な気がしましたが、現地の状況は山紫水明の絵画にあるようなものとは違うのだそうです。だから山梨に来て緑豊かなさまに感嘆するということです。その点は私も同じ(^o^) その緑の山々に囲まれ過ぎていて街なかに緑地公園が少ない甲府、というのも外と内からの見る目の違いかも知れません。
山梨総合研究所の渡辺利夫理事長は伊藤先生からの問いかけとして、東アジアから見た山梨という事を話されました。私は甲府に来て最初のインターネットサーチで山梨総合研究所の存在を知り、そこに渡辺利夫先生のお名前を見て驚いたのですが、じかにお話を聞くのは初めてです。中国や韓国から見た山梨は自然が豊かな土地ということだそうです。意外な気がしましたが、現地の状況は山紫水明の絵画にあるようなものとは違うのだそうです。だから山梨に来て緑豊かなさまに感嘆するということです。その点は私も同じ(^o^) その緑の山々に囲まれ過ぎていて街なかに緑地公園が少ない甲府、というのも外と内からの見る目の違いかも知れません。







 シンプルなチキンカレーを注文しましたが、うん、この懐かしい雰囲気からすぐに思い出したのが渋谷百軒店(ひゃっけんだな)にある
シンプルなチキンカレーを注文しましたが、うん、この懐かしい雰囲気からすぐに思い出したのが渋谷百軒店(ひゃっけんだな)にある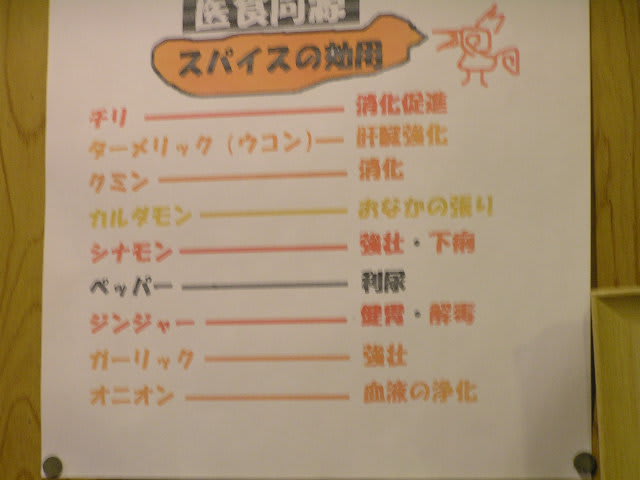
 お店の場所は電話で確認してから出かけました。岡島百貨店の紅梅通り入口の斜め前の位置でした。ちょっと急な階段を昇った二階です。
お店の場所は電話で確認してから出かけました。岡島百貨店の紅梅通り入口の斜め前の位置でした。ちょっと急な階段を昇った二階です。