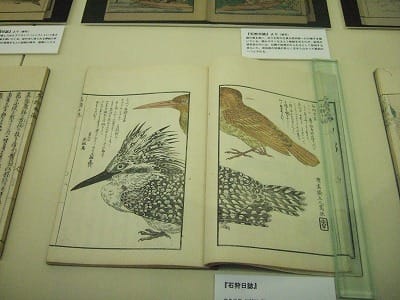しばらく前、仕事で日本の城を調べる機会がありました。そこで驚いたのは、建築時期が集中していること。天正8年(1580)から慶長5年(1600)の20年間に、姫路城、大阪城、松本城、二条城、熊本城など主要な城が18も築造されています。私が調べた35基のうち半分がこの時期に建てられているのです。
着工から竣工まで4~5年かかるでしょうから、当時の日本はお城の建設ラッシュだったわけで、ものすごい量の木材が消費されたはずです。「全国の良質なヒノキやケヤキが伐採され尽くしたのではないか」とさえ思えます。
そんなことから城郭建築に興味が湧いたので、連休中に彦根城を見学してきました。日本には昔のままの天守を有する城が12残っており、彦根城もその一つ。しかも、姫路城、松本城、犬山城と並ぶ国宝。築城400年のキャラクターとして生まれたのが「ひこにゃん」です。

しかし、彦根城はリサイクルで建てられたので、木材をあまり消費していません。理由はもちろんエコではなく、経費節約でもなく、きわめて政略的。
この近辺には石田三成の居城であった佐和山城をはじめ豊臣方の城があったので、それらを解体して西軍の残党の勢力を削ぐことが主な狙い。しかも再利用すれば早く築城できるという一石二鳥です。
考えたのは徳川家康。関ヶ原で軍功を上げた徳川四天王の一人・井伊直政に近江を与え、天守は大津城から、多聞櫓は佐和山城から、西の丸三重櫓は小谷城から移築したそうです。

石田三成の居城から移築した多聞櫓
下の写真は多聞櫓の柱ですが、カンナではなくチョウナではつった凹凸跡があります。カンナがなかった室町~戦国時代に築かれた佐和山城の木材をそのまま使ったのではないでしょうか。

城にはドラマがあって、特に姫路城の歴史は波乱万丈です。築城以来大きな戦さを経験せず、また明治維新で新政府軍と一触即発の状態に陥りながらも戦闘を回避。また、明治6年の廃城令で競売にかけられたものの、落札者が放置したために権利を失い、城のまま残りました。
さらに、多くの城が空襲で焼失する中、姫路城に着弾した焼夷弾は2発とも不発。姫路の町が焼け野原になったにもかかわらず城だけは残りました。そうした幸運が重なって、日本初の世界遺産になったわけです。

(Himeji Castle 11 by Shadowgate)
現在は平成の大改修で外観が隠れていますが、そういうドラマを知るとよけいに姫路城を見に行きたくなります。