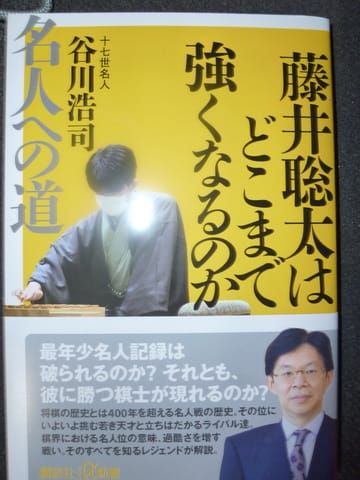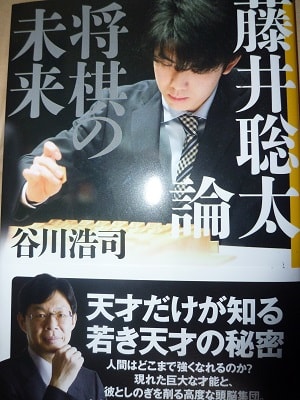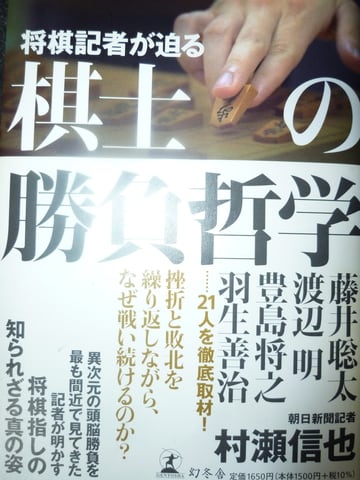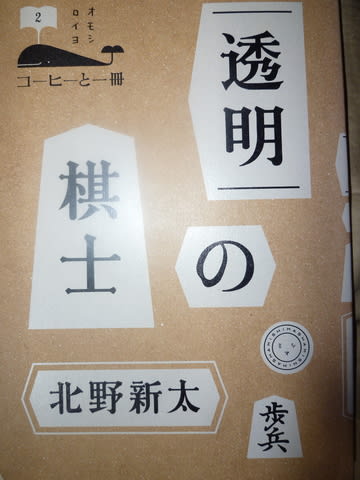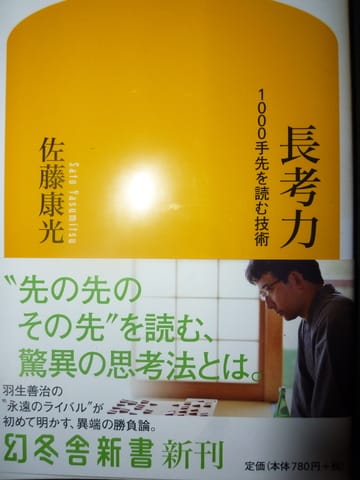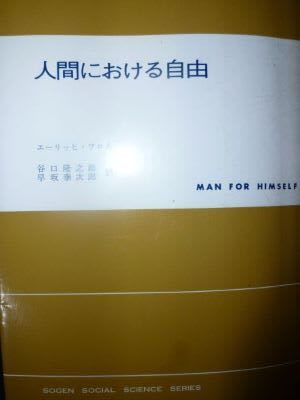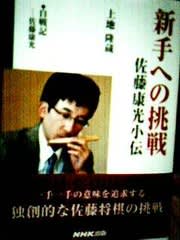スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。
2024年度の将棋大賞 が昨日,発表されました。棋聖防衛 ,王位防衛 ,王座防衛 ,竜王防衛 ,棋王防衛 ,王将防衛 ,NHK杯優勝 。年度の初めにタイトルをひとつ失いましたが,ほかはすべて防衛しましたので当然の受賞。2020年度 ,2021年度 ,2022年度 ,2023年度 に続き5年連続5度目の最優秀棋士賞。叡王奪取 ,順位戦昇級。残りひとつのタイトルを奪取しましたからこれも当然。2023年度に続き2年連続2度目の優秀棋士賞。王座挑戦 ,王将挑戦,名人挑戦。この部門は棋戦をふたつ優勝した丸山忠久九段との争い。3つという点の方が高く評価されたということでしょう。2019年度 以来となる2度目の敢闘賞。女流王位防衛 ,清麗防衛 ,女流王座防衛 ,倉敷藤花防衛 ,女流王将挑戦 ,白玲挑戦,マイナビ女子オープン挑戦 。まだ戦われている女流名人戦を含め,すべてのタイトル戦に出場。出産に伴う不戦敗もあってのものですから当然でしょう。2009年度 ,2010年度 ,2011年度 ,2012年度 ,2013年度 ,2015年度 ,2016年度 ,2017年度 ,2018年度 ,2019年度,2020年度,2021年度,2022年度,2023年度に続き10年連続15度目の最優秀女流棋士賞。マイナビ女子オープン防衛 ,女流王将防衛,白玲防衛,女流王座挑戦 ,女流名人挑戦,女流王位挑戦 。不戦勝での防衛もありましたがこちらも当然。2021年度,2022年度,2023年度に続き4年連続4度目の優秀女流棋士賞。白玲戦第一局 。総講 がありましたのでお寺に行きました。眼科検診 に行きました。この日は網膜症の検査のほかに,緑内障 の進行度合いを調べるための視野の検査も実施しました。どちらも変化はありませんでした。
『証言 羽生世代』は講談社現代新書から2020年12月20日に発売されたもので,著者は将棋記者の大川慎太郎。大川は『不屈の棋士 』を出版した後に,講談社の担当者から羽生世代を中心とした本の提案を受けていました。2018年の竜王戦に羽生が敗れたとき,この機会に棋士たちの証言を集めておいた方がよいと大川も思い,講談社のPR誌である『本』の2019年8月号から連載を開始。その後の情勢の変化,というのは主に藤井聡太の活躍ですが,そうしたことのために大川が書いた部分には修正があるとのことですが,ほとんどの部分は騎士へのインタビューになっていますから,内容に変更はないとしてよいでしょう。属性 attributumは雑多な考え方,それこそ眼鏡属性というようないい方が基本に忠実であるといえるような使われ方をしていたのですが,17世紀に入ってから哲学的に属性の概念notioが純化されました。いうまでもなくこの純化に貢献を果たしたのはデカルト René Descartesです。デカルトはあらゆる精神的実体に備わる本質的な特性として思惟Cogitatioを,そしてあらゆる物体的実体substantia corporeaに本質的に備わる特性として延長Extensioを示し,この思惟と延長だけを属性として認めました。デカルトは基本的に動物のことを,精神mensをもたない自動機械automa spiritualeとみなします。したがって人間以外の動物は延長の属性Extensionis attributumの様態modiということになります。延長というのは空間的な広がりを意味します。たとえばあるネコが年齢とともに色が白っぽくなったとしても,あるいは事故で1本の脚を失ってしまうというようなことがあったとしても,ネコがネコであることに変わりはないのですが,空間的な広がりをもたないネコというのはあり得ません。いい換えれば空間的な広がりを欠いてしまえば,ネコはネコであることはできなくなってしまうでしょう。つまりネコがネコとしてある,ありとあらゆる特性は,空間的な広がりなしにはあることも考えるconcipereこともできないということになります。したがってこの空間的な広がりを意味する延長は属性であるとデカルトはいいました。すなわちネコとは,物体的実体の属性である空間的な広がりが,ネコという形態を帯びているという意味になり,この意味においてネコは物体的実体のあるいは延長の属性の様態であるということに,デカルトの哲学のうちではなるのです。第一部定理一四 にあるように,実在する実体が神 Deusだけであるとスピノザが主張している点です。いい換えれば神以外には実体は存在しないのですから,デカルトが規定しているような精神的実体とか物体的実体といった実体が存在するということは認めません。そして実在する実体が神だけである以上,あらゆる属性は神の本性 essentiaを構成することになります。
『藤井聡太論 将棋の未来 』を書いた谷川浩司が翌年に出版した藤井論が『藤井聡太はどこまで強くなるのか』です。こちらも前のものと同じく,講談社+@新書から出版されました。翌年といいましたが,前のものが2021年5月の出版で,こちらは2023年1月です。僕が翌年といったのは,谷川によるあとがきが,前者は2021年4月で後者は2022年12月になっているからです。書簡五十 の冒頭で,ホッブズThomas Hobbesの国家論と自身の国家論の相違について,自然権jus naturaeという観点から説明していました。それは具体的には,ホッブズは自然権を国家Imperiumのうちにそのまま残していないけれど,スピノザはそれをそっくりそのまま残しているということです。自然権をそっくりそのまま国家においても残すということが何を意味しているのかということは,ここまでの國分の説明から明瞭になるでしょう。それは,自然権は人間に与えられている力potentiaと過不足なく重複しているので,国家においてもそれ自体でそれを制限することはできないし,それ以上のことを要求することもできないということです。つまりここにはふたつの意味が含まれているといえるでしょう。過不足ない力を不足させることもできないし増大させることもできないというふたつの意味です。
1日に2023年度の将棋大賞 の受賞者が発表されました。叡王防衛 ,名人奪取,棋聖防衛 ,王位防衛 ,王座挑戦 ,奪取 ,竜王防衛 ,王将防衛 ,棋王防衛 。棋戦は日本シリーズ優勝 。これはほかに選びようがありません。2020年度 ,2021年度 ,2022年度 に続き4年連続4度目の最優秀棋士賞です。勝率1位賞も受賞しています。竜王挑戦 ,棋王挑戦 ,叡王挑戦 。最優秀棋士が突出しているため,優秀棋士賞は票が割れました。永瀬拓矢九段との争いでしたが,竜王戦と叡王戦の挑戦者決定戦の結果が影響したように思います。優秀棋士賞は初受賞。最多対局賞と最多勝利賞も受賞しました。銀河戦優勝 。ここも永瀬九段との争い。銀河戦の本選での直接対決で勝ったというのもあるでしょうが,敢闘賞というのはよく頑張ったという主旨があり,永瀬九段に対してよく頑張ったというより,50代で銀河戦を優勝した丸山九段はよく頑張ったという意味合いの方がやや強かったということかもしれません。敢闘賞は初受賞。優勝 。新人王戦は決勝で負けましたが,伊藤七段と最多勝利賞を受賞していますからこれは当然の選出でしょう。女流王位防衛 ,清麗防衛 ,白玲挑戦,倉敷藤花防衛 ,女流王座防衛 ,女流名人挑戦,奪取 。八冠のうちの五冠を占めていますから当然でしょう。2009年度 ,2010年度 ,2011年度 ,2012年度 ,2013年度 ,2015年度 ,2016年度 ,2017年度 ,2018年度 ,2019年度 ,2020年度,2021年度,2022年度に続き9年連続14度目の最優秀女流棋士賞。清麗挑戦 ,女王防衛 ,倉敷藤花挑戦 ,女流王将防衛 ,白玲防衛 。こちらは残る三冠の覇者ですからやはり当然。2021年度,2022年度に続き3年連続3度目の優秀女流棋士賞。加藤桃子女流四段 でした。第二局 。両者は2023年度にタイトル戦で17局を戦いました。その中で最も内容が優れていたという評価を受けたのがこの一局だったということです。ステノ Nicola Stenoが過剰な信仰心を抱いていたとみていましたから,チルンハウス Ehrenfried Walther von Tschirnhausにも改宗を迫ったであろうといっています。ライプニッツ Gottfried Wilhelm Leibnizにこの手稿を見せてもよいかという打診をスピノザにしています。したがって,もしもそれを読むのにふさわしい人物がいるなら,それをその人に読ませてもよいと思っていたのは間違いありません。チルンハウスはこのときもステノのことをそのような人物だと思い,しかしスピノザはもう死んでいたのでその可否を問うことができず,自分の判断でステノに手稿を渡したところ,その手稿がチルンハウスの手に戻ってこなかったということは,考えられないことではありません。ただ,ステノが國分がみるように,チルンハウスに改宗を迫るような人物であったとしたら,そのような人に手稿を読ませるのは危険であると判断した可能性が高くなりますから,このケースは考えにくくなります。また,僕がみるように,改宗後のステノが,過剰な信仰心を抱いていた人物とはいえなかったとしても,改宗者には違いないのですから,やはりチルンハウスは手稿を読ませるのは危険であると判断しそうに思えます。とくにステノはこの年のうちに司教となって,プロテスタントのルター派が優勢であったドイツに移り,カトリックの布教活動に従事してそのまま死んでいます。このような経歴を考えれば,ステノはこの時点でカトリックの内部でそれなりの地位を占めていたと考えることができるわけで,そうであるならなおのことチルンハウスは手稿をステノに渡してしまうことの危険性を高く見積もれたのではないかと思うのです。
十七世名人の谷川浩司は藤井聡太について多くを語っています。その1冊が『藤井聡太論 将棋の未来』です。これは2021年5月19日に講談社@新書から発売になったもの。「おわりに」のところで二〇二一年四月と谷川は書いていますので,原稿はそのときまでにできていました。説明するまでもないでしょうが藤井は現在はすべてのタイトルを保持していますが,谷川がこれを書いた時点では棋聖と王位の二冠でした。つまりそのときまでに書かれた藤井聡太論であって,現時点ではまた谷川は藤井に対して別の見方をしている部分もあると踏まえる必要はあるでしょう。このことは谷川自身がいっていることでもあり,「はじめに」の中で谷川は,現時点での私なりの藤井聡太論を展開していくといっています。それは同時に,藤井の将棋が進化していくのと並行して,谷川自身の藤井聡太論も進化していくであろうということを,その時点で谷川が意識していたということでもあるでしょう。たぶん谷川は藤井の将棋がさらに進化していくであろうということについては,ある程度の確信をこの時点で有していたのだろうと僕は思います。フーコー Michel Foucaultは,デカルト René Descartesやスピノザが真理veritasの探究を始めるときに,それを強い決意decretumと共に開始したのは,そうした強い決意が,狂気を自身から引き剥がすために必要だったからだと指摘しています。他面からいえば,狂気から身を引き剥がすことが,デカルトやスピノザの時代においては重要なことであったとフーコーは指摘しているわけです。Histoire de la folie à l'âge classique 』は読んでいませんが,フーコーの全体的な主張からすると,このような解釈は恣意的なものではなく,それが指摘されている文脈において正しいか正しくないかは分かりませんが,少なくともフーコーの全体的な思想から俯瞰してみれば,ひどく誤った解釈を國分がしているということはあり得ないのであって,むしろフーコーの主張に沿ったものであるといえると思います。Discours de la méthode 』で,スピノザは『知性改善論 Tractatus de Intellectus Emendatione 』で,揃って強い決意を述べているということが,この時代の理性の地位が弱小なものであったということを示しているということなのです。
『透明の棋士 』の著者である北野新太の,「報知新聞の北野です」と同様に.棋士の記者会見でよく耳にするのが「朝日新聞の村瀬です」というフレーズです。北野が朝日新聞に転職したことによって,このふたりは現在は同僚になっています。その村瀬信也の著書が『棋士の勝負哲学』です。第二部定義七 でいわれている,多数の個体がすべてある結果effectusに対する原因causaとして,個々の活動 actioにおいて協力するような個物になるということです。現実的にはこのことはきわめて困難なことといわなければなりませんが,国家の最高権力者の合倫理性は,国家がこの方向へと進むことを目指すことにあるのであって,これに反するようなことは非倫理的といわなければなりません。そこで,もしも国家の最高権力者が,自分の子どもへの愛amorのゆえにその子どもを権力の中枢に抜擢するということがあるとすれば,それは国家を構成する市民の一致や融和を齎すよりは,亀裂とかあるいは最高権力者自身への政治的信頼の失墜という方向へ向かわせるでしょう。よってこのようなことをする最高権力者は,子どもを愛するという意味では合倫理的であったとしても,国家の最高権力者として合倫理的であるかといえばそういうわけではなく,むしろ非倫理的であるといわなければならないのです。ですから,僕は愛は一般的に合倫理的な感情affectusであるといいますが,個別の愛によって個別の人間に対して親切をなす人間が,全面的に合倫理的であるということを肯定しているわけではなく,その人間のその個別の愛だけでなくその他の事情を考慮すれば,その人間自身は非倫理的であるという場合があるということは認めます。
2022年度の将棋大賞 が3日に発表されました。防衛 ,棋聖防衛 ,王位防衛 ,竜王防衛 ,王将防衛 ,棋王挑戦 ,奪取 。名人挑戦。日本シリーズ ,銀河戦 ,朝日杯将棋オープン ,NHK杯 と出場できる棋戦ですべて優勝。文句のつけどころがない成績で当然の受賞。記録部門の最多勝利賞と勝率1位賞も受賞しています。2020年度 ,2021年度 に続き3年連続3度目の最優秀棋士賞です。渡辺明名人 。名人防衛。名人という大きなタイトルを防衛したことでの選出になりました。2005年度 ,2008年度 ,2010年度 ,2011年度 ,2015年度 ,2018年度 ,2020年度,2021年度に続き3年連続9度目の優秀棋士賞になります。優勝 。記録部門の最多対局賞も受賞しました。防衛 ,清麗挑戦 ,奪取 ,白玲挑戦,奪取 ,倉敷藤花防衛 ,女流王座防衛 。2009年度 ,2010年度,2011年度,2012年度 ,2013年度 ,2015年度,2016年度 ,2017年度 ,2018年度,2019年度 ,2020年度,2021年度に続き8年連続13度目の最優秀女流棋士賞です。防衛 ,倉敷藤花挑戦 ,女流王将挑戦 ,奪取 。女流名人挑戦,奪取 。記録部門の女流最多対局賞も受賞しました。2021年度に続き2年連続2度目の優秀女流棋士賞。王将戦第二局 。女流名局賞は女流王座戦第五局。名局賞の特別賞は朝日杯将棋オープン2回戦の藤井聡太竜王と増田康宏六段の将棋。終盤で後手の玉が延々と逃げ続けた一局です。個物 res singularisを構成する個体の数が多くなればなるほど,いい換えればあるひとつの個物が複雑になればなるほど,そうした個物一般とこの個物あるいはあの個物といわれるような個物との一般性のレベルの差は大きくなるだろうと僕は考えています。僕はあの人間あるいはかの人間といわれる人間と人間に共通する本性 essentiaによって規定される人間の間にある一般性のレベルの差は,あのティラノサウルスあるいはこのティラノサウルスといわれるティラノサウルスとティラノサウルスに共通の本性によって規定されるティラノサウルスとの間にある一般性のレベルの差よりも大きくなるといいましたが,それはこの理由によっています。人間というひとつの個物を構成する個体の数はティラノサウルスを構成する個体の数よりも多く,その分だけ人間の方がティラノサウルスよりも複雑な個物であることになり,なので個々の人間と人間一般との間の一般性のレベルの差は,個々のティラノサウルスとティラノサウルス一般との間にある一般性のレベルの差よりも大きくなると僕は考えるのです。
2002年に報知新聞に入社し,2010年ごろから同社で将棋を担当する記者として仕事をしていた北野新太が,今年の3月31日に報知新聞を退社するということをTwitterで告げたのは,僕にとっては残念な出来事でした。「報知新聞の北野です」というのは,たとえば棋士の記者会見などで必ずといっていいほど耳にするフレーズで,それに続く質問は優れたものが多いと感じていたからです。優秀な記者が将棋の取材から離れることは,将棋界にとっての損失だと僕は思うのです。ですから翌日の,朝日新聞に入社したというTwitterでの告知は,驚きであると同時に喜びでもありました。報知新聞はスポーツ新聞の中では将棋の記事は手厚いですが,一般紙である朝日新聞とは比べるべくもなく,むしろ北野の記事を目にする機会は増えると思えたからです。スピノザ『神学政治論』を読む 』の中では,スピノザの哲学で目指すものとスピノザの政治的実践との間の乖離の理由が,次のように説明されています。上野によれば,スピノザはエチカすなわち倫理学とポリチカすなわち政治学を異質なままにしておくのです。国家Civitasの論理からすれば,市民Civesは自己の権利jusの下にあるのではなくて,国家の権利の下にあります。しかし現実的に存在する人間は,理性ratioに従っている限りでは,たとえ国家の法に服していたとしても,判断においては自由libertasであって,自己の権利の下にあるのです。ここには明らかな乖離があるようにみえますが,スピノザは弁証法的に綜合しようとしないのです。要するに上野は,スピノザにとって倫理学と政治学は異質なもので,綜合する必要がないものだとみているのです。ただし,綜合する必要がないというのは,そのままにしておいて相反するわけではないという意味でもあるでしょう。神学・政治論 Tractatus Theologico-Politicus 』は,匿名とはいえ実際に出版された書物です。『エチカ』は未出版ですし,おそらく『神学・政治論』が発行された時点では,『エチカ』は現行の形態にはなっていませんでした。他面からいえば,現在の『エチカ』が完成形であるとすれば,『神学・政治論』が出版されたときには『エチカ』は未完成でした。なので『神学・政治論』の本文の中で,『エチカ』の文章に直接的に訴えるということは不可能だったのです。国家論 Tractatus Politicus 』は未完です。それはスピノザが書き終える前に死んでしまったからです。ということはその時点では『エチカ』は現在の形であったことになります。
谷川の辞任が突然のことであったため,佐藤の新会長 の就任も突然の事態ではあったものの,それは既定路線から外れるものではありませんでした。そのときに被害者であった三浦が,佐藤の就任を許容した,もっといえば好ましいこととも受け取れるような表現で発言したのも,谷川が辞任する決意を固めた時点で,おおよその流れが将棋連盟の中で決定していた,個々の棋士の胸の内で決定していたということを証しするひとつの事実であったのかもしれません。追い風 なしにそれを語ることはできないだろうとも思っていますが,女流棋戦の増設 やスポンサーの増加 はともかく,将棋会館の移転 という長年にわたっての大きな課題に目途を立てたのですから,棋士の間での佐藤の評価が概ね変わっていないであろうことは,容易に推測できますし,むしろその評価が高まっていたとしてもおかしくはないだろうと思います。課題 が残っているとも思うのです。いうまでもなくそれは,佐藤の後継者 はだれになるのかということです。米長から谷川,そして谷川から佐藤というのは,既定路線であったわけです。しかし佐藤の次の会長に関しては,既定といえるような路線が定まっているようには僕には思えないのです。もちろん佐藤は予定していたよりも早くに会長に就任したのですから,予定よりも長きにわたって会長を務めることになるのだろうと推測されます。とはいえ谷川の辞任が突然であったように,予期せぬことが起こる可能性は0ではないのです。早期に佐藤の後継者を育成するということがは,実は今の将棋連盟の最大の課題なのではないでしょうか。神学・政治論 Tractatus Theologico-Politicus 』で具体的に示されている例を用いるなら,理性 ratioに従って神Deusを愛しまた隣人を愛する者は敬虔pietasです。これと同様に,聖書の教えに従って神を愛しまた隣人を愛する人も敬虔です。しかし,徳virtusという観点からみるならこうはいえません。理性に従って神を愛しまた隣人を愛する者は有徳的であることになりますが,聖書に従って神を愛しまた隣人を愛する者は,有徳的であるとはいわれ得ず,無力impotentiaであるといわれなければならないのです。第四部定理五九 を参照すれば十分でしょう。この定理Propositioは,現実的に存在する人間が能動によってなすすべての行動を,受動によってもなすことがあるということを示すものではありません。しかし,受動感情によって決定されるすべての行動は,理性に従っても決定され得るのであれば,少なくとも受動によっても能動によっても同じ行動に決定される場合があることは明白でしょう。そしてその場合に,その行動が能動によって決定されるのであれば有徳的であるといわれ,受動によって決定されている場合は無力であるといわれるのです。第四部定理二〇 は,身体が健康であるなら有徳的で,身体が何らかの病気に罹患しているなら無力であるといっているというように解する余地があると思います。何らかの病気に罹患している身体は,自己の有 を維持することを放棄している身体であって,健康である身体は,それに対していえば自己の有を維持することに努めている身体であるとみることができるからです。ですがこの定理が示しているのはそのようなことではありません。つまりスピノザがここでそのようなことをいっているのではないという点に,解釈上の注意を要すると僕は考えています。第三部定理六 により,現実的に存在するどのようなものも,自己の有を維持することには努めますsuo esse perseverare conatur。
米長は佐藤に直談判 されたということは明かしていますが,そのときの心情については何も吐露していません。会長である自分に対して意見してきたことを不快に感じたかもしれませんし,逆にほかの方法ではなく一対一の場で自身の考えを伝えてきたことを好ましく思ったかもしれません。ただ,米長がそのときにどのように感じていたのだとしても,米長は自身の後継者 は谷川であると考えていたのですし,遅くとも谷川が理事になってからは,自身の病気のこともあり,谷川が会長になった後のことまでは考えていなかっただろうと推測されます。なので,佐藤が将棋連盟の会長として相応しいかどうかということについては,晩年は何も考えていなかったであろうと僕は思います。フロム Erich Seligmann Frommが示唆している自己関心と良心の間にある関連性とは,ごく簡潔にいうなら,自己関心が高いほど良心が働き,自己関心が低くなるほど良心が働くことが困難になるということです。このときフロムは文脈の中で,自己関心を生産性という語に置き換えています。フロムがいう生産性というのは,スピノザの哲学でいう能動actioと意味合いが一致すると解して間違いありません。つまり人間は,能動に傾くほど良心が働くのであり,受動passioに傾くほど良心が働くことは困難になるというようにフロムはいっていると解して差し支えありません。もちろんこれは関連性なのであって,能動が良心の原因causaとなるということでは必ずしもありません。むしろその逆もまた真verumなのです。つまり,現実的に存在する人間は,良心が働くほど能動的であることができ,良心が働かない場合は受動に隷属するのです。第四部定理三五 にあるように,人間の現実的本性 actualis essentiaは理性に従っている限りでは一致するからです。したがって,道徳的目標がどのようなものであったとしても,一致してその目標への道を進むことになるでしょう。それに対して,第三部定理三四 にあるように,受動状態においては人間は対立的であり得ますから,その目標がどのような目標であれ,各人が一致してその目標に向かって進むということはできないでしょう。第三部定義二 により,ある人間のなす事柄に対してその人間が十全な原因causa adaequataとなっているかそれとも部分的原因causa partialisとなっているのかということに帰せられるとフロムがみている点です。ここにある特徴があります。
米長が棋士とコンピュータソフトが公開の場で対戦することを禁じた後,最初のイベントとして開催されたのが,当時の竜王であった渡辺明とコンピュータソフトとの対戦でした。2007年3月21日のことです。新会長 に就任するにあたって,意外と大きな出来事であったという可能性は否定できないでしょう。反対感情 としての歓喜gaudiumは,自己満足acquiescentia in se ipsoと自己愛philautiaを分けて考えたとき,自己満足の一種であるなら推奨されますし,自己愛の一種であるなら推奨されません。ではどのような歓喜がこの場合の自己満足の一種となり,どのような歓喜がこの場合の自己愛の一種となってしまうのかを,もう少し具体的に検討してみます。
米長の死の要因となったのは前立腺癌でした。前立腺癌を罹患していること,そしてそのために放射線治療を受けているということは公表されていました。米長はそれでも会長職を続けたのですから,任期中は生きていられると思っていたのかもしれません。ただ,それほど多くの時間が自身に残されているわけではないということは理解していたでしょう。棋士たちを二分するようなことを,やや拙速とも思えるやり方で推進していったことには,そうした米長の感覚が影響していたのかもしれません。少なくとも谷川を理事にして自身の近くに置いたことと,米長が前立腺癌を罹患していたこととの間には,明らかに関係があったと僕は推測します。米長は自身の後継者,いい換えれば次期会長が必要であるということを,明確に意識していたのだと思います。現実的本性 actualis essentiaに反し,かつ非道徳的であるような感情affectusであっても,スピノザによって推奨されている感情があるということは,ここまでの説明から理解することができました。スピノザは敬虔pietasであること,いい換えれば人と人とが対立的にならないことを推奨するのですから,スピノザはそのために有益であるような受動感情は,悲しみtristitiaでも推奨することになるのです。第四部定理四系 によって,そうした感情を禁じるということはないにしても,とくに避けるべき感情といわれることになります。第三部諸感情の定義二八 の高慢superbiaです。この感情は喜び laetitiaですから,人間の現実的本性には反しません。しかし定義Definitioから明白なように,観念ideaとしてみた場合は混乱した観念idea inadaequataであり,したがって現実的に存在する人間が高慢という感情を感じるときには,必然的に働きを受けています。よって非道徳的です。そしてこの高慢は第三部定理二六備考 で狂気といわれています。つまりこの感情は,人間が理性に従って振る舞うのとは正反対の行動に向かわせるのです。また人と人とを対立させます。このことも高慢の定義から明らかなのでとくに説明するまでもないでしょう。そしてそれが理解できれば,スピノザがこの感情を徹底的に否定するのも当然だといえます。第三部諸感情の定義七 の憎しみodiumに属する感情です。これをスピノザが推奨していないのは,第四部定理四五系二 から理解することができるでしょう。また憎しみが人と人とを対立させるということは,第三部定理三九 から明白であるといえます。ですから憎しみに属する一連の感情をスピノザが推奨しないのは当然です。
女流棋戦の増設 ,スポンサーの増加 ,将棋会館の移転 の目途と,佐藤が新会長 になってからの体制は,過去に類をみないほどといっていい大きな仕事を次つぎと成し遂げました。というか,この体制は現在も継続しているのですから,成し遂げつつあるといった方がいいのかもしれません。ただ,僕は課題がないというわけではないと思っています。最後にそのことについて示して,この連載を終了させることにします。処分 を下したために,谷川の指名を受ける形で会長となりました。つまりこれは急遽の出来事であって,このときの状況から佐藤が新会長に選出されたことからしても,いずれは佐藤が会長になったのだろうと思われますし,谷川にも佐藤にもそういう意識はあったと僕は推測しますが,その時期に佐藤が会長に就任することは,予定外であったのは間違いないでしょう。第三部定理五九 は,能動的である喜びと欲望 cupiditasがあるといっていますが,すべての喜びと欲望が能動的であるといっているわけではありません。つまり,受動的な喜びもあれば受動的な欲望もあるわけです。その限りでは喜びも欲望も非道徳的なことになるのであって,それが能動的である限りにおいて,道徳的であるといわれるのです。第三部諸感情の定義一二 の希望spesや,第三部諸感情の定義二八 の高慢superbiaは,基本感情としては喜びの一種です。希望に関しては定義 Definitioの中でそのようにいわれていますし,高慢は第三部諸感情の定義二八説明 から分かるように自己愛 philautiaの特質とされていて,この自己愛というのは第三部諸感情の定義二五 の自己満足acquiescentia in se ipsoのことであって,それは喜びの一種です。しかるにこのふたつの感情については,その定義それ自体から明らかなように,観念ideaとしてみた場合には混乱した観念idea inadaequataであって,それは第三部定理一 によって受動です。なのでこれらの感情は喜びであっても必然的にnecessario非道徳的とされることになります。一方,必然的に能動とされるような感情はありません。したがって,それ自体で道徳的であるとされる感情があるわけではないのです。ですから,良心の呵責は非道徳的なことであるとされるのですが,何らかの道徳的な感情が前もってあるのではありません。感情は能動的である限りにおいては道徳的であり得るのであり,良心の呵責は能動的ではあり得ないので,それ自体で非道徳的であることになります。そしてすべての悲しみと,ある種の喜びおよび欲望は,それ自体で非道徳的であることになるのです。
女流棋戦の増設 とスポンサーの増加 は,佐藤が新会長 となってからの体制の実績といっていいでしょう。このほかにもうひとつ,この体制は大きな実績を残すことに成功しました。それが東西の将棋会館の移転に目途をつけたということです。追い風 が吹き始めたことを抜きには考えられないでしょう。ただ純粋になし得たことという観点だけでみるなら,今尾の将棋連盟の体制は,過去に類をみないほどの大きな仕事をした,あるいはしているといえるかもしれません。第三部諸感情の定義二〇 の憤慨indignatioであると思います。この感情は,害悪の観念を原因として伴っているからです。この憤慨は,定義 Definitioの中で直接的にそのようにいわれているわけではありませんが,他人に対して向かう感情です。それが自分自身に対して向かうと,良心の呵責ということになるのではないかと僕は思うのです。他面からいえば,良心の呵責というのは,自分自身に対して向かう憤慨であるといういい方が可能なのではないでしょうか。第三部諸感情の定義七 から分かるように,悲しみの一種です。ですから,僕がいった良心の呵責も憤慨も,同じように悲しみであるという点では変わるところはありません。ただ,憎しみというのは外部の原因の観念 idea cause externaeを伴った悲しみのことをいうのであり,僕がいう良心の呵責は外部の原因の観念を伴っているわけではありません。伴っているのは自分がなしたあるいはなすであろう害悪なのですから,それは外部に対していえば内部だからです。ですからこの意味での良心の呵責は悲しみの一種であっても,憎しみの一種ではないのです。他面からいえば,憎しみというのは外部に向かう感情なので,内部には向かいません。つまり自分で自分を憎むということは,スピノザの哲学では語義矛盾となるのです。とはいえ,自分で自分を憎むというのは,文法的にはあるいは慣用的な表現としては成立します。ですから,僕がいう良心の呵責を,自分で自分を憎むことの一種であると理解しても,間違いであるというわけではありません。ただスピノザの哲学では,そのようないい方は成立しないのだということは,理解しておいてください。
2021年度の将棋大賞 が1日に発表されています。防衛 ,叡王挑戦 ,奪取 。王位防衛 。竜王挑戦 ,奪取 。王将挑戦,奪取 。記録部門の最多対局賞と最多勝利賞も合わせて受賞。文句なしでしょう。2020年度 に続いて2年連続の最優秀棋士賞。渡辺明名人 。名人防衛。棋聖挑戦 。棋王防衛 。これも当然。2005年度 ,2008年度 ,2010年度 ,2011年度 ,2015年度 ,2018年度 ,2020年度に続き2年連続8度目の優秀棋士賞。銀河戦 と朝日杯将棋オープン に優勝。タイトル戦に出場しないでの受賞は珍しいケースかもしれません。同じようにふたつの棋戦で優勝し,王位に挑戦した豊島九段の方が上だったような気もします。敢闘賞は初受賞。優勝 。記録部門の勝率一位賞も受賞。これは妥当なところでしょう。初受賞。防衛 。女流王将挑戦 ,奪取 。倉敷藤花防衛 。女流王座挑戦 ,奪取 。マイナビ女子オープン挑戦 。これも当然。2009年度 ,2010年度,2011年度,2012年度 ,2013年度 ,2015年度,2016年度 ,2017年度 ,2018年度,2019年度 ,2020年度に続き7年連続12度目の最優秀女流棋士賞。防衛 。白玲獲得 。女流王位挑戦 。こちらも当然。この年度が初の受賞対象でした。第二局 でした。Korte Verhandeling van God / de Mensch en deszelfs Welstand 』では良心の呵責conscientiae morsusが後悔poenitentiaの同類感情とされていました。後悔は『エチカ』でも定義されています。第三部諸感情の定義二七 です。そこでは,僕たちが自由な決意decretumによってなしたと信じる行為の観念ideaを伴った悲しみtristitiaが後悔といわれています。このとき,自由な決意によってなしたということは,字義通りに積極的に解する必要はありません。僕たちが何かある行為をなして,後にその行為を表象して悲しみを感じたときに,もしもその行為をなさないことも可能であったと表象されるなら,僕たちは後悔するとスピノザはいっているのです。他面からいえば,ある行為について,自分はその行為をなすこともできたしなさないこともできたと認識した場合には,僕たちはその行為を自分の自由な決意によってなしたと判断しているということです。第三部諸感情の定義一七 でいわれている落胆conscientiae morsusについて,それは後悔の類似感情であるというのは僕には難しいと思えます。少なくともこの場合の良心の呵責すなわち落胆は,事前にそれと関係する希望spesおよび不安metusという感情がないならば,現実的に存在する人間の精神mens humanaのうちには発生し得ない感情affectusですが,後悔の方はそのような感情であるとはいえないからです。よって『エチカ』で定義されている良心の呵責が,『エチカ』でいわれている後悔の類似感情であるとはいえないでしょう。したがってスピノザは,良心の呵責が後悔の類似感情であるという点については.『短論文』のときと『エチカ』のときで,考え方を改めている,あるいはそれぞれの感情を見直しているといっていいと思います。