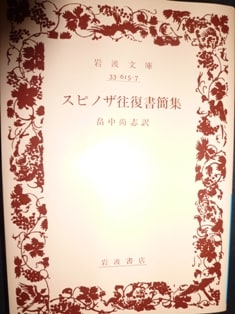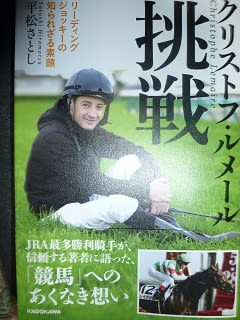スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。
日本時間で20日の深夜にイギリスのヨーク競馬場で行われたインターナショナルステークスGⅠ 芝2050m。哲学者スピノザの叡智 Think Least of Death 』に示されている第四部定義八 の訳については,僕は感心しません。徳 virtusは人間の本性 natura humanaである。ただしそれは人間が十全な原因causa adaequataである限りである。というのは文章構造としては倒置法に該当し,事物の定義Definitioに倒置法を採用するのは不適切だと僕は考えるからです。なのでここは,徳は人間が十全な原因である限りで人間の本性であるとするべきです。
昨日の第3回ルーキーズサマーカップ 。御神本騎手が病気のためロードレイジングは笹川騎手に変更。ロードレイジング はデビューから3連勝で南関東重賞制覇。その連勝がともに出遅れて差してきてのものでしたので,展開面での不安はあまりありませんでした。浦和が初コースになる点が最大の不安点でしたが,かなり器用に走れましたのでまったく問題になりませんでした。現時点での完成度でほかの馬との差が大きかったように思います。父はモズアスコット 。母の父はネオユニヴァース 。黒潮盃 に続く南関東重賞25勝目。第2回 からの連覇でルーキーズサマーカップ2勝目。管理している川崎の加藤誠一調教師は開業から13年9ヶ月で南関東重賞初制覇。哲学者スピノザの叡智 Think Least of Death 』の中に出てくるのは当然ですし,場合によっては『エチカ』の定義Definitioや公理Axioma,また定理Propositioといったものをそのまま利用するということもあり得るでしょう。しかしその文章はナドラーが書いているわけですから,当然ながら英語で書かれることになります。そしてその英語がそのまま和訳されることになります。よって『哲学者スピノザの叡智』の中に,スピノザが書いたものが重訳される,つまりラテン語が一旦は英語に訳され,その英語がまた日本語に訳されるという事態が生じることになります。要するに,ナドラーの地の文章の和訳の中に,重訳されたスピノザの文章や概念が入り込んでくることになるのです。第四部定義八 を示しましょう。『哲学者スピノザの叡智』出てくるこの定義は,「私は,美徳と力を同じものであると理解する。すなわち,美徳が人に関係している限り,それはまさに人間の本質あるいは本性である。そして,それはその人の本性の法則のみを通して理解される何かを引き起こす力を,その人がもっているときに限られる」。
書簡二十八 および書簡三十七 はラテン語で書かれた可能性は高く,それはバウメーステル Johannes Bouwmeesterの経歴から,バウメーステルがラテン語を解したからだといいました。この経歴の部分を説明しておきましょう。マイエル Lodewijk Meyerは,同一の秘密結社に所属していました。この秘密結社が『ハイ・イブン・ヤクザーン』という,元はアラビア語で書かれた小説のオランダ語訳版の出版に関わっています。小説といってもこれは宗教批判を含んだもので,アラビア語ですからイスラムと関係するのですが,内容的には『神学・政治論 Tractatus Theologico-Politicus 』と重なる部分をもっていて,とくにスピノザがその中で,服従 obedientiaを教える聖書の有用性を説いているのと同一視することができるような内容が含まれています。リューウェルツ Jan Rieuwertszでした。哲学者スピノザの叡智 』のうち,ナドラーSteven Nadlerの論考とは直接的には関連しないことをひとつだけ指摘しておきます。これは訳語,日本語の訳語のことです。この本を読んでいると,なぜこの種の訳語上の問題が出てくるのかということが僕には推測できましたので,まずはそのことから始めます。ただしこれはあくまでも僕の推測ですから,これから僕が述べていくことが確実な事実であるというようには理解しないようにお願いします。Opera Posthuma に掲載されたものについてはそれを原文で読むことができ,単に読むことができるわけではなくてその意味を解することができるのだろうと僕には思えます。ただナドラーはイギリス人ですから,最も親しんでいる言語は英語であって,ラテン語というのはある年齢に達してから習得した言語です。ですからナドラーが読み込んでいるスピノザの文章は,スピノザが記したラテン語であるよりは,そのラテン語の英訳版であると思われます。つまり,たとえば『エチカ』でいえば,ナドラーが最も深く読み込んでいるのは英訳版の『エチカ』であって,その英訳版の『エチカ』に基づいてナドラーの思考は進んでいると想定されます。そしてナドラー自身が執筆するのは当然ながら英語です。つまりナドラーは英訳版のスピノザの書物に親しみ,それを基に考察し,そして英語で文章を書いているということになります。De Nagelate Schriften が第一の原版となるでしょう。もちろん翻訳者が,各国の言語に訳された『エチカ』を参照するということはあるでしょうが,原版はスピノザが書いたものでありそのオランダ語訳なのであって,英訳された『エチカ』が英語から日本語に翻訳されるということは絶対にありません。
17日に函館競輪場 で行われた第68回オールスター競輪の決勝 。並びは吉田‐佐藤の茨城,脇本‐寺崎‐古性‐南の近畿,太田‐岩津の岡山で松本は単騎。第五部定理四二備考 で稀でありまた困難difficiliaであるといっている立場を,それでもそこを目指していくということも意味があるし,それは立派なことであると僕は思います。ただそこを目指していく際にも,スピノザがそれは稀であり困難であるといっていること,とくにその根拠になるであろう第四部定理三 ,第四部定理四 ,第四部定理四系 といった一連のスピノザの主張に気を留めておくべきなのであって,自身が受動的に振舞うこともあり得るということには,常に留意するべきであると僕は思います。
日本時間で昨日の夜にフランスのドーヴィル競馬場で行われたジャックルマロワ賞GⅠ 芝1600m。第四部定理五四備考 で,害悪よりも利益utilitasを齎すといわれているとき,そこで利益を齎されるのは,この備考Scholiumで示されている諸々の感情affectusに流される人のことではなく,そうした人びとと共に暮らし,また自分自身もそうした感情に流されているであろう共同社会状態status civilisの人びとのことであり,また共同社会状態そのもののことです。このことはこの備考の後続部分 から理解できます。そしてその後でスピノザは,民衆は恐れを知らないときに最も恐るべきものであるという意味のことをいっています。国家論 Tractatus Politicus 』の中に,「彼らは恐れを持たざる時に恐ろし」といわれていると記されている部分があり,これは『エチカ』のその記述と似ています。元はタキトゥスCornelius Tacitusがこのようなことをいっていたようで,スピノザはそれを踏まえているのでしょう。もっとも,『国家論』のこの部分の記述は,民衆は恐れを知らないときに恐ろしいといわれているけれども,人間の本性natura humanaは民衆であろうと支配者であろうと同一なので,恐れを知らない支配者も恐ろしいといわれなければならないという文脈になっています。ですから『エチカ』のこの部分も,とくに民衆だけを対象としてこのようにいわれているわけではなくて,支配者に対しても同じことをスピノザはいうと想定しておいた方がいいでしょう。神学・政治論 Tractatus Theologico-Politicus 』と『エチカ』では異なっているのですが,『神学・政治論』でいわれていた意味での敬虔は,『エチカ』では別の形であれ生かされているのであり,スピノザの思想は変化していないとみるべきだと思います。
日本時間で昨晩にフランスのドーヴィル競馬場で行われたギヨームドルナノ賞GⅡ 芝2000m。アロヒアリイ は重賞初制覇。ただこの馬は新馬を勝った後,1勝クラスの2着を挟んで弥生賞で3着。権利を得たので出走した皐月賞は8着でしたがこれが全成績。ですから素質があるということは確かで,海外とはいえGⅡなら相手次第で勝ててもおかしくありませんでした。ヨーロッパの競馬に特有のスローペースを逃げ切っての勝利なので,どのくらいの能力があるのかということをこのレースから測るのは難しいですが,もっと上のクラスで通用する可能性はあるでしょう。父はドゥラメンテ 。母の父はオルフェーヴル 。4代母がバレークイーン で母のふたつ上の半兄に2017年の青葉賞を勝ったアドミラブル 。Alohi Aliiはハワイ語で輝く王。日本馬による海外重賞制覇はクイーンエリザベスⅡ世カップ 以来。フランスでは2021年のフォワ賞 以来。UAEダービー 以来の日本馬に騎乗しての海外重賞13勝目。管理している田中博康調教師は海外重賞初勝利。神学・政治論 Tractatus Theologico-Politicus 』の中でははっきりとした形で示しましたが,『エチカ』ではこの観点が明らかに後退してしまっているのも事実です。『神学・政治論』では,自由の人や賢者viriest sapientisが採用する行動という意味で用いられていた敬虔という概念notioは,第四部定理三七備考一 で,理性 ratioの導きに従って生活することから生じる善行なそうとする欲望cupiditasと規定されることになったからです。よって岩波文庫版の『エチカ』では,これが『神学・政治論』でいわれている敬虔とあまりに異なっているため,道義心pietasと訳されることになりました。第五部定理二八 をみる限り,そういうことをスピノザはあまり想定していないと思われます。なので『神学・政治論』でいわれている敬虔という規準を,『エチカ』にそのまま適用してしまうと,この規準はナドラーが示している規準と何ら変わらなくなってしまうのです。第四部定理五四備考 では,いくつかの受動感情が害悪よりも利益utilitasを齎すとされていますが,その理由というのは備考Scholiumの文言にもある通り,人間が理性の指図によって生活することが稀であるから,つまり自由の人として生活することが稀であるからとされていて,ここに示されている感情affectusは,受動passioによってそうした人びとを自由の人と同じ行動に導くからだとしか考えられないからです。
スピノザがブレイエンベルフ の人物像を誤解したのは,書簡十八 においては真理veritasを探究するにあたって真理そのもの以外には何の目的finisももっていないといっていたブレイエンベルフが,書簡二十 では哲学をする際の根本原則として,知性 の明瞭判然たる概念notioのほかに,啓示された神Deusのことばをあげたからです。したがってブレイエンベルフが最初から根本原則をスピノザに伝えておけば,スピノザの誤解は生じなかったのであり,スピノザとブレイエンベルフとの関係は現にあったのとは別の形になっていただろうと想定されます。書簡十九 を受け取った後で,根本原則として神のことばというのをあげているのですから,スピノザが自身のことを誤解しているということについては,たぶん書簡十九を読んだ時点で理解したのだろうと思います。他面からいえば,自身が神のことばも哲学する際の根本原則としているということを,スピノザに伝えておかなければならないということを悟ったのです。
昨晩の第29回北海道スプリントカップ 。ヤマニンチェルキ は重賞初制覇。3走前にオープンの勝利があり,ここは優勝候補の1頭。前走のオープンは大敗していたのですが,これは古馬相手のレースでしたから仕方がないでしょう。前々走は2着馬に負けていたのですが,距離短縮で逆転した形。したがって1400mよりも1200mの方がよいのだと思われます。母の父は2002年の京成杯を勝ったヤマニンセラフィム 。Cerchiはイタリア語で探す。JBC2歳優駿 以来の重賞4勝目。北海道スプリントカップは初勝利。管理している中村直也調教師も北海道スプリントカップ初勝利。第一部公理三 から理解できるように,スピノザの哲学では一定の原因 causaが与えられると必然的にnecessario結果effectusが生じ,何の原因も与えられないのであれば結果が生じることはありません。これを結果の方からみれば,何らかの結果が生じるためにはその結果を生じさせるための必然的なnecessarius原因が必要とされ,そうした原因がないのであればその結果は生じ得なかったということです。第五部定理四二備考 でいわれているような,稀なものとはならないでしょうし,現実的に存在している人間にとって困難difficiliaでもないでしょう。
高知から1頭が遠征してきた昨晩の第59回黒潮盃 。マウンテンローレル は南関東重賞初挑戦での優勝。これまで5勝,2着1回,3着1回と安定した成績を残していて,4連勝中。オープンを連勝していましたので,実績も十分でした。ペースが上がらなかったため,道中の位置取りは結果に大きく影響したかもしれません。崩れていない馬なので今後も注目でしょう。母の父はキングカメハメハ 。祖母の6つ上の全兄が1998年の北海道3歳優駿を勝ったキングオブサンデー で,5つ上の全兄が2003年に京都ジャンプステークス,小倉サマージャンプ,阪神ジャンプステークス,京都ハイジャンプを勝ったウインマーベラス 。習志野きらっとスプリント に続く南関東重賞24勝目。第52回 以来となる7年ぶりの黒潮盃2勝目。管理している大井の福田真広調教師 は南関東重賞3勝目。黒潮盃は初勝利。理性 ratioに従ってその行動をしている場合は,その行動をしているのがだれであったとしても同じ行動をすることになります。このことは第四部定理三五 から明らかであるといわなければなりません。
第四部定理六五 には系Corollariumが付せられています。理性の導きに従って我々は,より大なる善のためにより小なる悪に就き,またより大なる悪の原因たるより小なる善を断念するであろう 」。第四部定理六三系 により,僕たちは理性に従う限りでは,より大なる善のためにはより小なる悪に就くことになりますし,より大なる悪を逃れるためにより小なる善を忌避することになるのです。第二部定理四四系二 にあるように,ものをある永遠の相aeternitatis specieの下に認識するpercipereことが理性の本性natura Rationisに属しているからです。このゆえに僕たちは第四部定理六二 にあるように,観念ideaが過去と関係しているか現在と関係しているか未来と関係しているかということとは無関係に,同じようにその観念を観想しますcontemplari。よって未来の悪の観念と現在の善の観念を同じように観想するために,未来の悪を回避するために現在の善を忌避することになります。同様に未来の善の観念と現在の悪を同じように観想するために,未来の善を享受するために現在の悪を甘受することになるのです。こうしたことが僕たちに生じるのが,僕たちが理性に従っている場合だけであるということは,この理由によります。神学・政治論 Tractatus Theologico-Politicus 』でいわれている敬虔pietasであるというのが僕の考えです。つまりこの場合は,合倫理性の規準が,ナドラーSteven Nadlerが示している規準よりは緩やかになっているのであって,ナドラーの規準だと自由の人だけが合倫理的で奴隷は非倫理的であるという結論になりますが,敬虔という規準で区分すれば,自由の人が合倫理的であるということは変わりはありませんが,奴隷であるから非倫理的であることにはならず,合倫理的でもあり得ることになります。