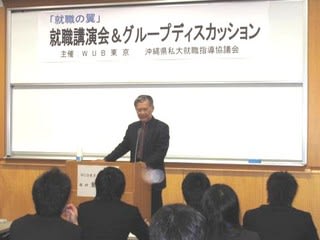当社の県出身大卒出身採用は累積75名、現定着率は15名の20%。その内訳はグラフで示すようにこれまで県立芸大以外の県内全6大学からの採用実績があるが、採用・定着共に圧倒的に琉球大学が多い。以下、その経緯と理由を開陳する。
創業5年目の昭和59年は日本経済のバブル絶頂期とも言うべき時代で沖縄には富士通に次いで日電が子会社を設立、進出、この日本有数のコンピューター両子会社が琉大電子工学系の卒業生の大半を数10人単位で根こそぎ掻っ攫って行く時代でした。あまつさえ、琉大工学系卒業は沖縄電力、公務員、教職が3大志望先で、その後にNTT、富士通、日電、日立と大手電機メーカーと続く。当時はベンチャー等見向きもされず、まして創業5年目の当社が琉大工学卒業生を採用する等至難の業だった。
そんな最中私は何度も琉大、それも教授の研究ゼミ室に通い、お願いして会社説明会の機会を頂いた。その中に当社琉大入社一期生として、電力も公務員も受けず当社に入社したのが現在勤続23年目の沖縄事業所長である。
当時私が臆せず琉大に通ったのは私の高校同期が10名以上琉大教授を勤めており、現ポリテックカレッジの校長を務めている機械工学の屋良教授の部屋を琉大の当社事務所のように使わして頂き、各教授ゼミ教室に通いました。爾来当時の短大生を含め30名の卒業生を採用、現在11名が勤続定着している。ここ数年は院卒が毎年入社している。
県内大卒社員中、琉大生が多いのはその他に以下の事由があると思う。
①琉大にはIT業である当社が求める人材を教育、供給する情報、電子工学部があるのに対し、県内他大学にも情報経営的な専攻科があるとは言え、どちらかと 言えば文系。さらにIT業界は専門職の色彩が強いため大学院のある琉大生が馴 染み易い点もあるようです。事実定着している琉大出身者の8割が工学系出身で その内4名は院卒です。
②もう一つの理由は琉大には比較的本土・他府県出身在学が多く、彼等は就職対象として、当社のような沖縄に関連がある本土企業を注目すること。現実の当社在席の琉大OB中3名が本土出身。
③さらにはわずか一年とは言え、かって私が琉大に在学したのもどこか作用しているのかも知れません。
女性の最長勤続は今年で18年。現在4年制大になったキリスト教学院卒が一人頑張っている。配偶者も県出身勤続21年目の社員同士で共に本社勤務。

(06年、琉球大学同窓会関東支部20周年で報告挨拶)
創業5年目の昭和59年は日本経済のバブル絶頂期とも言うべき時代で沖縄には富士通に次いで日電が子会社を設立、進出、この日本有数のコンピューター両子会社が琉大電子工学系の卒業生の大半を数10人単位で根こそぎ掻っ攫って行く時代でした。あまつさえ、琉大工学系卒業は沖縄電力、公務員、教職が3大志望先で、その後にNTT、富士通、日電、日立と大手電機メーカーと続く。当時はベンチャー等見向きもされず、まして創業5年目の当社が琉大工学卒業生を採用する等至難の業だった。
そんな最中私は何度も琉大、それも教授の研究ゼミ室に通い、お願いして会社説明会の機会を頂いた。その中に当社琉大入社一期生として、電力も公務員も受けず当社に入社したのが現在勤続23年目の沖縄事業所長である。
当時私が臆せず琉大に通ったのは私の高校同期が10名以上琉大教授を勤めており、現ポリテックカレッジの校長を務めている機械工学の屋良教授の部屋を琉大の当社事務所のように使わして頂き、各教授ゼミ教室に通いました。爾来当時の短大生を含め30名の卒業生を採用、現在11名が勤続定着している。ここ数年は院卒が毎年入社している。
県内大卒社員中、琉大生が多いのはその他に以下の事由があると思う。
①琉大にはIT業である当社が求める人材を教育、供給する情報、電子工学部があるのに対し、県内他大学にも情報経営的な専攻科があるとは言え、どちらかと 言えば文系。さらにIT業界は専門職の色彩が強いため大学院のある琉大生が馴 染み易い点もあるようです。事実定着している琉大出身者の8割が工学系出身で その内4名は院卒です。
②もう一つの理由は琉大には比較的本土・他府県出身在学が多く、彼等は就職対象として、当社のような沖縄に関連がある本土企業を注目すること。現実の当社在席の琉大OB中3名が本土出身。
③さらにはわずか一年とは言え、かって私が琉大に在学したのもどこか作用しているのかも知れません。
女性の最長勤続は今年で18年。現在4年制大になったキリスト教学院卒が一人頑張っている。配偶者も県出身勤続21年目の社員同士で共に本社勤務。

(06年、琉球大学同窓会関東支部20周年で報告挨拶)