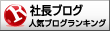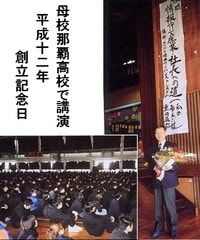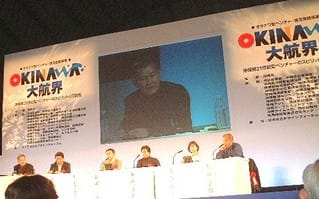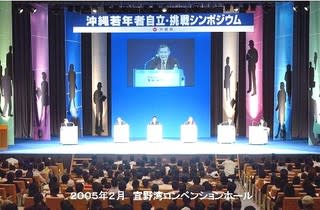先週終了した沖縄県職場実習高校生4名から早速、以下のような礼状が届きました。引率教師の指導跡が伺えますが、個々の感想も滲んでいます。イニシャルとは言え、ご本人達の承諾なく敢えて紹介したのは後に続く後輩諸君の参考になればと考えました。
(未来工科高 H君より)
企業職場体験の三日間、会社の改装等でお忙しい中時間をつくっていただき本当にありがとうございました。学校では聞けないような県外で就職する心構えが聞けて、私のような県外就職希望者にとって、とてもいい事を聞くことや体験をすることができました。お世話をして下さった社員の皆様、ありがとうございました。
(八重山商工 N君より)
企業職場体験実習をさせていただき、ありがとうございました。三日間という短い間でしたが、社会人としての心構えや必要な物。又、必要とされている物が何なのか分かった気がします。この体験を基に進路を考えたいと思います。会長並びにお世話をして下さった社員の皆様、貴重な体験をさせていただき、本当にありがとうございました。
(浦添工業高M君より)
県外企業体験実習では大変お世話になりました。沖縄に居ては経験する事の出来ない県外の雰囲気や生活を身を持って経験する事が出来ました。また、先輩の話など貴重な時間を過ごす事が出来ました。今回経験したことを糧にして、今後の自分の進路に生かしていきたいと思います。会長、お世話をして下さった皆様、本当にお世話になりました。
(名護商工高 N君より)
三日間の就職体験実習で大変お世話になりました。初めてのHTMLでやり方もまったく分からず、出来るのかと不安でしたが(講師の方)のおかげで見事完成することができました。この体験で得た経験を生かし、今後の就職活動で役立てることが出来るように努力し、私も御社のようにパソコンを使う会社へ就職できるように頑張りたいです。今回の職場体験の間、会長、お世話をして下さった皆様方、本当にご親切にしていただき、ありがとうございました。
(未来工科高 H君より)
企業職場体験の三日間、会社の改装等でお忙しい中時間をつくっていただき本当にありがとうございました。学校では聞けないような県外で就職する心構えが聞けて、私のような県外就職希望者にとって、とてもいい事を聞くことや体験をすることができました。お世話をして下さった社員の皆様、ありがとうございました。
(八重山商工 N君より)
企業職場体験実習をさせていただき、ありがとうございました。三日間という短い間でしたが、社会人としての心構えや必要な物。又、必要とされている物が何なのか分かった気がします。この体験を基に進路を考えたいと思います。会長並びにお世話をして下さった社員の皆様、貴重な体験をさせていただき、本当にありがとうございました。
(浦添工業高M君より)
県外企業体験実習では大変お世話になりました。沖縄に居ては経験する事の出来ない県外の雰囲気や生活を身を持って経験する事が出来ました。また、先輩の話など貴重な時間を過ごす事が出来ました。今回経験したことを糧にして、今後の自分の進路に生かしていきたいと思います。会長、お世話をして下さった皆様、本当にお世話になりました。
(名護商工高 N君より)
三日間の就職体験実習で大変お世話になりました。初めてのHTMLでやり方もまったく分からず、出来るのかと不安でしたが(講師の方)のおかげで見事完成することができました。この体験で得た経験を生かし、今後の就職活動で役立てることが出来るように努力し、私も御社のようにパソコンを使う会社へ就職できるように頑張りたいです。今回の職場体験の間、会長、お世話をして下さった皆様方、本当にご親切にしていただき、ありがとうございました。