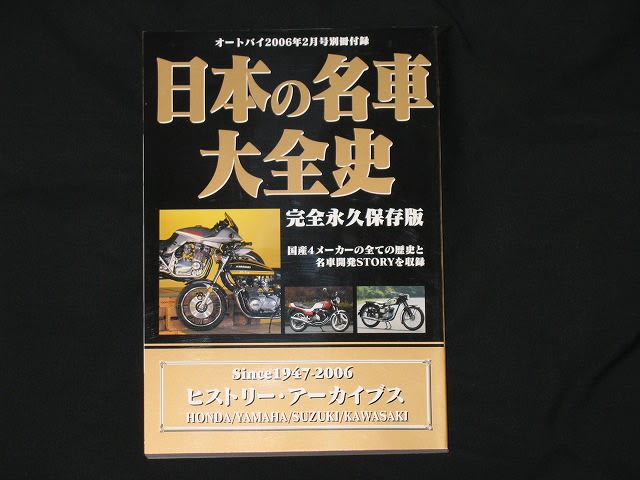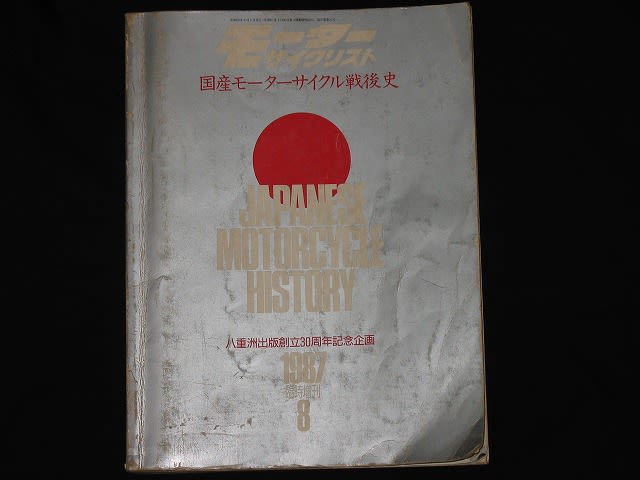人気blogランキングへ
ワタシが本題の禅とオートバイ修理技術を購読したのはカレコレ10年ほど前でしょうか。あらましは解説とレビューを読んでも良く分かりませんが、1970年代にアメリカでベストセラーになったそうです。日本で和訳されたのは1990年ですが、意外と有名であり、読んだことはないが題名は知っているという声も多く聞きます。
ワタシが購読するキッカケは書店で見かけ題名に引かれたのですが、開いてみると難解(翻訳者もそう言っています)でしかも700ページもあり、薄めの文庫本であれば一晩で読んでしまうワタシも、休み休み読んで2ヶ月くらい掛かったのではないでしょうか。
10年前の記憶で申し訳ありませんけれど、電気ショック治療により記憶を失った大学教授が、今までと変ってしまった父親に戸惑う幼い息子と一緒にバイクに乗り旅行するノンフィクションです。
禅とオートバイ修理技術(以下の文の引用先)
出会いは某市のグルーヴ本店でした.
「解かるヒトにだけ解かればいい」
という札とともに平積みにされていました.
いつ見てもうずたかく積まれており,
店長の趣味だけで置かれたことが一目瞭然でした.
この本は副題を「価値の探求」といいます.
難解です.しかし,私の心を突き抜ける本です.
私の仲間たちのバイブルです.
電気ショック療法で記憶をなくした著者と,
「お父さんなのだけれど,お父さんでなくなってしまった」
ことに戸惑いを覚える幼い息子との
オートバイでの旅の中で
オートバイのメンテナンスを例にとり,
物事の捉え方,考え方を書いてあるノン・フィクションです.
確かに,オートバイに乗っているときというのは
考える時間になりがちです.
私は著者ほど理論だった考え方は出来ないし,
哲学もありません.
しかし,私もやはり“考える葦”なのです.
内容を一部を以下に記します.
《古典的な理解とロマン的な理解》
【古典的な理解】
理性,または法則によって前進する.
すなわち,理性や法則が思考や行為の根本形式である.
例えばオートバイのメンテナンスは古典的である.
この理解様式には時に表面的な醜さが見出される.
しかし,「古典美学」というものがあり,
ロマン的なニンゲンはその緻密さ故に見逃しがちであるが,
古典的な表現様式とは
率直で飾り気がなく,理知的で,入念な釣り合いのもとに
簡潔に表現されている.
その意図は感情を奮い立たせることではなく
混沌から秩序を引き出し,
未知なるものを解き明かすことである.
それは自由で自然なものではなく,
表現の一つ一つが制御されている.
そしてこの表現様式の価値は
制御を維持するする技術によって評価される.
このような古典的様式から見るロマン的様式とは,
軽薄で一貫性がなく,信用ならない.実体がない.
寄生動物のようで,社会のお荷物である,となる.
【ロマン的な理解】
インスピレーションと想像力に富み,
直感的かつ創造的である.
感情,直感,感覚的分別によって前進する.
感情が事実より優位で,「科学」にたいする「芸術」は
しばしばロマン的である.
例えば,オートバイに乗ることはロマン的である.
ロマン的様式から見る古典的様式とは
機械のメンテナンスそのもので,
泥や油,基本構造に関する専門知識,
部品と構成部分とその相互関係,
全てが計算され,測定され,証明されなければならない.
退屈で,扱いにくく,醜く,果てしなく暗いものである.
この二つの現実観は,現在二分された状態で
統一点がなく,和解策を生み出そうと思索した
著者の思想の物語です.
私は明かにロマン的ニンゲンなのですが,
古典的理解にとても魅力を感じます.
その最たるものは,私の中で
「修理すること」「作り出すこと」です.
身近なものとしてボニーちゃんがいるわけで,
古典的理解を求めてバヤシ・モーターサイクルさん(仮)で
お世話になったりしているわけです.
ちなみに,私が考えるロックとは,
古典的様式側からぐるりと回って
ロマン的に行きついたものです.
何の根拠もありませんが,
古典的思考を右側とするなら
ロマン的思考は左側で,
とっても遠くでつながっており,
全体を見れば円になっているように思います.
*どなたが書いたか不明ですが、一つの解釈として引用させていただきました。
主人公が毎朝出かける前に、ドライブチェーン調整やバルブクリアランス調整などを失われなかった記憶に基づき行いますが、何のために行うのか自問する場面もあったかと思います。
ところで、この書を紹介させて頂いたのはワケがあります。当ブログにコメントを頂きましたU.S.さんの貴重な情報を引用させていただきますと(勝手にごめんなさい)、
今は毎日環境の違う場所で環境の違う状態のバイクと格闘しています、40000マイル走ると流石のTC88も旧車の如く壊れてしまいますが、それがまた刺激的な毎日です。
30000マイルを越えるとことごとく配線ターミナルの継ぎ目のハーネスワイヤーが長期振動による”疲れ”により断線し始めます、点検に入ってくる車両には大抵トラブルコードが入っていて、OPENかSHORTしています。 ロックタイト(レッド)付きの200Nm以上で締められたのコンペンセーターナットが平気で緩んで入ってきて、スプラインの破損で普通にクランクを交換したり・・・。
古きも新しきも、限界を越えれば必ず壊れていくもので、昔、TC88は殆ど壊れないとお客様に言っていた自分を悔やみます。 ただ年間5000キロ程度ではよくよく整備されたパンヘッドでも壊れないんじゃないかと。
”古きも新しきも、限界を越えれば必ず壊れていくもので、”
「禅とモーターサイクル修理技術」の主人公が旅をした時代は1960年代と思われますが、丁度この頃から日本製のバイクは毎日整備をしなくても走れる信頼性を武器にして台頭してきました。1980年前後に一時ブームになったハーレーダビッドソンのオーナーの中でも、”裕福な旦那”たちには”近くはハーレー遠くはGL”という風潮さえありました。エボ以降は(’95年頃から特にかな?)急にレベルアップして故障も少なくなりましたが、日本に比べはるかに広い国土のアメリカ本国では、TCモデルでも苛酷な条件で使われると、日本で使う分には過剰品質とも思えるワイヤーハーネスもトラブルし、ストレートピンになり永久に使えそうなクランクも、つまらないことで壊れてしまうのですね。
パソコンもフロッピーデイスクを何枚も入れて立ち上げる時代から、あっという間にウインドウズになり、さすがにギガ容量のハードデイスクになってからは、そうはありませんが、今使っている一つ前のワタシのパソコンも画像をいじっているとスグにフリーズしたものです。
ココで何が言いたいかというと、壊れやすいものや性能が低いものは丁寧に扱いますが(承知さえしていれば文句も言わない?)、人間の欲望には限度がありませんから、性能が良くなったり壊れにくくなったと聞くと、苛酷に取り扱ったり、より以上のものを求めてしまうのではないかということです。
*再度引用すると、
ロマン的様式から見る古典的様式とは
機械のメンテナンスそのもので,
泥や油,基本構造に関する専門知識,
部品と構成部分とその相互関係,
全てが計算され,測定され,証明されなければならない.
退屈で,扱いにくく,醜く,果てしなく暗いものである.
この二つの現実観は,現在二分された状態で・・・・。
*ハーレーのオーナーはロマン的様式ですから、故障(オーナーから見て)に対して「こんなもんですよ」と言ってはいけません。
U.S.さんの情報の行間を読むと、故障しないハーレーダビッドソンを目標とするメーカーにとって振動は大敵であり、振動によっても故障しないワイヤーハーネスを開発するか、振動を減らすかの選択に迫られていると判断せざるを得ません。
「禅とオートバイ修理技術」は高価である上に難解ですので、特にお勧めはいたしませんが、読むことで自分のバイクや乗ることに対する思いが変るかもしれません。(もっと深い意味もありますがココでは書けませんね)
人気blogランキングへ 関東に本格的な夏到来はまだですが、クリックお願いします。