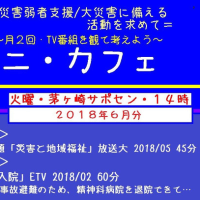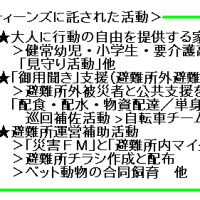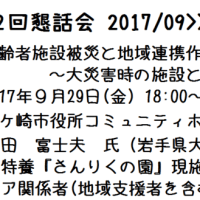玉井昭彦さんから、
ぜひ読んでいただきたいです。
そして乞う拡散。
*
電源の入らない携帯電話がつながる日はあるか~渋谷・ホームレス女性殺害
「いのちの分断」が進む社会で必要なのは想像する力、共感する力、そして連想する力
彼女のことを考えている。当然、会ったことはない。
居場所はなく、バス停で休んでいた。そして、いきなり殴り殺された。付近の住民は「小柄でおかっぱ頭」だったという。64歳。
どんな人だったのだろう。どこで生まれ、どんな人生を歩んできのだろう。なぜ、あの場所にいたのだろう。報道では今年の2月まで渋谷区のスーパーで働いていたという。なぜ、仕事と住まいを失ったのだろう。コロナの影響か。
何もわからない。しかし、私たちは想像することができる。できる限りの「想像力」をもって彼女のことを考える。それが残された者の「宿題」あるいは「義務」なのだ。
薄れていく意識の中で何を考えたのか
16日午前5時、東京都渋谷区のバス停のベンチに座っていたOさんが襲われた。路上生活者だったという。救急搬送されたが、死亡が確認された。防犯カメラの映像によると、犯人はベンチに座っていたOさんの頭を袋で殴り逃走。言葉を交わした様子もなく、いきなり殴りかかったとみられる。
21日警視庁は、現場近くの交番に母親に付き添われて出頭した46歳の男を逮捕した。「痛い思いをさせればあの場所からいなくなると思い殴ったが、まさか死んでしまうとは思わなかった」と供述しているという。
凶器となった袋には「ペットボトルなどが入っていた」「石を入れた」などと話しているという。付き添いの母親は「あんな大事(おおごと)になるとは思わなかった」と本人が言っていたと語っている。
Oさんは意識が薄れていく中で何を考えただろうか。そこにあったのは、無念、苦しみ、痛み、怒り、悲しみ……。あるいは、「これで楽になれる」と思っただろうか。
「もう二度と目が覚めませんように」と祈る毎日
そう思わざるを得ないほど路上生活は苦しい。僕には経験はない。だから、本当のことはわからない。だが、30年数年過酷を極める路上生活をする人を間近に見てきた。「3日やればやめられない」などと茶化す人もいる。いや、それはあなたが現実を知らないからです、あるいは人としての「想像力」を欠いているからです。
あるホームレスの親父さんは「毎晩祈ってから寝る」と語った。牧師である私は「もしかしてクリスチャンですか」と尋ねた。すると彼は「もう神も仏もありません」と静かに答えたのだ。
彼は何を祈っていたのか。「もう二度と目が覚めませんように」。彼は毎晩そう祈っていたという。言葉の重さにたじろいた。鈍感な私でさえ、この言葉に野宿生活とはどういうことなのかを考えざるを得なった。
排除の町で~「最も醜いベンチ」で事件は起きた
最初にニュースが飛び込んできた時、映像にうつるベンチが事件の背景を物語っているように思えた。二人掛けの小さなベンチの真ん中に仕切りの「手すり」。多くの人は、この「手すり」に違和感を覚えない。しかし、ホームレスの現場を長く見てきた私には、このベンチが事件を象徴しているように映った。
この手のベンチは、ここ二十年ほどの間に全国に広がった。「横になれないように仕切りを付けたベンチ」は、ホームレス対策として設置されたベンチだ。人を拒絶する「最も醜いベンチ」は今も増え続けている。
ベンチに仕切りだけではない。公園の東屋の屋根は外された。駅の待合室は改札の中へと移された。居場所がない人々を何とか引き受けてきた場所が消えつつある。格差が広がり、困窮者が増え、ホームレスが顕在化したころから町は疲れた人が横になる場所を奪い始めた。
事件はこの「最も醜いベンチ」で起こった。最も小さくされた人を排除するそのベンチが殺害現場となったのだ。
無言のまま人を「拒絶」する町々
「痛い思いをさせればあの場所からいなくなると思い殴った」。これが犯行の理由だった。ふざけるな、と言いたい。
しかし、この言葉はここ数十年、日本中の町々が多かれ少なかれ、口にはしなくても考え「醜いベンチ」という非言語的な具象によって表出させた思いと符号する。犯人の後ろに共犯する社会が存在する。あの「最も醜いベンチ」はそれを物語っている。
「最も醜いベンチ」は、無言のまま「拒絶」の姿勢を示していた。犯人もまた、言葉もなく突如Oさんに襲った。野良犬を棒切れで追い払うかのように彼女は襲われた。
言うまでもなくOさんは人間である。犯人が言葉を放棄したことは、Oさんを人間扱いしていない証しだと思う。同時に人間性の根幹である「言葉」や「対話」を放棄することで彼は、人であることを放棄したかのように私には見えた。
多くの人がOさんを知っていたのに……
近所の人の証言によると「いつもバス停のいすで寝ていた。朝2時くらいに来て6時前には帰る。新宿の方向へ」というのが、Oさんの日々だったようだ。一部の人は彼女の存在を認識していた。そして、彼女もまた町の人々を意識していた。
「朝2時から来て6時には帰る」。このような行動をとる野宿者は少なくない。深夜、町の人が寝静まった後にひっそり休息をとる。バスが来ない時間帯にバス停で休んでいたのは、人目を気にしているのみならず、なるべく迷惑にならないようにという思いがあったのだと思う。数時間、それが彼女の唯一休息だったのだと「想像」する。
かつて私が知り合ったホームレスの親父さんも、終電後の駅に戻りダンボールを敷き眠り、始発の前にその場所を去り町に消えていた。そんな日々を送る彼は、「見られのも嫌だし、みんなに迷惑もかけたくない」と言っていた。Oさんもまたそうだったのだと私は「想像」している。
事件を通報した女性は、「いつも見かける人が倒れている」と110番に告げたという。Oさんは「いつも見られていた」のだ。さらに「パーカを着たり、上着を着たりして寝てて、最近寒いので、凍死しちゃうんじゃないかなと心配していた」「ベンチに座ってね、もう1カ月くらい前から気になっていた。キャリーケースを杖みたいにして寝てるんです」との声も報じられている。Oさんは認識されていたし、心配もされていた。
しかし、それらの思いは、個々人の中に留まり、肝心のOさんには伝わらず、「心配」が公的機関や支援団体にもつながることもなかった。あと一歩のところでブレーキがかかったのだ。
格差が「いのち」にまで広がっている
もし、小学生の女の子がバス停で夜を過ごしていたならばどうだろう。「大騒ぎ」になっていただろう。心配されながら1カ月も放置されることは、まずない。しかし、相手が大人であり、かつ「ホームレス」の場合、強烈なブレーキがかかる。これを差別と言う。
昨年9月。台風19号が首都圏を直撃した。テレビでは「いのちを守る最大限の努力を」との呼びかけが繰り返された。そんななか、ホームレス状態だった人が台東区の避難所を訪れた。しかし「ここは区民のための避難所だ」と入室を断られ、嵐の中へ押し返された。後日、区民以外の外国人や旅行者を避難所が受け入れていたことが判明し、区長が当事者に謝罪する事態となった。
経済格差が問題となっているが、格差は「いのち」にまで広がっている。「大事にされるいのち」と「ぞんざいに扱われるいのち」。そんな「いのちの分断」が社会には存在している。
この分断は、さらに深まっている。2016年7月の相模原事件は、「いのちの格差」を明示した事件だった。私たちは、この分断をどうすれば乗り越えることができるだろうか。
所持品は「衣類と食品のゴミ」報道は間違い
Oさんの所持金は8円だったという。想像したい。8円しかないという現実を。たまたま通帳から下ろし忘れたというというのではない。全財産が8円なのだ。私ならどうだろうか。
「衣類と食品のゴミ」を持っていたと報道は伝えた。しかし、この報道は間違っている。記者の目には、あるいは担当した警察官には「食品のゴミ」としか映らなかった。しかし、それは間違いなく彼女の「食べ物」だった。「ゴミ」ではない。
誰が「ゴミ」を大事に持ち歩くか。彼女のいのちをつなぎとめるための「食べ物」だったのだ。「ゴミを食べざるを得ない人の気持ち」を想像したい。自分ならどうだろうか。
多くの野宿者が自分の食べ物を「エサ」と呼ぶ。関東でも、関西でも、そして九州の野宿者も。私が「人が食べているのだから『食べ物』と言ったらどうです」と言うと、「残飯を漁っているから犬や猫と一緒。だからエサだ」と彼らは言う。
「エサ」ならまだ「食べ物」の範疇に留まるが、「ゴミ」はもはや「食べ物」ではない。突如襲撃されたホームレスの女性の悲劇を伝える記事であるにも関わらず、残念ながら「想像力」に欠けている。
記者は「伝えなければならない」との正義感をもって記事を書いたと思う。当日トップニュースにもなった。しかし、そこに想像と共感はどれだけあったのか。
想像力という「教養」を失った社会
養老孟司は、著書の中で「教養はものを識ることとは関係がない。やっぱり人の心がわかる心というしかないのである」と言う。
無言のまま彼女を殴り殺す人。彼女のことを心配しつつも対話なき地域の人々。なけなしの食べ物を「食品のゴミ」と認識するジャーナリズムに欠落しているのは「教養」だ。すなわち「人の心」を理解しようとする営みである。
想像する力、共感する力、そして連想する力が私たちには必要なのだ。どれだけ豊かになったとしても、どれだけ便利になったとしても、それらが不十分なら、私たちは「ただの無教養な民」となる。
犯人の46歳の男性は、母親に付き添われて出頭したという。この家族がどのような状況にあったかも想像せねばなるまい。
母子家庭。彼の父は生前、「息子がひきこもっている」と心配していたともいう。いかなる事情であれ今回の事件を割り引いて考えることはできない。それでもなお、私達は、「自宅のバルコニーから見える世界が自分のすべて」と近所に語っていたこの男性のことも想像するしかない。
いかなる理由であれ他者に対する「想像」を怠れば、私達は他者を排除する「無教養な民」となってしまう。
「あんな大事(おおごと)になるとは思わなかった」と本人は言った。「大事(おおごと)」とは何を指すのか。「まさか死ぬとは思わなかったが死んでしまった。自分が殺人者になるとは思わなかった」ということか。
そうならば、どこまでも「他者」不在の「無教養な男」と言わざるを得ない。自分のことしか考えない。それが「無教養」の証しだ。
殺されたから「大事(おおごと)」なのではない。64歳の女性が野宿せざる得ない現実が「大事(おおごと)」なのだ。「大事(おおごと)」、つまり「大変な事態」なのだ。社会は、その「大事(おおごと)」に気付くことなく、まるで「小事」のごとく受け流す。人の心を考えず、その人の苦しみも想像せず、一方的に排除する。
そういう「無教養な社会」になっていることが最も「大事(おおごと)―大変な事態」なのだ。
なぜ電源の入らない携帯電話を持っていたのか
彼女には、もう一つ所持品があった。「電源の入らない携帯電話」だ。どんな思いで携帯電話を握りしめていたのだろう。
かつてその携帯電話先にはどんな人々がいたのだろう。その人々は、彼女が亡くなったことを知っているだろうか。さらに、親戚の連絡先のメモも見つかった。
Oさんは、誰かとつながっていたかったのだ。起動することもない携帯電話を持ち続けたOさんは、いつの日か、その電話に再び誰かがかけてくることを待っていたのだと思う。いつの日か、懐かしい人々に電話をする日を待っていたのだと思う。
しかし、その夢はもう叶わない。
「野蛮人の国」にならないために
だから、最大の「教養」をもってOさんのことを想像したい。「電源の入らない携帯電話」を持ち続けた路上生活者Oさんのことを考え続けたい。彼女の思いを想像したい。それがあるべき「教養」なのだ。
それができたなら、次に私たちは連想するのだ。この社会で「電源の入らない携帯電話」を握りしめている人が他にもいるであろうことを。今、この時に、すでに鳴らなくなった携帯電話を「この世界とのつながりの証拠」であるかのように握りしめる人々を連想するのだ。そのイメージが沸いたなら、その携帯電話が再びつながるためには何をすべきかを考えるのだ。
すべては想像から始まる。私たちは「教養ある民」でありたい。そうでなければこの国は「野蛮人の国」で終わる。
二度とこのような事件を
朝日新聞 論座 2020年11月23日