昭和40年に洋画家である林武画伯(1896-1975)が自身の半生を綴った新書である。林武氏の画風は、いわゆる厚塗り派で、原色に近い赤や黄を多用して、バラや富士や婦人を描いている。ルオーは物体の外側に藍色の縁書きをほどこすのだが、全体に宗教的に暗いが、反対に林画伯は明るい色彩で描き、物体の実在感が非常に強く感じられる。

一冊の前半は苦労して画家となるまでが書かれ、後半は画家として自分の画風が確立していく過程が書かれるのだが、この前半の部分は、林武自身のことだけではなく、父親のことが多く書かれている。国学者であって偏った国粋主義者だった父親を書くことで、明治後半から昭和前半の日本の黒歴史を垣間見ることができる。後半より、数奇な林一家の家族史が書かれる前半の方がおもしろい。
本書に書かれていないが、その実力からいえば、個人美術館が建ってもおかしくないほどの存在なのだが、存在しない。それ以上に、全国の美術館にも、彼の絵画はきわめて少ないらしい(愛知県のいくつかの美術館に偏在している)。画家は絵を描いて売って生活するのが通常だが、良い絵を売らないで手元に置いておこうという誘惑があるそうだ。さらに多作家で高額ともなると売り切れない場合もある。個人美術館(例えば東山魁夷の専門美術館は何か所かにあるが、画家の没後に親族が保管の問題や相続税の問題に困って、地元と協議して寄贈したり、貸与したりして専用美術館にすることが多い。林武は本書に書かれるように、貧乏だったので、ほとんど手元に残さなかったのではないだろうか。また新宿が故郷なので、地価から言って美術館では不経済ということかもしれない。
で、本書に沿って書くと、彼の父親は狂熱的な国家主義者で国文学者だった。國學院大學の創立にもかかわっていた。その祖父は水戸藩の国学者で名前も林国雄と勇ましい。その息子も幕末の千葉道場で剣を磨いた。そして父は明治維新に取り残され、英国研修を拒否したため、地方の神官の職を与えられ、後に国語教師となる。
しかし、社会の洋風化に抵抗を続け、家族の中で親子喧嘩が絶えない状況になり、家族はバラバラになっていくわけだ。
その中で五人兄弟の5番目の武は、とりあえず小学校に行っていたが、絵の上手な児童が二人いた。一人は林武でもう一人は後の東郷青児だった。小学教師が、「将来、絵を描く職業を目指しなさい」と言ったことが、少なからず彼の人生に影響を与えたことになる。
その後、一家困窮で家族バラバラの中、武少年は新しい家業の牛乳売りを手伝うが体力が持たない。文士になろうと早稲田実業に入るが中退(早稲田には退学一流、留年二流、卒業三流という伝統がある)。ついにペンキ絵の出張販売という怪しい仕事を始める。怪しい画家がペンキのように描いた絵を北海道各地で売りさばいていた。自らは偽画家として即売会場でそれらしい扮装でキャンバスに向かっていたわけだ。
そして、偽画家でも絵筆を動かさないといけないわけで、そうなると、小学生の頃からの腕前を発揮してしまうわけだ。偽画家がペンキ絵を描いたら本格的な絵画になったということだ。
そして、ついにフランスに渡って修行しようということになるのだが、フランスには既に何もない状態だった。「すべての色彩は光の中にある」という思想から嵐のように吹き荒れた印象派は去り、既に何もない時代だった。野獣派とかフォービズムなど数多くの手法が現れる。どの流儀で行くか。当時の人気はセザンヌだったようだ。どちらかというと構図至上主義。空間の美学ともいうべきか。彼もかなりセザンヌを研究し、構図にこだわっている。さらにルドンの迫力というか、バラや富士山を描くとき、どうしても背景に空間が必要なのだが、きわめて余白を小さく描くのが林流だろうか。

一冊の前半は苦労して画家となるまでが書かれ、後半は画家として自分の画風が確立していく過程が書かれるのだが、この前半の部分は、林武自身のことだけではなく、父親のことが多く書かれている。国学者であって偏った国粋主義者だった父親を書くことで、明治後半から昭和前半の日本の黒歴史を垣間見ることができる。後半より、数奇な林一家の家族史が書かれる前半の方がおもしろい。
本書に書かれていないが、その実力からいえば、個人美術館が建ってもおかしくないほどの存在なのだが、存在しない。それ以上に、全国の美術館にも、彼の絵画はきわめて少ないらしい(愛知県のいくつかの美術館に偏在している)。画家は絵を描いて売って生活するのが通常だが、良い絵を売らないで手元に置いておこうという誘惑があるそうだ。さらに多作家で高額ともなると売り切れない場合もある。個人美術館(例えば東山魁夷の専門美術館は何か所かにあるが、画家の没後に親族が保管の問題や相続税の問題に困って、地元と協議して寄贈したり、貸与したりして専用美術館にすることが多い。林武は本書に書かれるように、貧乏だったので、ほとんど手元に残さなかったのではないだろうか。また新宿が故郷なので、地価から言って美術館では不経済ということかもしれない。
で、本書に沿って書くと、彼の父親は狂熱的な国家主義者で国文学者だった。國學院大學の創立にもかかわっていた。その祖父は水戸藩の国学者で名前も林国雄と勇ましい。その息子も幕末の千葉道場で剣を磨いた。そして父は明治維新に取り残され、英国研修を拒否したため、地方の神官の職を与えられ、後に国語教師となる。
しかし、社会の洋風化に抵抗を続け、家族の中で親子喧嘩が絶えない状況になり、家族はバラバラになっていくわけだ。
その中で五人兄弟の5番目の武は、とりあえず小学校に行っていたが、絵の上手な児童が二人いた。一人は林武でもう一人は後の東郷青児だった。小学教師が、「将来、絵を描く職業を目指しなさい」と言ったことが、少なからず彼の人生に影響を与えたことになる。
その後、一家困窮で家族バラバラの中、武少年は新しい家業の牛乳売りを手伝うが体力が持たない。文士になろうと早稲田実業に入るが中退(早稲田には退学一流、留年二流、卒業三流という伝統がある)。ついにペンキ絵の出張販売という怪しい仕事を始める。怪しい画家がペンキのように描いた絵を北海道各地で売りさばいていた。自らは偽画家として即売会場でそれらしい扮装でキャンバスに向かっていたわけだ。
そして、偽画家でも絵筆を動かさないといけないわけで、そうなると、小学生の頃からの腕前を発揮してしまうわけだ。偽画家がペンキ絵を描いたら本格的な絵画になったということだ。
そして、ついにフランスに渡って修行しようということになるのだが、フランスには既に何もない状態だった。「すべての色彩は光の中にある」という思想から嵐のように吹き荒れた印象派は去り、既に何もない時代だった。野獣派とかフォービズムなど数多くの手法が現れる。どの流儀で行くか。当時の人気はセザンヌだったようだ。どちらかというと構図至上主義。空間の美学ともいうべきか。彼もかなりセザンヌを研究し、構図にこだわっている。さらにルドンの迫力というか、バラや富士山を描くとき、どうしても背景に空間が必要なのだが、きわめて余白を小さく描くのが林流だろうか。


















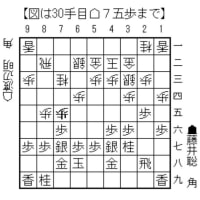

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます