三島由紀夫の主要作品は高校生の時に読んだが、いくつか読んでいないものもあり没後50年を機に補完している。著者の作品は読者を強く突き放す作が多いのだが、なんとなくだが、主張性の弱い作品もある。分類的には「沈める滝」「絹と明察」、名作「午後の曳航」などがそうなのだろう。

「絹と明察」はある意味で企業小説のようだが、著者の小説によく登場する「未亡人」とか病弱だが病院のベッドの上から画策する人物(社長夫人)とか、政商(大物、中物、小物たち)が登場。
労働争議とか、労働災害、ブラック職場など戦後復興期の日本の闇が描かれる。
しかし、あえて言うなら社会派作家の描く「信念」とか、企業内幕小説家の描く「深い闇」というような読者への押し付けとか共感というものは感じられない。
作家三島がゼウスの神のように、人間界で起こっている醜い低レベルの争いを淡々と鑑賞して紙の上に記録するという書き方である。
そういう意味で、仮に著者が、その後に妙な思想を入手して自爆せず、ゼウススタイルで、人間の普遍的な愚かさを淡々と書き連ねていったらどうなっただろうと推測してみるのだが、おそらくそういう書物が市井の庶民にも、様々な色に染まった評論家群に評価されることはなく、逆にノーベル賞に到達したかもしれない。

ところで、本小説の中に何度となく登場する場所が、彦根城。現存12天守閣の一つで、国宝である。十数年前に登城した時の画像から二枚を参考に。

小説では現在のしゃちほこの一代前のしゃちほこが天守閣内に飾られているようになっているのだが、ネット上で所在を捜索したところ、現在は別の場所に展示されているようだ。どうして冷遇されているのか、何かわけがあるのかもしれない。

「絹と明察」はある意味で企業小説のようだが、著者の小説によく登場する「未亡人」とか病弱だが病院のベッドの上から画策する人物(社長夫人)とか、政商(大物、中物、小物たち)が登場。
労働争議とか、労働災害、ブラック職場など戦後復興期の日本の闇が描かれる。
しかし、あえて言うなら社会派作家の描く「信念」とか、企業内幕小説家の描く「深い闇」というような読者への押し付けとか共感というものは感じられない。
作家三島がゼウスの神のように、人間界で起こっている醜い低レベルの争いを淡々と鑑賞して紙の上に記録するという書き方である。
そういう意味で、仮に著者が、その後に妙な思想を入手して自爆せず、ゼウススタイルで、人間の普遍的な愚かさを淡々と書き連ねていったらどうなっただろうと推測してみるのだが、おそらくそういう書物が市井の庶民にも、様々な色に染まった評論家群に評価されることはなく、逆にノーベル賞に到達したかもしれない。

ところで、本小説の中に何度となく登場する場所が、彦根城。現存12天守閣の一つで、国宝である。十数年前に登城した時の画像から二枚を参考に。

小説では現在のしゃちほこの一代前のしゃちほこが天守閣内に飾られているようになっているのだが、ネット上で所在を捜索したところ、現在は別の場所に展示されているようだ。どうして冷遇されているのか、何かわけがあるのかもしれない。











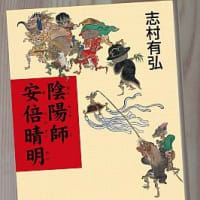








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます