ニュース「奈良の声」 2323年8月23日 浅野善一
■関東大震災100年、朝鮮人ら虐殺事件を考える 8月26日、奈良天理で討論会
【写真】討論会「関東大震災から100年~現代の課題を考える」の案内ちらし
討論会「関東大震災から100年~現代の課題を考える」(同実行委員会主催)が8月26日午後2時から、奈良県天理市川原城町の市民会館で開かれる。震災の混乱の中、流言飛語によって多くの朝鮮人や中国人が虐殺された事件について、なぜ起きたのかを検証し、現代に投げ掛ける問題を考える。震災直後、当時の奈良県知事が県報で流言に言及するなど、県も無縁ではないという。
1923年9月1日に起こった関東大震災は首都圏に死者10万人の被害をもたらした。同実行委事務局は虐殺事件について「内務省警保局が『朝鮮人が爆弾を所持、石油で放火するものあり』と公文書で流すなどして流言飛語が広まり、官憲や自警団に加わった民衆が恐怖に駆られ、朝鮮人6000人、中国人800人、社会主義者、労働運動の活動家、朝鮮人に間違われた日本人を殺害した。最近の研究で琉球人の犠牲者の名前も分かってきた」とする。
国の中央防災会議が2009年3月にまとめた「災害教訓の継承に関する専門調査会報告書」の「1923 関東大震災【第2編】」も、「朝鮮人が武装蜂起し、あるいは放火するといった流言を背景に、住民の自警団や軍隊、警察の一部による殺傷事件が生じた」と指摘。「朝鮮人が最も多かったが、中国人、内地人も少なからず被害にあった。犠牲者の正確な数は掴(つか)めないが、震災による死者数の1~数パーセントにあたり」などと述べている。
同実行委事務局によると、奈良県では震災直後の9月18日、当時の成毛基雄知事が奈良県報号外で「今度の震災に当り多くの朝鮮人は能(よ)く同情し又救済等に努力しつゝあるが、極めて少数の鮮人は災難に乗じて悪い事を働いたそうである」などと流言を疑うことなく述べたという。同事務局は、奈良県も事件と無縁ではないとする。
当日は4人のパネリストによる発表と討論が行われる。パネリストとそれぞれの発表内容は、松田暢裕さん(小説「智異山」翻訳者)「千葉県の虐殺事件、八千代市観音寺のこと」▽崎浜盛喜さん(「琉球人遺骨返還を求める奈良県会議」共同代表)「琉球人虐殺について」▽姜信子(カン・シンジャ)さん(作家)「鎮魂と予祝~百年芸能祭に取り組んで」▽浅川肇さん(ハッキョ支援ネットワーク・なら)「関東大震災の時代状況と現代の課題を考える」。
このほか、関東大震災100年をテーマにしたテレビニュース番組の放映や、虐殺事件を扱った詩人壷井繁治の詩「十五円五十銭」を基にした渡部八太夫さんの祭文語りがある。
同実行委事務局は「関東大震災の朝鮮人虐殺の背景には、官憲に植民地支配からの独立運動に立ち上がった朝鮮民族に対する恐怖があったと言われる。100年後の今、ロシアのウクライナ侵略から岸田政権は安保関連3文書を閣議決定し、敵地基地攻撃能力を有した長距離ミサイル配備で、沖縄―南西諸島の前線基地化を図るっている。こうした他民族、国家に向けた敵愾(てきがい)心が増す今、なぜ惨劇が起きたのか、歴史を検証し、現代に投げ掛けられた課題を明らかにするため、参加者と共に議論したい」と話している。
参加者には資料代として500円のカンパの協力を求める。当日、市民会館の駐車場は利用できない。事務局は天理駅前の駐車場を利用してほしいとしている。
問い合わせは事務局の川瀬さん、電話090-8234-0077、電子メールkawase2018@yahoo.co.jp
ニュース「奈良の声」 2023年8月8日 浅野善一
奈良県天理市長、柳本飛行場跡フィールドワークに参加 「強制連行」記述巡る説明板撤去で 再設置求める団体が案内
【写真】柳本飛行場跡のフィールドワークに参加した並河健天理市長(右から2人目)。左は案内役を務めた高野真幸さん=2023年8月8日、同市内
奈良県天理市の並河健市長は8月8日、太平洋戦争末期に建設された市内の大和海軍航空隊大和基地(通称・柳本飛行場)の跡地を歩くフィールドワークに参加した。市民団体「天理・柳本飛行場跡の説明板撤去について考える会」が案内した。
飛行場跡の一角には、過去の市長の時代に市などが設置した飛行場の説明板があったが、並河市長は2014年、建設工事に関し朝鮮人の強制連行などの記述があることを問題視して撤去。「考える会」は説明板の再設置を求めて市と交渉を続けている。市長の姿勢は変わっていないが、「考える会」は「一歩前進」と受け止めた。
同飛行場は本土決戦に備えて建設されたといわれる。同市長柄町や岸田町の付近に、長さ1500メートルの滑走路や関連施設があった。現在は元の水田などに戻っている。
フィールドワークには、並河市長や市教育長、市教育委員会文化財課の職員、「考える会」の関係者ら約20人が参加した。水田地帯に点在する滑走路のコンクリート舗装の一部や通信に使われたコンクリート製の防空壕(ごう)、海軍施設部跡の建物などを、「考える会」共同代表の一人、高野真幸さんの案内で約2時間かけて巡った。高野さんは強制連行や慰安所についても言及した。並河市長は時折、質問もしながら説明に耳を傾けていた。
並河市長はフィールドワーク終了後のあいさつで「飛行場の全体像を教わり、平和を次の世代に受け継いでいかないといけないという思いを新たにした。朝鮮半島から来られた皆さんにも本来、故郷で平穏な日常がなければならなかった。われわれ日本人は真摯(しんし)に受け止め反省し、決して繰り返されてはならない」と述べた。
その上で強制連行などの歴史認識については「いろいろな研究家もおられ、(考える会)の皆さんの成果も勉強させていただきたい。今日のフィールドワークはその一環としてあったと思う」とした。史跡としての保存についても触れ、「壕なども劣化しており、どうしたら残していけるのか予算面も含め検討していかなければならない」と述べた。
高野さんは取材に対し、「一歩前進と思う。市長には1回だけでなくフィールドワークを続けてほしい。付随する施設はたくさんある」と述べた。
同飛行場を巡っては、その歴史の解明に取り組むグループが、強制連行された朝鮮人労働者が建設工事に動員されたことや、朝鮮人女性の慰安所があったことを、独自に掘り起こした。説明板は1995年、そうした調査を踏まえて設置された。しかし、2014年、「強制連行」や「慰安所」の記述に対し、外部から批判的な指摘があり、市はこれを機に「強制性については議論があり、説明板を設置しておくと、市の公式見解と誤解される」と判断、撤去した。











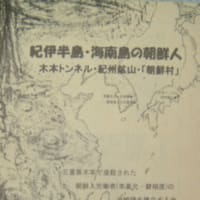





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます