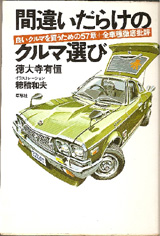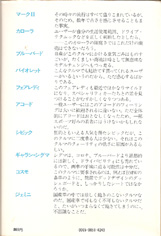4月27日の朝日新聞beの1面「日曜ナントカ学」は、「ケガをしないパソコン追求」と題して、長時間パソコンを使い続ける人が、肩こりや頭痛などを起こさないようなパソコンを追求しています。
「それなら親指シフトキーボードだろう」と突っ込みを入れようと2面を開いたら、何とそこには親指シフトキーボードの話題が掲載されていました。ありがたいことです。
「仮名で入力できるキーボードなど、ストレスを軽くするための工夫も行われてきた。たとえば、富士通による『親指シフト方式』。」
「『各文字の出現頻度はもちろん、文字の連なり方の特徴などまで、徹底的に日本語を解析、どの文字配置が指の動きを最小限にできるかを考えた』と開発者の神田泰典・富士通顧問は振り返る。」
それは、親指シフトを使う私にはよく理解できます。ごく普通の日本語文を入力するときは、きわめて快適に指が動きます。それに対し、カタカナ語の入力となると、とたんに指の動きがぎくしゃくするのです。カタカナ語は文字の連なりが普通の日本語と異なるので、親指シフトの特質が生かされないのですね。
「愛用者は今もいる。文筆業者、司法関係者など、長い文章を書くことの多い『プロ』が多いのが特徴だ。翻訳業の竹内裕さん(名古屋市)もそんな一人。
『書くのは、日本語と英語が半々。どちらで書いているのかわからなくなって、しばしぱカタカナ語を英語のスペルのまま打ったりする。両者を別のシステムにしておいた方が効率的。一種のバイリンガルです。』」
“英文入力が多いからこそ、日本語をローマ字入力で打つことに抵抗がある”として親指シフトを使っている人は確かにいます。日常に英文入力を行っている人にとって、"computer"を"konnpyu-ta-"などと打つのは大きな抵抗でしょう。
「『打つ文字と表示される文字が違うローマ字入力は、日本語を書く方法としては自然ではない。定着したのは、ある意味不思議』と、人とコンピューターの問題に詳しい奥野卓司・関西学院大教授(社会学)ははなす。」
次に記事は、携帯電話のテンキー入力について述べます。
「達人と呼ばれる人は、100字の漢字かなまじり文を1分で打ち込むことができるという。」
「10個だけのキーは、何よりも覚えやすい利点がある。テンキーだけのパソコンの時代の到来も予感させる。」
これはまたおかしな方向に話が展開したものです。
「覚えやすい」を第一に考えるなら、五十音順のキー配列が候補に挙がるはずです。たしかにワープロ専用機の初期にはこのようなキー配列がありました。私が最初に買ったオアシスライトFも、設定で五十音順配列に変更することが可能でした。
しかし五十音順配列は普及しなかったわけで、ちょっとでも習熟したあとはおそらく使いづらい配列なのでしょう。
携帯入力方式は、打鍵数が恐ろしく多いのではないでしょうか。たとえ親指1本入力ではないにしても、打鍵数の多さで腱鞘炎になるはずです。なお、高速入力を実現している達人は、おそらく仮名漢字変換機能の助けを借りて少ない文字入力で文章を書いているのでしょう。それであれば、普通のキーボードでもその機能を使おうと思えば使えるのですから、キーボード比較を行う上ではどちらかの条件に合わせるべきでしょう。
「達人で100文字を1分」と驚いていますが、文字入力シロウトの私でさえ、20年ほど前には漢字仮名まじり文を10分間で900文字入力するスピードでした。親指シフトです。
親指シフトには、シロウトでもこのレベルに比較的簡単に到達できるというメリットがあります。
そして今回の記事「日曜ナントカ学」の最初のテーマである「ケガをしない」という観点でも、親指シフトに軍配が上がるはずです。打鍵数の少なさから、腱鞘炎になりにくい打鍵方式であると思っています。
すでに世の中はゴールデンウィークに突入しています。私も明日から旅行に出かけます。旅行先からアクセスできるかどうかはわからないので、次の発言は旅行から帰る5月7日以降になると思います。
それでは皆さん、よい連休を!
「それなら親指シフトキーボードだろう」と突っ込みを入れようと2面を開いたら、何とそこには親指シフトキーボードの話題が掲載されていました。ありがたいことです。
「仮名で入力できるキーボードなど、ストレスを軽くするための工夫も行われてきた。たとえば、富士通による『親指シフト方式』。」
「『各文字の出現頻度はもちろん、文字の連なり方の特徴などまで、徹底的に日本語を解析、どの文字配置が指の動きを最小限にできるかを考えた』と開発者の神田泰典・富士通顧問は振り返る。」
それは、親指シフトを使う私にはよく理解できます。ごく普通の日本語文を入力するときは、きわめて快適に指が動きます。それに対し、カタカナ語の入力となると、とたんに指の動きがぎくしゃくするのです。カタカナ語は文字の連なりが普通の日本語と異なるので、親指シフトの特質が生かされないのですね。
「愛用者は今もいる。文筆業者、司法関係者など、長い文章を書くことの多い『プロ』が多いのが特徴だ。翻訳業の竹内裕さん(名古屋市)もそんな一人。
『書くのは、日本語と英語が半々。どちらで書いているのかわからなくなって、しばしぱカタカナ語を英語のスペルのまま打ったりする。両者を別のシステムにしておいた方が効率的。一種のバイリンガルです。』」
“英文入力が多いからこそ、日本語をローマ字入力で打つことに抵抗がある”として親指シフトを使っている人は確かにいます。日常に英文入力を行っている人にとって、"computer"を"konnpyu-ta-"などと打つのは大きな抵抗でしょう。
「『打つ文字と表示される文字が違うローマ字入力は、日本語を書く方法としては自然ではない。定着したのは、ある意味不思議』と、人とコンピューターの問題に詳しい奥野卓司・関西学院大教授(社会学)ははなす。」
次に記事は、携帯電話のテンキー入力について述べます。
「達人と呼ばれる人は、100字の漢字かなまじり文を1分で打ち込むことができるという。」
「10個だけのキーは、何よりも覚えやすい利点がある。テンキーだけのパソコンの時代の到来も予感させる。」
これはまたおかしな方向に話が展開したものです。
「覚えやすい」を第一に考えるなら、五十音順のキー配列が候補に挙がるはずです。たしかにワープロ専用機の初期にはこのようなキー配列がありました。私が最初に買ったオアシスライトFも、設定で五十音順配列に変更することが可能でした。
しかし五十音順配列は普及しなかったわけで、ちょっとでも習熟したあとはおそらく使いづらい配列なのでしょう。
携帯入力方式は、打鍵数が恐ろしく多いのではないでしょうか。たとえ親指1本入力ではないにしても、打鍵数の多さで腱鞘炎になるはずです。なお、高速入力を実現している達人は、おそらく仮名漢字変換機能の助けを借りて少ない文字入力で文章を書いているのでしょう。それであれば、普通のキーボードでもその機能を使おうと思えば使えるのですから、キーボード比較を行う上ではどちらかの条件に合わせるべきでしょう。
「達人で100文字を1分」と驚いていますが、文字入力シロウトの私でさえ、20年ほど前には漢字仮名まじり文を10分間で900文字入力するスピードでした。親指シフトです。
親指シフトには、シロウトでもこのレベルに比較的簡単に到達できるというメリットがあります。
そして今回の記事「日曜ナントカ学」の最初のテーマである「ケガをしない」という観点でも、親指シフトに軍配が上がるはずです。打鍵数の少なさから、腱鞘炎になりにくい打鍵方式であると思っています。
すでに世の中はゴールデンウィークに突入しています。私も明日から旅行に出かけます。旅行先からアクセスできるかどうかはわからないので、次の発言は旅行から帰る5月7日以降になると思います。
それでは皆さん、よい連休を!