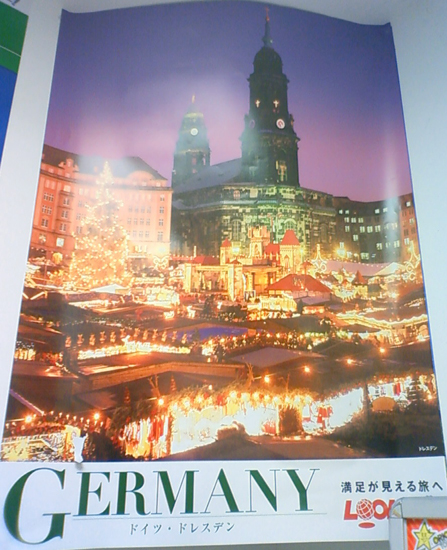だいぶ前になりますが、日経新聞「私の履歴書」12月23日は、1996年当時にペリー(当時)米国防長官が沖縄の普天間問題にどのように取り組んだかが示されています。
橋本龍太郎首相が、日本外務省の反対にもかかわらず普天間返還を米側に言い出したがっている、という情報はペリー国防長官に事前に届いていました。
ペリー長官は当初から、沖縄県内で沸騰する反米軍基地の空気を鎮静化するためには「返還」という劇的な決断が必要だと感じており、クリントン大統領には「適切な状況さえ設定できれば、この(普天間返還)問題を無視するのではなく、推し進めるべきだ」と進言していました。ただし、普天間返還をクリントンに勧めるに際して、ペリー長官は最後まで代替地は沖縄県内であるべきだと思っていました。
『その理由は何といっても沖縄が備えている地理的な特性である。仮に朝鮮半島で有事が発生した場合、北朝鮮から最も近接した場所の一つは沖縄だ。だから、この問題について、私が日本政府と協議する際も「撤退」といった憶えは一度もない。あくまでも沖縄県内の他の場所に「移設」することを条件として、「返還」を決めたのだ。クリントンにもその点は念を押していた。』
沖縄米軍・普天間基地を5~7年以内に日本に全面返還することで正式に合意し、1996年4月12日夜、橋本首相はウォルター・モンデール駐日米大使と首相官邸で共同記者会見しました。
『だが、その後、普天間を巡る緊張が緩み、何年も注意を振り向けなかった結果、普天間問題はまたしても漂流を始めてしまった。その漂流が長引けば長引くほど、この問題は難しさと同時に危険度も増していく。やがてこの問題が極度に深刻化すれば、それはすべての物を失うことにつながっていく。非常に残念なことだが、その懸念は今、現実のものとなっている。』(12月23日記事)
普天間返還の方針を発表した直後、1996年4月17日、国賓として来日したクリントン米大統領は橋本首相と会談し、冷戦終結後の日米安保体制の重要性を再確認した「日米安保共同宣言」に署名しました。
この会談で、両首脳は極東有事の際の日米防衛協力を本格的に検討することでも合意し、橋本首相は「危機が生じた時に日米安保体制が円滑に機能し、効果的に運用するため、日米協力できることとできないことの研究をきちんとしなければならない」と述べ、日米防衛協力の指針の見直しを軸に共同対処研究に取り組んでいく意向を表明しました。(12月24日記事)
橋本首相のこの方針がその後もぶれずに貫かれていたら、今ごろはずいぶんと違った風景になっていたことでしょう。なぜそうならなかったのか・・・。
日本史年表で簡単に調べてみました。
1998年7月に自民党(橋本政権)は参院選挙で惨敗し、小渕恵三内閣が成立しています。
2000年4月に小渕首相が病気入院し、森喜朗内閣が成立します。
2001年4月、自民党総裁選で小泉純一郎氏と橋本龍太郎氏が戦って小泉氏が勝利し、小泉内閣が成立します。
橋本内閣は国民に人気がなかったのですね。
その後、現在まで続く日本の政治を振り返ると、“ポピュリズム”“大衆迎合”でない政治はほとんど不可能となっているようです。
日本が国際社会の中で名誉ある地位を占めることのできる国に成長しようとしても、国民がそのような方向の政府を選択しないということで、現在の日本が国際社会で漂流しているのも日本国民が結果として選んだ道でしかない、といえるようです。
なお、96年以降の普天間返還問題の推移については、小川和久著「普天間問題」を参照してください。
それでは皆さん、良いお年をお迎えください。
橋本龍太郎首相が、日本外務省の反対にもかかわらず普天間返還を米側に言い出したがっている、という情報はペリー国防長官に事前に届いていました。
ペリー長官は当初から、沖縄県内で沸騰する反米軍基地の空気を鎮静化するためには「返還」という劇的な決断が必要だと感じており、クリントン大統領には「適切な状況さえ設定できれば、この(普天間返還)問題を無視するのではなく、推し進めるべきだ」と進言していました。ただし、普天間返還をクリントンに勧めるに際して、ペリー長官は最後まで代替地は沖縄県内であるべきだと思っていました。
『その理由は何といっても沖縄が備えている地理的な特性である。仮に朝鮮半島で有事が発生した場合、北朝鮮から最も近接した場所の一つは沖縄だ。だから、この問題について、私が日本政府と協議する際も「撤退」といった憶えは一度もない。あくまでも沖縄県内の他の場所に「移設」することを条件として、「返還」を決めたのだ。クリントンにもその点は念を押していた。』
沖縄米軍・普天間基地を5~7年以内に日本に全面返還することで正式に合意し、1996年4月12日夜、橋本首相はウォルター・モンデール駐日米大使と首相官邸で共同記者会見しました。
『だが、その後、普天間を巡る緊張が緩み、何年も注意を振り向けなかった結果、普天間問題はまたしても漂流を始めてしまった。その漂流が長引けば長引くほど、この問題は難しさと同時に危険度も増していく。やがてこの問題が極度に深刻化すれば、それはすべての物を失うことにつながっていく。非常に残念なことだが、その懸念は今、現実のものとなっている。』(12月23日記事)
普天間返還の方針を発表した直後、1996年4月17日、国賓として来日したクリントン米大統領は橋本首相と会談し、冷戦終結後の日米安保体制の重要性を再確認した「日米安保共同宣言」に署名しました。
この会談で、両首脳は極東有事の際の日米防衛協力を本格的に検討することでも合意し、橋本首相は「危機が生じた時に日米安保体制が円滑に機能し、効果的に運用するため、日米協力できることとできないことの研究をきちんとしなければならない」と述べ、日米防衛協力の指針の見直しを軸に共同対処研究に取り組んでいく意向を表明しました。(12月24日記事)
橋本首相のこの方針がその後もぶれずに貫かれていたら、今ごろはずいぶんと違った風景になっていたことでしょう。なぜそうならなかったのか・・・。
日本史年表で簡単に調べてみました。
1998年7月に自民党(橋本政権)は参院選挙で惨敗し、小渕恵三内閣が成立しています。
2000年4月に小渕首相が病気入院し、森喜朗内閣が成立します。
2001年4月、自民党総裁選で小泉純一郎氏と橋本龍太郎氏が戦って小泉氏が勝利し、小泉内閣が成立します。
橋本内閣は国民に人気がなかったのですね。
その後、現在まで続く日本の政治を振り返ると、“ポピュリズム”“大衆迎合”でない政治はほとんど不可能となっているようです。
日本が国際社会の中で名誉ある地位を占めることのできる国に成長しようとしても、国民がそのような方向の政府を選択しないということで、現在の日本が国際社会で漂流しているのも日本国民が結果として選んだ道でしかない、といえるようです。
なお、96年以降の普天間返還問題の推移については、小川和久著「普天間問題」を参照してください。
それでは皆さん、良いお年をお迎えください。