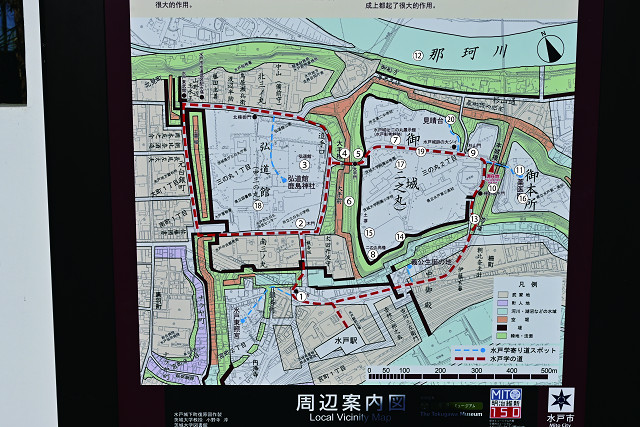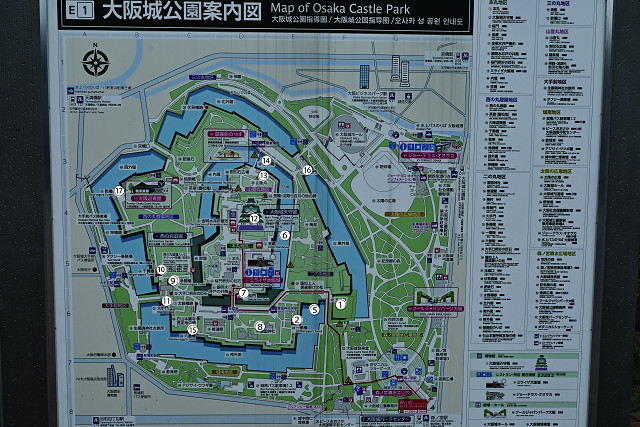2月14日にプライトンの三笘薫が決めたシュート、見事でした。こんなプレイができるサッカー選手、そうそう誕生するとは思えないしまして日本人がなし遂げるとは。私も動画を何度でも見直してしまいます。下記に動画を示します。
三笘の神トラップ・神タッチ・神シュート(動画)
日経新聞にも下記の記事が掲載されました。
歴史刻む三笘のゴール
2025年2月21日 日経新聞アナザービュー 武智幸徳
『2月14日のイングランド・プレミアリーグのチェルシー戦でサッカー日本代表の三笘薫(ブライトン)が決めたゴールは、まごうことなき芸術品だった。映像を何度見ても飽きることがない。
GKからのロングパスを背走しながら追い、頭越しに落ちてくるボールを小さく跳躍しながら優しく受け止めた。重力や質量を感じさせない人球一体感で度肝を抜いた刹那、小さく、大きくボールを1回ずつつついてDFを振り切り、フィニッシュに持ち込んだ。
卓越した選手でも生涯に一度あるかないかの会心作。・・・
三笘が見せた繊細なタッチをデニス・ベルカンプになぞらえる意見があるのも頷ける。このオランダ代表のレジェンドが1998年ワールドカップフランス大会のアルゼンチン戦で奪ったゴールも「完璧」で、W杯のたびに紹介される。三笘のゴールもプレミアの歴史に深く刻まれ、事あるごとに引用されるとしたら本当にすごいことだ。
・・・』
オランダのベルカンプが見せたフランスW杯での見事なトラップとシュートについては、2022年に私も記事にしたことがあります。日本代表の浅野がW杯ドイツ戦で見せたトラップとシュートにからめてです。
浅野の超絶トラップ! 2022-11-24
日本対ドイツ戦の日本の2点目です。板倉からロングパスを受けた浅野がボールをトラップし、ドイツディフェンスとキーパーをかわしてゴールに突き刺しました。
私は「浅野の一世一代のトラップだった」とつぶやいていました。
この浅野の見事なプレイから、私は「ベルカンプ」を思い出しました。ベルカンプの絶妙トラップからのゴールを見た記憶がある・・・。そう、フランスW杯でのオランダ対アルゼンチン戦でのオランダ・ベルカンプの見事なトラップとシュートです。
天才FWベルカンプ、誕生日に超絶トラップの伝説ゴール再脚光 「美しい」「最高の実況」
2019.05.11
『公開された映像は、98年フランスW杯準々決勝アルゼンチン戦で生まれた一撃だ。1-1と拮抗した展開で迎えた後半44分、DFフランク・デ・ブールが自陣から対角線上にロングボールを供給。これに反応したのがベルカンプだ。
相手ペナルティーエリアに走り込んだベルカンプは落下地点に右足を伸ばすと、足の甲に吸い付くような超絶トラップを披露。直後に相手DFロベルト・アジャラがボール奪取を狙ったなか、地面にボールが付くと同時に2タッチ目で完璧にボールを制御してアジャラをかわすと、右足アウトサイドで決勝ゴールを決めた。』
上記のサイトで、そのベルカンプのプレイを動画で見ることができます。今回再見したら、三笘の技術レベルとほど同等の技術を発揮したプレイでした。
このとき、ベルカンプはピッチに大の字になって驚喜し、チームメートがベルカンプに折り重なりました。三笘の驚喜はそれに比べるとおとなしいですね。ピッチに大の字になってチームメートが折り重なるパフォーマンスを見たかったです。
いずれにしろ、ベルカンプのあのプレイが今に至るまで伝説ゴールとして語り伝えられているのであれば、今回の三笘のプレイも同じように語り伝えられるべきものです。
同じ日本人として誇りに思います。
三笘の神トラップ・神タッチ・神シュート(動画)
日経新聞にも下記の記事が掲載されました。
歴史刻む三笘のゴール
2025年2月21日 日経新聞アナザービュー 武智幸徳
『2月14日のイングランド・プレミアリーグのチェルシー戦でサッカー日本代表の三笘薫(ブライトン)が決めたゴールは、まごうことなき芸術品だった。映像を何度見ても飽きることがない。
GKからのロングパスを背走しながら追い、頭越しに落ちてくるボールを小さく跳躍しながら優しく受け止めた。重力や質量を感じさせない人球一体感で度肝を抜いた刹那、小さく、大きくボールを1回ずつつついてDFを振り切り、フィニッシュに持ち込んだ。
卓越した選手でも生涯に一度あるかないかの会心作。・・・
三笘が見せた繊細なタッチをデニス・ベルカンプになぞらえる意見があるのも頷ける。このオランダ代表のレジェンドが1998年ワールドカップフランス大会のアルゼンチン戦で奪ったゴールも「完璧」で、W杯のたびに紹介される。三笘のゴールもプレミアの歴史に深く刻まれ、事あるごとに引用されるとしたら本当にすごいことだ。
・・・』
オランダのベルカンプが見せたフランスW杯での見事なトラップとシュートについては、2022年に私も記事にしたことがあります。日本代表の浅野がW杯ドイツ戦で見せたトラップとシュートにからめてです。
浅野の超絶トラップ! 2022-11-24
日本対ドイツ戦の日本の2点目です。板倉からロングパスを受けた浅野がボールをトラップし、ドイツディフェンスとキーパーをかわしてゴールに突き刺しました。
私は「浅野の一世一代のトラップだった」とつぶやいていました。
この浅野の見事なプレイから、私は「ベルカンプ」を思い出しました。ベルカンプの絶妙トラップからのゴールを見た記憶がある・・・。そう、フランスW杯でのオランダ対アルゼンチン戦でのオランダ・ベルカンプの見事なトラップとシュートです。
天才FWベルカンプ、誕生日に超絶トラップの伝説ゴール再脚光 「美しい」「最高の実況」
2019.05.11
『公開された映像は、98年フランスW杯準々決勝アルゼンチン戦で生まれた一撃だ。1-1と拮抗した展開で迎えた後半44分、DFフランク・デ・ブールが自陣から対角線上にロングボールを供給。これに反応したのがベルカンプだ。
相手ペナルティーエリアに走り込んだベルカンプは落下地点に右足を伸ばすと、足の甲に吸い付くような超絶トラップを披露。直後に相手DFロベルト・アジャラがボール奪取を狙ったなか、地面にボールが付くと同時に2タッチ目で完璧にボールを制御してアジャラをかわすと、右足アウトサイドで決勝ゴールを決めた。』
上記のサイトで、そのベルカンプのプレイを動画で見ることができます。今回再見したら、三笘の技術レベルとほど同等の技術を発揮したプレイでした。
このとき、ベルカンプはピッチに大の字になって驚喜し、チームメートがベルカンプに折り重なりました。三笘の驚喜はそれに比べるとおとなしいですね。ピッチに大の字になってチームメートが折り重なるパフォーマンスを見たかったです。
いずれにしろ、ベルカンプのあのプレイが今に至るまで伝説ゴールとして語り伝えられているのであれば、今回の三笘のプレイも同じように語り伝えられるべきものです。
同じ日本人として誇りに思います。