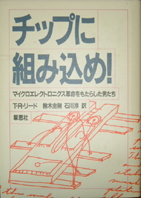テキサス・インスツルメンツ社のジャック・キルビーと、フェアチャイルド社(当時)のロバート・ノイスとは、ほぼ同時期(1958~1959)にそれぞれ単独で半導体集積回路(IC)の発明を完成した発明者として知られています。
ところで、キルビーとノイスの研究アプローチが、対照的といえるぐらいに異なっている点に興味をそそられます。「チップに組み込め!」を古本で再度購入した動機も、その点を確認することが最大の目的でした。
キルビーは1958年5月、セントララブという会社からテキサス・インスツルメンツ社(TI社)に転籍します。電気回路の大規模化の問題解決のため、キルビーは的はずれのプロジェクトに取り組まされることになります。
TI社は夏期休暇で全員が7月の同じ数週間を休みますが、キルビーは入社直後で休暇の権利がなく、ひとりだけ研究室に残されます。
ここでキルビーは、一心にシリコンのことを考え始めます。そして1枚のシリコン半導体基板の上に、ダイオード、トランジスタのみならず、抵抗器やコンデンサーも配置できることに思い至るのです。
全員が休暇から戻ってきてプロジェクトにとりかかったとき、キルビーは自分のノートのスケッチを上司であるウィリス・アドコックに見せます。アドコックはそれほど興奮しませんでしたが、一つの試作品(発振器)を作ることを承認します。9月12日、キルビーが試作したワンチップ発振器は見事に作動しました。
キルビーはICの開発の後、順調に昇給と昇進を繰り返し、ポケット電卓の開発もこなし、TI社研究開発部門のナンバー・ツーとなります。ところが、1970年、彼は会社を去ります。フリーランスの発明家になるのです。
「ダラスの北のはずれのとりちらかしたオフィスでは、内向的で口数の少ないジャック・キルビーが、公式には自分以外を代弁する必要のない境遇に満足している。ときおり立ち寄る記者や歴史家にはよく話をするが、このごろはかねがね最も気に入っている仕事--発明に黙々と取り組んでほとんどの時間を創造的に過ごしているのである。」
一方のノイスは、ここで記したとおり、同僚とおしゃべりをしながらアイデアを固めていくタイプです。
「もの静かなキルビーはひとりで問題と取り組み、徹底的に考えぬいて最高の成果をあげるタイプだが、ノイスはそれと違って、外向的かつおしゃべりで、直感を重んじる発明家であり、自分の着想に耳を傾けて、うまくいきそうにないところを指摘してくれる人間を必要とする。その冬、ノイスの共鳴板になってくれたのは、友人のゴードン・ムーアだった。」
物理学者であったノイスがショックレー(トランジスターの発明者のひとり)に突然呼び出され、ショックレー研究所の一員となります。その後8人の研究者とショックレー研究所を飛び出してフェアチャイルド社を立ち上げると、リーダーとして振る舞います。またフェアチャイルド社を飛び出してインテル社を創設し、ノイスが社長、ムーアが会長に就任します。
さらにシリコン・バレーのエグゼクティブが集まって半導体工業界を結成したとき、ノイスは理事会に名を連ね、スポークスマンとなります。
このように気質の異なるキルビーとノイスが、それぞれ単独でほぼ同時期にICの発明を完成しました。優れた発明を完成する過程で、その人ごとに思索を突き詰めていくアプローチが異なるのですね。
ちなみに私は沈思黙考型のようです。新入社員の頃は、「また居眠りしている」と同僚からからかわれたものです。
ところで、キルビーとノイスの研究アプローチが、対照的といえるぐらいに異なっている点に興味をそそられます。「チップに組み込め!」を古本で再度購入した動機も、その点を確認することが最大の目的でした。
キルビーは1958年5月、セントララブという会社からテキサス・インスツルメンツ社(TI社)に転籍します。電気回路の大規模化の問題解決のため、キルビーは的はずれのプロジェクトに取り組まされることになります。
TI社は夏期休暇で全員が7月の同じ数週間を休みますが、キルビーは入社直後で休暇の権利がなく、ひとりだけ研究室に残されます。
ここでキルビーは、一心にシリコンのことを考え始めます。そして1枚のシリコン半導体基板の上に、ダイオード、トランジスタのみならず、抵抗器やコンデンサーも配置できることに思い至るのです。
全員が休暇から戻ってきてプロジェクトにとりかかったとき、キルビーは自分のノートのスケッチを上司であるウィリス・アドコックに見せます。アドコックはそれほど興奮しませんでしたが、一つの試作品(発振器)を作ることを承認します。9月12日、キルビーが試作したワンチップ発振器は見事に作動しました。
キルビーはICの開発の後、順調に昇給と昇進を繰り返し、ポケット電卓の開発もこなし、TI社研究開発部門のナンバー・ツーとなります。ところが、1970年、彼は会社を去ります。フリーランスの発明家になるのです。
「ダラスの北のはずれのとりちらかしたオフィスでは、内向的で口数の少ないジャック・キルビーが、公式には自分以外を代弁する必要のない境遇に満足している。ときおり立ち寄る記者や歴史家にはよく話をするが、このごろはかねがね最も気に入っている仕事--発明に黙々と取り組んでほとんどの時間を創造的に過ごしているのである。」
一方のノイスは、ここで記したとおり、同僚とおしゃべりをしながらアイデアを固めていくタイプです。
「もの静かなキルビーはひとりで問題と取り組み、徹底的に考えぬいて最高の成果をあげるタイプだが、ノイスはそれと違って、外向的かつおしゃべりで、直感を重んじる発明家であり、自分の着想に耳を傾けて、うまくいきそうにないところを指摘してくれる人間を必要とする。その冬、ノイスの共鳴板になってくれたのは、友人のゴードン・ムーアだった。」
物理学者であったノイスがショックレー(トランジスターの発明者のひとり)に突然呼び出され、ショックレー研究所の一員となります。その後8人の研究者とショックレー研究所を飛び出してフェアチャイルド社を立ち上げると、リーダーとして振る舞います。またフェアチャイルド社を飛び出してインテル社を創設し、ノイスが社長、ムーアが会長に就任します。
さらにシリコン・バレーのエグゼクティブが集まって半導体工業界を結成したとき、ノイスは理事会に名を連ね、スポークスマンとなります。
このように気質の異なるキルビーとノイスが、それぞれ単独でほぼ同時期にICの発明を完成しました。優れた発明を完成する過程で、その人ごとに思索を突き詰めていくアプローチが異なるのですね。
ちなみに私は沈思黙考型のようです。新入社員の頃は、「また居眠りしている」と同僚からからかわれたものです。