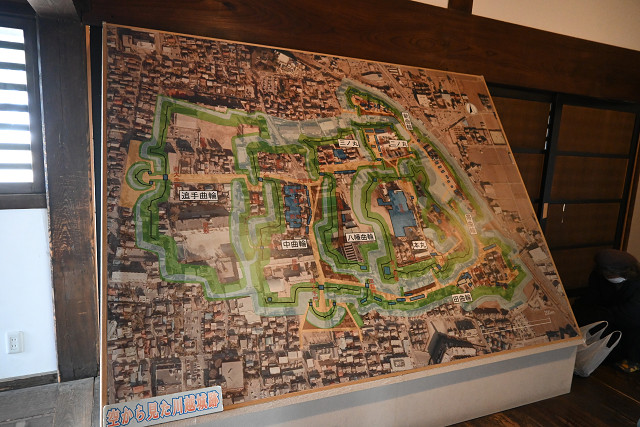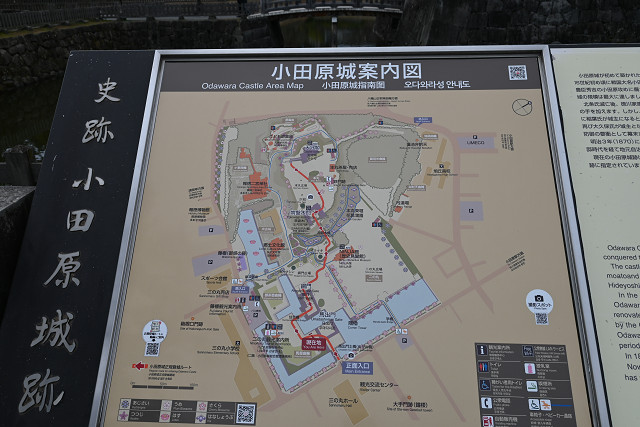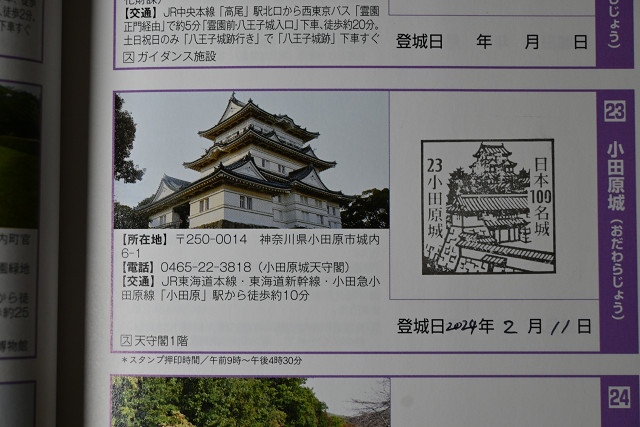日経平均「バブル最高値超え」で4万5000円突破の現実味
2/24
日経平均株価がバブル最高値を超えました。
日本株価上昇の原動力は、アメリカの株価上昇だといいます。
そしてアメリカの株価上昇の原動力は、たった一つの会社の業績向上とそれに基づくその会社の株価上昇、時価総額の上昇だといいます。
そのたった一つの会社とは、半導体メーカーであるnVIDIA(エヌビディア)です。
エヌビディアは、AIに特化した半導体の独占的なメーカーであり、最近のAIの進歩に伴って業績が急速に伸びているといいます。
私は、エヌビディアの存在については、2007年頃から知っていました。
以前、パソコンのOSがWindows95に代わった以降、パソコンの拡張ボードにグラフィックボード(ビデオボード)が接続されているのが常でした。ウインドウズの高解像度の画面を制御するには、それ専用の半導体が必要とされ、グラフィックボードによってその機能を満たしていたのです。
1998年以降の私のパソコンについて、グラフィックボードの変遷をたどってみました。以下に、M/Bと書いたのはマザーボード、 CPUと書いたのはいわゆるCPU、そしてGPUと書いたのがグラフィックボードを意味します。GPUは「グラフィックスプロセッサーユニット」の略です。
1998年から2007年にかけては、グラフィックボードのメーカーとしては、Creative Labs、Diamond、Matrox、Canopus、NVIDIA、ASUSなどが入り乱れています。
2008~2013の時代、NVIDIAの一人勝ちになりました。
2013年以降は、CPUの性能が向上したのでしょう。グラフィックボードは搭載されないようになりました。
以上のように、2008~2013に私が所有していたパソコンにおいて、グラフィックボードはエヌビディアの一人勝ちである、というのが私の印象でした。よっぽど傑出した技術を保持していたのでしょう。
数年前、またエヌビディアの名前を聞きました。クルマの自動運転のニュースです。クルマの自動運転の開発において、エヌビディアのGPUに関する技術が役立っている、というニュースでした。パソコンのグラフィックスの技術を持っているのだから、それが理由だろうと納得していました。
それがこの1,2年、エヌビディアの技術がAIで役立っているというニュースに取って代わりました。
たった1社の業績によって、世界の株価が多大な影響を受けている、という事実には驚くばかりです。
以下に、私が所有していたパソコンの構成をリストアップします。
1998
CPU Pentium(MMX) 200MHz
GPU Graphics Blaster Exxtreme (Creative Labs)
1998
CPU AMD K6 232MHz
GPU Diamond Stealth 3D 2000Pro
1999
CPU Pentium(MMX) 200MHz
GPU Matrox Millennium G200 SD PCI
2007
M/B P3B-F
CPU Pentium III 1000MHz
GPU Canopus SPECTRA5400 Premium Edition
2007
M/B P4B533-V
CPU Pentium4 2542MHz
GPU MSI MS-StarForce GeForce4 MX 440/MX 440SE (NVIDIA GeForce4 MX 440/MX 440SE)
2007
CPU Dual Pentium4 2600MHz
GPU ASUS RADEON A9200SE Secondary
2007
M/B P4V800D-X
CPU Pentium4 2542MHz
GPU ASUS RADEON A9200SE Secondary
2007
M/B P4V800D-X
CPU Dual Pentium4 2600MHz
GPU Canopus SPECTRA Light G64
2007
M/B P5B
CPU Dual Pentium III 2137MHz
GPU NVIDIA GeForce 7300 GS
2007
M/B P5B
CPU Core2 Duo E6420
GPU GeForce 7300GS 256MB
2008
M/B P5B
CPU Dual Pentium III 2137MHz
GPU NVIDIA GeForce 7600 GS
2009
M/B P5Q PRO
CPU Core 2 Quad
GPU NVIDIA GeForce GTS 250
2011
M/B P8P67
CPU nVIDIA GeForce GTX 550 Ti
GPU
2013
M/B Inspiron 17R Turbo(7720)BTX
CPU Core i7-3630QM
GPU NVIDIA GeForce GT 650M GDDR 2GM
2013
M/B P8Z77-V
CPU Core i7-3770
GPU なし
2019
M/B ASRocK B360M
CPU Core i5-8400
GPU なし
2023
CPU Core i5-10500
GPU なし
2/24
日経平均株価がバブル最高値を超えました。
日本株価上昇の原動力は、アメリカの株価上昇だといいます。
そしてアメリカの株価上昇の原動力は、たった一つの会社の業績向上とそれに基づくその会社の株価上昇、時価総額の上昇だといいます。
そのたった一つの会社とは、半導体メーカーであるnVIDIA(エヌビディア)です。
エヌビディアは、AIに特化した半導体の独占的なメーカーであり、最近のAIの進歩に伴って業績が急速に伸びているといいます。
私は、エヌビディアの存在については、2007年頃から知っていました。
以前、パソコンのOSがWindows95に代わった以降、パソコンの拡張ボードにグラフィックボード(ビデオボード)が接続されているのが常でした。ウインドウズの高解像度の画面を制御するには、それ専用の半導体が必要とされ、グラフィックボードによってその機能を満たしていたのです。
1998年以降の私のパソコンについて、グラフィックボードの変遷をたどってみました。以下に、M/Bと書いたのはマザーボード、 CPUと書いたのはいわゆるCPU、そしてGPUと書いたのがグラフィックボードを意味します。GPUは「グラフィックスプロセッサーユニット」の略です。
1998年から2007年にかけては、グラフィックボードのメーカーとしては、Creative Labs、Diamond、Matrox、Canopus、NVIDIA、ASUSなどが入り乱れています。
2008~2013の時代、NVIDIAの一人勝ちになりました。
2013年以降は、CPUの性能が向上したのでしょう。グラフィックボードは搭載されないようになりました。
以上のように、2008~2013に私が所有していたパソコンにおいて、グラフィックボードはエヌビディアの一人勝ちである、というのが私の印象でした。よっぽど傑出した技術を保持していたのでしょう。
数年前、またエヌビディアの名前を聞きました。クルマの自動運転のニュースです。クルマの自動運転の開発において、エヌビディアのGPUに関する技術が役立っている、というニュースでした。パソコンのグラフィックスの技術を持っているのだから、それが理由だろうと納得していました。
それがこの1,2年、エヌビディアの技術がAIで役立っているというニュースに取って代わりました。
たった1社の業績によって、世界の株価が多大な影響を受けている、という事実には驚くばかりです。
以下に、私が所有していたパソコンの構成をリストアップします。
1998
CPU Pentium(MMX) 200MHz
GPU Graphics Blaster Exxtreme (Creative Labs)
1998
CPU AMD K6 232MHz
GPU Diamond Stealth 3D 2000Pro
1999
CPU Pentium(MMX) 200MHz
GPU Matrox Millennium G200 SD PCI
2007
M/B P3B-F
CPU Pentium III 1000MHz
GPU Canopus SPECTRA5400 Premium Edition
2007
M/B P4B533-V
CPU Pentium4 2542MHz
GPU MSI MS-StarForce GeForce4 MX 440/MX 440SE (NVIDIA GeForce4 MX 440/MX 440SE)
2007
CPU Dual Pentium4 2600MHz
GPU ASUS RADEON A9200SE Secondary
2007
M/B P4V800D-X
CPU Pentium4 2542MHz
GPU ASUS RADEON A9200SE Secondary
2007
M/B P4V800D-X
CPU Dual Pentium4 2600MHz
GPU Canopus SPECTRA Light G64
2007
M/B P5B
CPU Dual Pentium III 2137MHz
GPU NVIDIA GeForce 7300 GS
2007
M/B P5B
CPU Core2 Duo E6420
GPU GeForce 7300GS 256MB
2008
M/B P5B
CPU Dual Pentium III 2137MHz
GPU NVIDIA GeForce 7600 GS
2009
M/B P5Q PRO
CPU Core 2 Quad
GPU NVIDIA GeForce GTS 250
2011
M/B P8P67
CPU nVIDIA GeForce GTX 550 Ti
GPU
2013
M/B Inspiron 17R Turbo(7720)BTX
CPU Core i7-3630QM
GPU NVIDIA GeForce GT 650M GDDR 2GM
2013
M/B P8Z77-V
CPU Core i7-3770
GPU なし
2019
M/B ASRocK B360M
CPU Core i5-8400
GPU なし
2023
CPU Core i5-10500
GPU なし