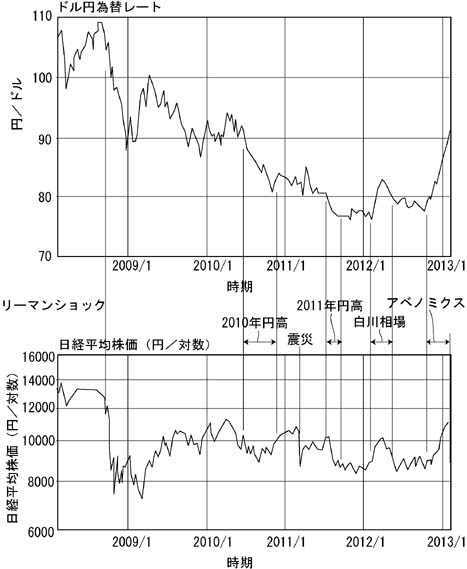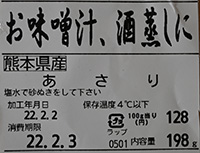自衛隊は市街戦を戦えるか (新潮新書)
自衛隊は市街戦を戦えるか (新潮新書)この本を読んでびっくりしたこと、それは、少なくとも2010年頃までは(ひょっとすると今でも)、“陸上自衛隊は戦闘で敵に勝利できるような訓練をしてこなかった”、ということです。
2002年頃、九州の第8師団が市街地戦闘訓練を行うための簡易市街地訓練場の構築を開始しました。著者はその頃第8師団に所属していました。
当時、陸上自衛隊ではほとんど知られていなかったダットサイトを米国が使用しているとの情報が入ってきました。ダットサイトは銃に装着する照準器の一種で、中に見える赤い点を目標に併せてトリガーを引くだけで弾を標的に命中させられるという便利な道具です。
私は、ダットサイト(ドットサイト)の存在を今回初めて知りました。ウィキの照準器の中に説明があります。
ダットサイトを供給していたのは、オペレーション・トレーニング・サービス(OTS)という民間企業でした。官公庁向けに、戦闘のための訓練用品や特殊装備品の販売を行っています。同社の畠山富士男氏から情報が得られました。
2003年、著者は40連隊の連隊長となり、小倉駐屯地に着任しました。まだ銃にダットサイトは使用していませんでした。
畠山氏が言うには、性能の高いスコープの能力を紹介したとき、隊員は「これが欲しい」との反応ではなく、「うちの○○2曹ならこれがなくても同じように当てられるから問題ない」と言ったそうです。民間から提供される道具に対して強い拒否感がありました。これはどの部隊でも共通していたと言います。
陸上自衛隊には、「他を知ろうとしない文化」「与えられたものだけで戦闘をするものだ」という文化が刷り込まれていました。
隊員の側から、実戦的な訓練やスキルアップを狙った訓練を提案すると、幹部や上司から「常識から外れている」「教範にないことはやってはならない」と止められてしまい、結局隊員はモチベーションを失ってしまいました。
40連隊では隊員が自発的に、民間のガン・インストラクターであるアメリカ在住のナガタ・イチロー氏から訓練を受けていました。
当時、市街地訓練教育を始めた隊員であっても、銃を取り扱う際に銃口が人に向いても何も感じていませんでした。ナガタ氏は強い口調でこれを非難しました。著者たちは「この銃は弾倉がついていないから弾は出ません」と反論しますが、「弾倉がついていなくても薬室に弾が込められていることがあるだろう」と簡単に再反論されてしまいます。当時の陸上自衛隊はこんなレベルでした。
ナガタ氏は強い口調で、「銃口を人に向けてはならない。米国では、軍、警察、一般人でも銃口は人に向けません。基本中の基本です」と指摘ましました。
少なくとも2003年当時の陸上自衛隊は、銃の取り扱いの基本を身につけていなかったのです。私は、村上春樹著「1Q84」3巻89ページ(文庫)の記載でこの基本を知っていました。青豆に拳銃を手渡したタマルは、「あんたは二つの重大な間違いを犯した」と指摘しました。「・・・もうひとつは受け取ってから、俺の方にほんの一瞬だが銃口を向けたことだ。どちらも絶対にやってはならないことだ。」
さて、2002年当時の陸上自衛隊が銃の取り扱いの基本をマスターしていなかったことはわかりました。ところで、日本の警察はどうなのでしょうか。
陸上自衛隊で実戦的な訓練が行われずにきた理由は何でしょうか。
自衛隊は、「実戦で戦うことはない」という情勢認識がそもそもの阻害要因となっています。このような情勢認識のもとでは、心の奥では「実戦の場で戦い抜く能力を無理して身につける必要はない」との気持ちが生じてしまいます。
そして、2年ごとで交代する部隊長が、とりあえず喜んで満足して、上司へ報告できるような訓練を行うことに重点を置くようになるのです。
1980年代、著者は情報小隊長として勤務していました。
訓練時、敵との距離が近くなったので、「敵に見つからない行動をとるように」と小隊へ指示を出そうとすると、ベテランの陸曹がこんなことを言ってきました。
「それでは情報入手に時間がかかってしまい、連隊本部から怒られます。道路沿いをバンバン歩かせていった方がいいです」
「死んでも2時間で復活ですから」「それにバンバン撃ってくる場所に敵がいることが分かるし、触雷によって地雷の存在も知ることができるから、それでよい」
いやはや、驚くばかりです。
孫がわが家に遊びに来たとき、ニンテンドースイッチを使って戦闘ゲームをやっています。見ていると、本人が演じている役がしょっちゅう戦死し、孫は「あ、死んだ」とつぶやきます。しかしすぐに復活します。
また、敵も味方も、身を隠すということをしません。実戦では、敵の姿が視認できることはほんとどないにもかかわらずです。戦場で生き残るためには敵に姿を見せないことが鉄則です。ゲームでは死んでもすぐに復活するから身を隠す必要を感じないのでしょう。
こんど孫のそのゲームを見たら、「陸上自衛隊というよ」とからかうことにします。
陸上自衛隊では、「陣地攻撃訓練」が重視されていました。この訓練では、最後に敵陣地に突撃して陣地を確保します。
富士トレーニングセンター(FTC)は2000年に編成されました。ここでは、訓練のために訪れた全国の普通科中隊と、センターに所属する敵部隊とが戦闘訓練を行います。FTCではバトラーが使用されていました。発射されたビームが命中すると敵に損耗を与えたことが分かります。
シナリオ通りワンパターンの突撃訓練を行ってきた部隊は、当然ながら敵陣地に到達する前に全滅していまいます。
著者が連隊長のとき、素早い照準を可能にするダットサイトやライト、スコープ、サプレッサー(銃声や閃光を軽減する装置)などの個人の装具類を小銃につけることは官給品以外、許されない環境でした。
ここで、
飯柴智亮さんに一体何が?! 2008-07-24
米国陸軍飯柴大尉のその後 2008-08-10
を思い出しました。この事件について、飯柴さんの釈明として、飯柴智亮・元米国陸軍大尉の陸自への兵器密輸出の声明文を読みました。それによると・・・
2005年秋、飯柴氏が所属する大隊が、渡米して近接戦闘訓練を行う陸上自衛隊所属の富士普通科教導連隊に訓練を施すこととなり、飯柴氏が連絡将校を務めました。
部隊が日本に帰国後も連絡を取り合うようになり、のちに電話による連絡がありました。『陸自内に新設された特殊作戦群が、新たに購入した米国コルト社製M4カービン小銃に取り付ける光学サイトの購入を検討、結果米国製EOTech 553が選ばれた。』
『EOTech 553六十個を購入して発送してくれないか。』
この要請に応じて日本宛に発送したのですが、輸出許可が必要であることを後で知りました。
今回の著書で明らかになった2000年代当時の陸上自衛隊の実情からすると、実戦で本当に必要な小道具を購入するに際し、正規でないルートで購入しなければならない事情が陸自側に存在していた可能性も否定できません。
2015年頃からは、世界の部隊が当たり前のように実際の戦闘で使用しているものを手にすることができるようになっています。
著者が連隊長のとき、民間のサバイバルゲーム(サバゲー)施設で訓練をしていました。サバゲーでは、自衛隊の部隊がサバゲーの対向部隊と対戦します。
ガン・インストラクターのトモ長谷川氏から紹介され、対向部隊専門家と話をしました。対向部隊をやっていると、対戦する部隊の強さがわかります。「普通」「強い」「怖いレベル」に分類することができ、怖いレベルの部隊ならば、戦闘が始まった瞬間に彼ら対向部隊を数発で仕留めてしまう」といいます。著者の連隊の中で、Iという陸曹のチームが「怖いレベル」に到達していたのです。
著者が連隊長のとき、電動ガンを使用した訓練も取り入れました。電動ガンではBB弾というプラスチックの丸い弾を使用して撃ち合います。
陸上自衛隊全体でも、訓練に電動ガンが導入され始めました。しかし、ちょうどその時期(2006年頃)に部隊内の銃が紛失する事案が発生し、その影響で、私的に購入した電動ガンは部隊へ持ち込むことが禁止されるという動きが全国的に広がったのです。陸上自衛隊での電動ガンの導入は激減しました。電動ガンによる訓練のメリットは計り知れないにもかかわらず、です。
著者が40連隊長を離任した後、後任の連隊長は昔の訓練パターンに戻してしまいました。
さて、2000年代までの陸上自衛隊がいかに実戦で勝てない軍隊であったかが、この著書で明らかになりました。それでは現在はどうでしょうか。
2008年に「飯柴智亮著「2020年日本から米軍はいなくなる」 2014-08-31」で書いたように、飯柴氏は2008年、「陸自で本当に使えそうなのは、宇都宮の中央即応連隊、九州の水陸両用団の基幹連隊になる西部方面普通科連隊、習志野第1空挺団、松本の山岳レンジャーであり、あとは要らない。
日本に戦車は1台も要らない。」と述べていました。
おそらくここで「使えそう」と言われた部隊は、ちゃんと「実戦で勝てるための訓練」がなされていると信じたいです。その他の一般「普通科連隊」では、まだダメかもしれませんが。