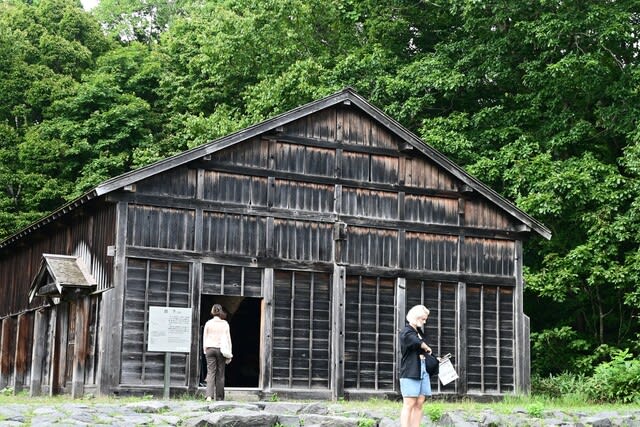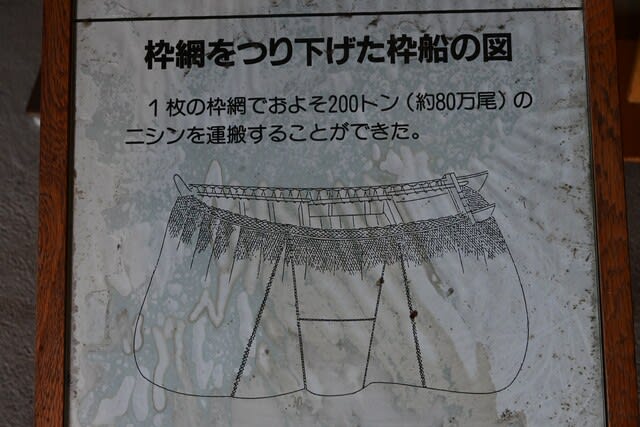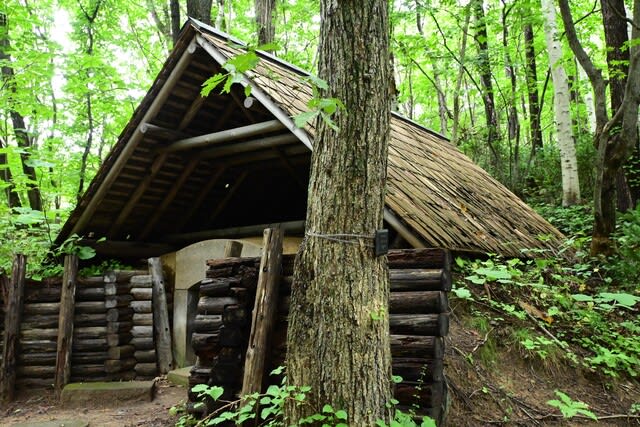アルツハイマー征服 (角川文庫)下山 進 (著)


この本の増補部分については、の
レカネマブはなぜ成功したか 2023-09-01で紹介しました。
また、初版部分の内容について、(1)エーザイのアリセプトの開発物語、(2)世界のアルツハイマー病研究の進捗とその成果としてのレカネマブの開発成功まで、の2つに分け、前回記事
山下進著「アルツハイマー征服」遺伝子工学編1 2023-09-11では(2)世界のアルツハイマー病研究の進捗とその成果としてのレカネマブの開発成功まで、について、1回目を報告しました。
ここでは、2回目について報告します。
《抗体薬・ハピネツマブ》
ワクチンが副作用を起こすのであれば、抗体そのものを投与すればいい。シェンクらは、トランスジェニック・マウスを使って抗体も作り出していました。この抗体のうちの一つをヒト化した抗体薬がバピネツマブと名付けられました。
バピネツマブのフェーズ1において、ハーバード大学にあるブリガム・アンド・ウィメンズ病院のレイサ・スパークリングは、被験者の一人にMRIによって脳の浮腫が見つけられました。この浮腫は、アミロイド関連画像異常(ARIA)と名付けられました。脳の血管に微少の出血を伴う浮腫もありました。
ARIAのため、フェーズ3の投与量は1mgまで抑えられました。結果として、フェーズ3は失敗に終わりました。
エラン、元のアセナ・ニューロサイエンスは、その開発拠点をすべて閉じることとなりました。
アミロイドβについて詳細に調べると、APPから切り出されたアミロイドβが集まってオリゴマー(十数個あつまったもの)を形成し、それがベータシート状をとって固まったものがアミロイド斑(老人斑)です。そこで、毒性を持つのはオリゴマーの段階だということを、2002年にデニス・セルコーが研究していました。スウェーデンの街ウメオで、家族性アルツハイマー病の家系を調べていたウプサラ大学のラース・ランフェルト(のちの「レカネマブ」の創始者)もこの少し前に気づいていました。
このころの研究結果から、アミロイドβが病気のトリガーであることが明らかになりました。ではなぜ、バピネツマブは効かなかったのか。バピネツマブは軽症から中等度のアルツハイマー病の患者が対象でした。これでは遅すぎるのではないか。そして投与量の1mgが少なすぎるのではないか。
ピッツバーグ大学の2人の研究者とスウェーデンのウプサラ大学が共同して作り上げた放射性化合物、ピッツバーグ・コンパウンドBは、静脈注射してPETスキャンで見れば、アミロイドβのたまり方が画像でわかります。
科学者たちは、アルツハイマー病は発症する前に、長い期間をかけて脳の中に変化が起こっているのではないか、と考えるようになりました。そしてワシントン大学のジョン・モリスは、ジョエル・プライスとともに、対象を65歳以上から45歳以上にまで引き下げることにしました。ピッツバーグ・コンパウンドBを利用したPETスキャンが使えるようになっていました。
ランディ・ベートマンは、ワシントン大学が把握する20人の家族性アルツハイマー病の遺伝子を持つ被験者を対象に調査を開始しました。さらに、国際的な調査の予算を獲得します。DIANプロジェクトが開始しました。
125人のデータが集まりました。それが1枚の表にまとめられました。その表は、アルツハイマー病が発症するまで脳内で起きている変化を発症前30年さかのぼり、発症後の変化を10年予見していました。アミロイドβは発症の20年前からたまり始め、タウは発症の10年前から急速に増えていました。
この論文の発表により、バピネツマブや別のソラネズマブの治験は、そもそも介入の時期が遅かったのでは?と疑念を持たれました。
《抗体薬・アデュカヌマブ》
バイオジェン社のアルフレッド(アル)・サンドロックは、業界でドラッグハンターと呼ばれていました。サンドロックは目利きとしていくつもの種をバイオジェンに持ち込んできていました。
サンドロックの手中には、新たな抗体薬BII037がありました。のちのアデュカヌマブと呼ばれる薬の共同開発権を、チューリッヒ大学のロジャー・ニッチとクリストフ・ホックの会社ニューリミューン社から購入していたのです。2007年11月です。チューリッヒ大学のロジャー・ニッチとクリストフ・ホックは、この記事の1回目で紹介した、ワクチン療法のフェーズ2に参加していた科学者です。
アミロイドβは、脳内だけでなく、体のいたるところで生じていることをデニス・セルコーが明らかにしていました。それに対する抗体も自然発生的に生まれていることもわかっていました。ニッチとホックは、1000以上もの検体の中で、アルツハイマー病にかかりやすいはずなのに発病していない人などをえらび、探し出したのがBIIB037、のちのアデュカヌマブでした。2007年11月、バイオジェン社はニューリミューン社から共同開発権を取得しました。
両社は、バピネツマブの失敗から学んでいました。バピネツマブ治験当時はPETをとっていないので、本当にアルツハイマー患者かどうかがわかりませんでした。また中等度まで進んだ患者が入っていましたが、そもそも軽症患者を選んで治験すべきだったのではないか。投与量が少なすぎたのではないか。このころには、ARIAはそれほど深刻な副作用でないことがわかっており、フェーズ2での最大投与量は10mgとされました。
アルツハイマー病薬剤の治験について、アリセプトの開発費が150億円であったところ、抗体薬系の費用は探索から臨床まで2000億円~3000億円が予想されていました。各社が単独での治験ではリスクが大きすぎます。結局、エーザイとバイオジェンが共同開発を行うこととなりました。バイオジェンは後のアデュカヌマブとタウ抗体薬を有し、エーザイは後のレカネマブとベース阻害薬のエレンベセスタットを有していました。
2014年11月、バイオジェンのアデュカヌマブのフェーズ2の結果が出ました。アミロイドを除去し、認知機能の面でも効果がある、という画期的な結果でした。
アデュカヌマブのフェーズ3では、「中間解析」を行っています。治験費用があまりにも膨大なので、中間解析で目標が達成できないとわかったら治験を中止するという趣旨です。
その中間解析で、副作用はない、治療的効果もない、との結果が出てしまいました。治験の中止が決定しました。
中間解析は、2018年12月までのデータをもとに解析され、中止が発表になる翌年3月までも治験は行われていました。この結果も加えて解析した結果、どんでん返しがありました。治験の大きなグループ二つのうち、一方(EMERGE)は治療上の目標をすべて達成しています。もう一つのグループ(ENGAGE)も10mg以上投与では有意に結果が出ています。
調べてみると、治験の初期段階では投与量をあげないように、とあったのです。10mg投与のグループも、中間解析段階のデータではまだ10mg投与が始まっていなかったのです。
2019年10月、バイオジェンとエーザイは、アデュカヌマブの新たな解析結果に基づき、米国FDAへの新薬承認申請を発表しました。
FDAはアデュカヌマブの審査に当たって、外部の委員による諮問委員会を開くことにしました。FDAは、有意な結果を示せなかった一方の治験結果(ENGAGE)を除外する、と述べたようです。これに諮問委員は反発しました。結論は「不賛成」です。
2021年6月、FDAはアデュカヌマブを「条件付き承認」としました。しかしその年の12月、欧州と日本の当局が非承認あるいは承認見送りとし、2022年4月にはアメリカの公的保険メディケアが保険の対象としないことを決定しました。バイオジェンはアデュカヌマブに関して営業活動を中止します。
「FDAとバイオジェンは、非公式な交渉を重ねた」との報道も反対論に拍車をかけました。中間解析後の追加データによる結果を、サンドロックはFDAの関係者に開示しましたが、その会合が公式に記録されてはいない、というのです。
バイオジェンには社内抗争がありました。
中間解析において、サンドロックの知らないところで、2つの治験データを一緒にして解析したことも後からわかりました。別々に解析していれば、中間解析においても一方のグループで効果が出ており、治験を中止せずに投与期間を完遂したはずです。治験を中止したことで、18ヶ月の期間続けた患者数は全体の半分になってしまいました。これでは「10mg投与で効いている」と主張しても、患者の数が少なく説得力がありません。
2021年12月、サンドロックはバイオジェンを去りました。
この後、エーザイが主導してバイオジェンと共同開発したレカネマブが成功に至りました。このブログの
レカネマブはなぜ成功したか 2023-09-01において言及しました。
《抗体薬の失敗と成功》
アルツハイマー病の抗体薬については、バピネツマブ→アデュカヌマブ→レカネマブの流れで開発が進行し、最後のレカネマブのみが成功しました。
しかし、現時点から振り返ってみると、レカネマブのみならず、バピネツマブ、アデュカヌマブについても、正しく治験していればいずれも効果が立証されて承認に至った可能性があります。
パピネツマブは、投与する対象の患者の病気の進行が進みすぎており、また投与量が少なすぎました。
アデュカヌマブは、軽症者に投与する、投与量の最大を10mgまで上げる、ということにより、フェーズ2では極めて良好な結果でした。ところがフェーズ3と、承認審査の手続きで失敗がありました。まず、周囲の声に押されて中間解析を採用しました。また、バイオジェン社のサンドロックが知らないところで、2つのグループを分けずに中間解析が行われていました。投与量の多いグループは、初期段階で投与量が少なかった、ということも、サンドロックは後から気づきました。さらに、手続きの経緯について、多くの関係者から反感を受ける結果となってしまいました。
フェーズ3の治験を正しく再度行えば、アデュカヌマブが承認される可能性は高いと思われます。しかし、今となっては、膨大な治験費用を負担しようとする人は現れません。残念なことです。
レカネマブが、これら先行する薬剤の反省を踏まえ、正しくフェーズ3を行った結果として、治験の成功に至った経緯については、
レカネマブはなぜ成功したか 2023-09-01でご紹介したとおりです。