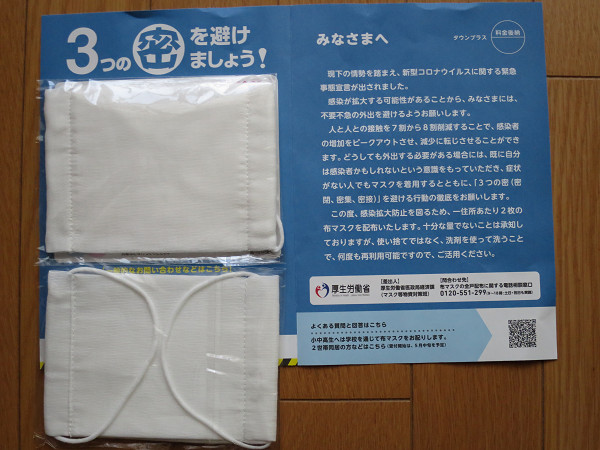入国緩和、カギは唾液検査の実現 無症状への適用を検証 2020年6月18日 朝日新聞
『安倍晋三首相は18日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部で、ベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランドからの入国緩和を進める方針を表明した。これに先立ち、国家安全保障会議の緊急事態大臣会合で、国際的な人の相互往来の再開に向けた防疫措置を決定。今後は唾液(だえき)を使ったPCR検査で、検査体制を拡充できるかがカギになる。
・・・
対策本部で首相は、唾液PCR検査などの導入や、出入国者のための「PCRセンター(仮称)」の設置を進めるよう指示した。・・・
ただ唾液検査は現在、発症から9日までの人が対象だ。出発前に健康観察を終えた出入国者のように、発症していない人や症状のない人への使用は認められていない。厚労省は症状のない人にも使えるか検証を進めており、空港検疫で確認された無症状の感染者らに協力を求めているが、国内の感染者数が減っているため、必要なデータを集めるのに時間がかかるという。
厚労省幹部は「無症状の人にも唾液検査が使えれば、検査の負担が減り、検疫をはじめ幅広い場面で検査の拡充が期待できる」としつつも、「偽陰性が出てはいけないので、しっかりと精度を検証しなければならない」と強調する。首相が表明したPCRセンターの設置は、唾液検査などの本格導入が前提で、実現のメドは立っていない。』
厚労省の対応はどうしても悠長ですね。
厚労省が唾液PCRを認める通知(「2019-nCoV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」の改訂について)を出したのは6月2日です。このブログでは「唾液PCRやっと解禁」として記事にしました。
通知の新旧対応表中では
『おおよそ発症から 9 日間程度は、唾液でのウイルス検出率も比較的高いことが報告されています(・・・)。加えて、発症後 10 日目以降の唾液については、ウイルス量が低下することが知られており推奨されません。』
とあるのみで、「無症状の人には使えない」とは明示で記載がありません。しかし、「発症から 9 日間程度」とあることから、『「無症状は対象外」と読め』との趣旨なのでしょう。分かりづらい通知です。
ブログ記事中にも書きましたが、新旧対応表中で紹介されている文献3件とも、無症状の人の評価を行っていません。政府は、判断まで1ヶ月もかけたのですから、その間に無症状の人で鼻腔PCR陽性だった人を対象に、唾液PCR評価を実施すべきでした。抜けていたとしか言いようがありません。
東京都新宿区で、夜の街関連の人たちから大量のPCR陽性者が出たのはつい最近です。この人たちの大部分は無症状だったと思われます。この人たち(PCR陽性も陰性もともに)にお願いして唾液PCRを同時に採取していれば、データはあっという間に増加したはずです。
厚労省と東京都新宿区の連携が悪いというか、厚労省はやる気がないのでしょうか。新宿区の夜の街は「クラスター」と言えますので、厚労省のクラスター対策班には連絡が行っていたはずです。厚労省内で、「クラスター対策班」と「唾液PCR検討班」(そんな班があるかどうか知りませんが)との連携が悪かったのでしょうか。
そもそも、通知の新旧対応表中に紹介された文献(Comparison of SARS-CoV-2 detection in nasopharyngeal swab and saliva)によると、患者76人について、鼻腔と唾液でPCR検査を行っています。うち、8人は両方とも陽性、1人は鼻腔のみ陽性、1人は唾液のみ陽性、66人は両方とも陰性です。
Figure 1 Aには、横軸を発症後の日数、縦軸をウイルスの量として、10人分のデータが載っています。△が鼻腔、●が唾液です。上記いずれかまたは両方が陽性であった10人のようです。発症後3日では鼻腔が陰性、19日では唾液が陰性、それ以外の8人(発症後7~13日)は両方とも陽性です。発症から最も早期の発症3日で、鼻腔が陰性、唾液が陽性です。このデータからは、「発症前の感染者は鼻腔よりもむしろ唾液の方がウイルスが多いのではないか」との仮説が成り立ちます。この仮説が真であったら、「無症状では唾液の方が有効」となるわけです。可及的速やかに結果を出すべきです。
また、厚労省の通知では、「加えて、発症後 10 日目以降の唾液については、ウイルス量が低下することが知られており推奨されません。」とあります。
しかし、北大の文献本文では、「回復期には、唾液の方が鼻腔に比較して早くにウイルスが減少している。」「最近の文献では、鼻腔には死んだウイルスが溜まり、“擬陽性”となる。興味あることに、われわれの結果では、鼻腔に比較して唾液の方が迅速に陰性になる。口の中では死んだウイルスが唾液によって効果的に清掃されるようだ。コロナ感染症患者の回復確認には唾液の方が好ましい。」と記載されています。即ち、北大の文献では、「発症後10日以降は唾液の精度が落ちる」のではなく、「発症後10日以降は唾液の方が正しく回復状況を示している」と述べているのです。
この点でも、唾液PCRの利点を、厚労省は逆に「唾液PCRの弱点」として捉えているわけです。ジャーナリズムはなぜこの点に切り込まないのか、理解に苦しみます。
『安倍晋三首相は18日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部で、ベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランドからの入国緩和を進める方針を表明した。これに先立ち、国家安全保障会議の緊急事態大臣会合で、国際的な人の相互往来の再開に向けた防疫措置を決定。今後は唾液(だえき)を使ったPCR検査で、検査体制を拡充できるかがカギになる。
・・・
対策本部で首相は、唾液PCR検査などの導入や、出入国者のための「PCRセンター(仮称)」の設置を進めるよう指示した。・・・
ただ唾液検査は現在、発症から9日までの人が対象だ。出発前に健康観察を終えた出入国者のように、発症していない人や症状のない人への使用は認められていない。厚労省は症状のない人にも使えるか検証を進めており、空港検疫で確認された無症状の感染者らに協力を求めているが、国内の感染者数が減っているため、必要なデータを集めるのに時間がかかるという。
厚労省幹部は「無症状の人にも唾液検査が使えれば、検査の負担が減り、検疫をはじめ幅広い場面で検査の拡充が期待できる」としつつも、「偽陰性が出てはいけないので、しっかりと精度を検証しなければならない」と強調する。首相が表明したPCRセンターの設置は、唾液検査などの本格導入が前提で、実現のメドは立っていない。』
厚労省の対応はどうしても悠長ですね。
厚労省が唾液PCRを認める通知(「2019-nCoV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」の改訂について)を出したのは6月2日です。このブログでは「唾液PCRやっと解禁」として記事にしました。
通知の新旧対応表中では
『おおよそ発症から 9 日間程度は、唾液でのウイルス検出率も比較的高いことが報告されています(・・・)。加えて、発症後 10 日目以降の唾液については、ウイルス量が低下することが知られており推奨されません。』
とあるのみで、「無症状の人には使えない」とは明示で記載がありません。しかし、「発症から 9 日間程度」とあることから、『「無症状は対象外」と読め』との趣旨なのでしょう。分かりづらい通知です。
ブログ記事中にも書きましたが、新旧対応表中で紹介されている文献3件とも、無症状の人の評価を行っていません。政府は、判断まで1ヶ月もかけたのですから、その間に無症状の人で鼻腔PCR陽性だった人を対象に、唾液PCR評価を実施すべきでした。抜けていたとしか言いようがありません。
東京都新宿区で、夜の街関連の人たちから大量のPCR陽性者が出たのはつい最近です。この人たちの大部分は無症状だったと思われます。この人たち(PCR陽性も陰性もともに)にお願いして唾液PCRを同時に採取していれば、データはあっという間に増加したはずです。
厚労省と東京都新宿区の連携が悪いというか、厚労省はやる気がないのでしょうか。新宿区の夜の街は「クラスター」と言えますので、厚労省のクラスター対策班には連絡が行っていたはずです。厚労省内で、「クラスター対策班」と「唾液PCR検討班」(そんな班があるかどうか知りませんが)との連携が悪かったのでしょうか。
そもそも、通知の新旧対応表中に紹介された文献(Comparison of SARS-CoV-2 detection in nasopharyngeal swab and saliva)によると、患者76人について、鼻腔と唾液でPCR検査を行っています。うち、8人は両方とも陽性、1人は鼻腔のみ陽性、1人は唾液のみ陽性、66人は両方とも陰性です。
Figure 1 Aには、横軸を発症後の日数、縦軸をウイルスの量として、10人分のデータが載っています。△が鼻腔、●が唾液です。上記いずれかまたは両方が陽性であった10人のようです。発症後3日では鼻腔が陰性、19日では唾液が陰性、それ以外の8人(発症後7~13日)は両方とも陽性です。発症から最も早期の発症3日で、鼻腔が陰性、唾液が陽性です。このデータからは、「発症前の感染者は鼻腔よりもむしろ唾液の方がウイルスが多いのではないか」との仮説が成り立ちます。この仮説が真であったら、「無症状では唾液の方が有効」となるわけです。可及的速やかに結果を出すべきです。
また、厚労省の通知では、「加えて、発症後 10 日目以降の唾液については、ウイルス量が低下することが知られており推奨されません。」とあります。
しかし、北大の文献本文では、「回復期には、唾液の方が鼻腔に比較して早くにウイルスが減少している。」「最近の文献では、鼻腔には死んだウイルスが溜まり、“擬陽性”となる。興味あることに、われわれの結果では、鼻腔に比較して唾液の方が迅速に陰性になる。口の中では死んだウイルスが唾液によって効果的に清掃されるようだ。コロナ感染症患者の回復確認には唾液の方が好ましい。」と記載されています。即ち、北大の文献では、「発症後10日以降は唾液の精度が落ちる」のではなく、「発症後10日以降は唾液の方が正しく回復状況を示している」と述べているのです。
この点でも、唾液PCRの利点を、厚労省は逆に「唾液PCRの弱点」として捉えているわけです。ジャーナリズムはなぜこの点に切り込まないのか、理解に苦しみます。