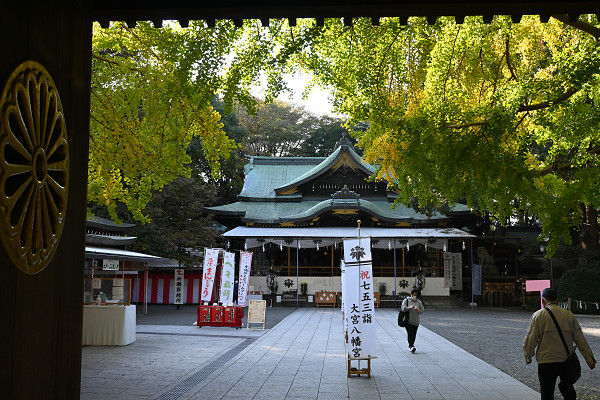久しぶりのサッカーネタです。
昨日の日本対ドイツ戦、前半を見る限り、実力での総合力は明らかにドイツが上でした。しかし終わってみたら、2対1で日本の勝利です。後半に交代で出場した選手が躍動しました。
日本1点目、三苫の切り返しからの南野へのパス、南野のシュートのこぼれ球を堂安がシュート・ゴール!も見事でした(動画)。
そして2点目です。ロングパスを受けた浅野がボールをトラップし、ドイツディフェンスとキーパーをかわしてゴールに突き刺しました(動画)。
私は「浅野の一世一代のトラップだった」とつぶやいていました。
今朝になって、私は「ベルカンプ」を思い出しました。ベルカンプの絶妙トラップからのゴールを見た記憶がある・・・。そこで、「ベルカンプ ワールドカップ トラップ」で検索してみました。ありました。
天才FWベルカンプ、誕生日に超絶トラップの伝説ゴール再脚光 「美しい」「最高の実況」
2019.05.11
『公開された映像は、98年フランスW杯準々決勝アルゼンチン戦で生まれた一撃だ。1-1と拮抗した展開で迎えた後半44分、DFフランク・デ・ブールが自陣から対角線上にロングボールを供給。これに反応したのがベルカンプだ。
相手ペナルティーエリアに走り込んだベルカンプは落下地点に右足を伸ばすと、足の甲に吸い付くような超絶トラップを披露。直後に相手DFロベルト・アジャラがボール奪取を狙ったなか、地面にボールが付くと同時に2タッチ目で完璧にボールを制御してアジャラをかわすと、右足アウトサイドで決勝ゴールを決めた。』
日本語での実況動画は「1998年ワールドカップ オランダvs アルゼンチン」にあります。
こちらでは「アーセナル・レジェンドがW杯で魅せた超人トラップ。芸術的タッチから生まれたオランダ代表伝説のゴール 2021年06月04日」と紹介されています。
「ベルカンプ」を「浅野」に、「フランク・デ・ブール」を「板倉」に書き換えたら、2022ワールドカップ日本対ドイツ戦の日本2点目になっちゃうじゃないですか。2タッチ目が異なりますが。
あのベルカンプのトラップ-シュート-ゴールは、「超絶」「超人」「伝説」と呼ばれているのですね。
私は、昨日の浅野のトラップは、98年フランスW杯準々決勝アルゼンチン戦でオランダのベルカンプが見せたトラップに匹敵する超絶トラップだ!、と言いたいです。
しかし残念なことに、試合後の浅野に対するインタビューでアナウンサーは「あのトラップが凄かったですね!」とは問いかけなかったです。
p.s. 12/24
あれからもうひと月ですね。
「サムライに勇気をもらった!」FIFA公式が浅野拓磨のドイツ戦逆転弾に再脚光で海外反響!「途轍もない衝撃だったな」【W杯】
サッカーダイジェストWeb編集部 2022年12月24日
【動画】何度でも観たい! FIFA公式が“1か月記念”で紹介した浅野のドイツ戦ゴールをチェック!
『現地12月23日、FIFA(国際サッカー連盟)の公式ツイッター&インスタグラムが日本代表のメモリアルシーンにスポットライトを当てた。「あれからちょうど1か月。タクマ・アサノが日本サッカーの歴史を作った」と綴り、ドイツ戦の逆転ゴールを動画で紹介している。』
『日本中が熱狂したあのドイツ戦(11月23日)から、早くも1か月が経った。FIFAの公式SNSには海外のサッカーファンから好意的な声が続々と寄せられ、「途轍もない衝撃だった!」「もうあれから1か月? 1週間じゃないのか」「あの試合で日本がお気に入りになったよ」「ファンタスティックの一語!」「サムライブルーに勇気をもらった!」など、枚挙に暇がないほどだ。
一方で、ドイツのファンからは「もう思い出させないでくれ」「悪夢が蘇った」「悲劇のすべてがこのゴールに凝縮されている」と、悲痛なコメントが寄せられている。』
私の周りでは、私1人が「一世一代のトラップだった」と騒いでいました。残念なことに、試合後の浅野に対するインタビューでアナウンサーは「あのトラップが凄かったですね!」とは問いかけなかったです。
しかし、サッカーの本場ヨーロッパでは強く印象に残っているのですね。
ただし、浅野が秀逸だったのはあの一撃だけでした。あれがなかったら、闘莉王の「ヘボ」指摘が定着していたことでしょう。
昨日の日本対ドイツ戦、前半を見る限り、実力での総合力は明らかにドイツが上でした。しかし終わってみたら、2対1で日本の勝利です。後半に交代で出場した選手が躍動しました。
日本1点目、三苫の切り返しからの南野へのパス、南野のシュートのこぼれ球を堂安がシュート・ゴール!も見事でした(動画)。
そして2点目です。ロングパスを受けた浅野がボールをトラップし、ドイツディフェンスとキーパーをかわしてゴールに突き刺しました(動画)。
私は「浅野の一世一代のトラップだった」とつぶやいていました。
今朝になって、私は「ベルカンプ」を思い出しました。ベルカンプの絶妙トラップからのゴールを見た記憶がある・・・。そこで、「ベルカンプ ワールドカップ トラップ」で検索してみました。ありました。
天才FWベルカンプ、誕生日に超絶トラップの伝説ゴール再脚光 「美しい」「最高の実況」
2019.05.11
『公開された映像は、98年フランスW杯準々決勝アルゼンチン戦で生まれた一撃だ。1-1と拮抗した展開で迎えた後半44分、DFフランク・デ・ブールが自陣から対角線上にロングボールを供給。これに反応したのがベルカンプだ。
相手ペナルティーエリアに走り込んだベルカンプは落下地点に右足を伸ばすと、足の甲に吸い付くような超絶トラップを披露。直後に相手DFロベルト・アジャラがボール奪取を狙ったなか、地面にボールが付くと同時に2タッチ目で完璧にボールを制御してアジャラをかわすと、右足アウトサイドで決勝ゴールを決めた。』
日本語での実況動画は「1998年ワールドカップ オランダvs アルゼンチン」にあります。
こちらでは「アーセナル・レジェンドがW杯で魅せた超人トラップ。芸術的タッチから生まれたオランダ代表伝説のゴール 2021年06月04日」と紹介されています。
「ベルカンプ」を「浅野」に、「フランク・デ・ブール」を「板倉」に書き換えたら、2022ワールドカップ日本対ドイツ戦の日本2点目になっちゃうじゃないですか。2タッチ目が異なりますが。
あのベルカンプのトラップ-シュート-ゴールは、「超絶」「超人」「伝説」と呼ばれているのですね。
私は、昨日の浅野のトラップは、98年フランスW杯準々決勝アルゼンチン戦でオランダのベルカンプが見せたトラップに匹敵する超絶トラップだ!、と言いたいです。
しかし残念なことに、試合後の浅野に対するインタビューでアナウンサーは「あのトラップが凄かったですね!」とは問いかけなかったです。
p.s. 12/24
あれからもうひと月ですね。
「サムライに勇気をもらった!」FIFA公式が浅野拓磨のドイツ戦逆転弾に再脚光で海外反響!「途轍もない衝撃だったな」【W杯】
サッカーダイジェストWeb編集部 2022年12月24日
【動画】何度でも観たい! FIFA公式が“1か月記念”で紹介した浅野のドイツ戦ゴールをチェック!
『現地12月23日、FIFA(国際サッカー連盟)の公式ツイッター&インスタグラムが日本代表のメモリアルシーンにスポットライトを当てた。「あれからちょうど1か月。タクマ・アサノが日本サッカーの歴史を作った」と綴り、ドイツ戦の逆転ゴールを動画で紹介している。』
『日本中が熱狂したあのドイツ戦(11月23日)から、早くも1か月が経った。FIFAの公式SNSには海外のサッカーファンから好意的な声が続々と寄せられ、「途轍もない衝撃だった!」「もうあれから1か月? 1週間じゃないのか」「あの試合で日本がお気に入りになったよ」「ファンタスティックの一語!」「サムライブルーに勇気をもらった!」など、枚挙に暇がないほどだ。
一方で、ドイツのファンからは「もう思い出させないでくれ」「悪夢が蘇った」「悲劇のすべてがこのゴールに凝縮されている」と、悲痛なコメントが寄せられている。』
私の周りでは、私1人が「一世一代のトラップだった」と騒いでいました。残念なことに、試合後の浅野に対するインタビューでアナウンサーは「あのトラップが凄かったですね!」とは問いかけなかったです。
しかし、サッカーの本場ヨーロッパでは強く印象に残っているのですね。
ただし、浅野が秀逸だったのはあの一撃だけでした。あれがなかったら、闘莉王の「ヘボ」指摘が定着していたことでしょう。