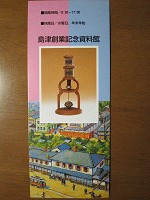特許庁は30日に産業構造審議会(経済産業相の諮問会議)の特許制度小委員会を開き、来年の通常国会への提出を目指す特許法改正に向けた基本方針について、有識者委員からおおむね了承を得たとのことですが、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会のサイトにはまだ情報が上がっていないようです。
今日はその話ではなく、ロシアについてです。
今年8月発行の本です。
先日のメドヴェージェフ・ロシア大統領の北方領土訪問の衝撃があったことから、タイムリーな本になりました。
著者の武田善憲氏は、現役の外務官僚で、1973年生まれ、本の後付では「外務省軍縮不拡散・科学部軍備管理軍縮課課長補佐」とあります。
ロシアを専門とする外務官僚として、ロシアを分析することを専門としているようです。専門家として知り得た事実のうち、外交秘密に属しない部分をピックアップして新書にしたのでしょう。
プーチンが大統領になった当初は、そのこわもての容姿とKGB出身という経歴やチェチェン戦争を主導したという事実から、ロシアは恐い国になるのではないかとの先入観を抱いていました。また、エネルギー価格の高騰で一時は成長著しかったものの、経済危機後は成長も鈍化しているのではないかと勝手に想像していました。
しかしこの本を読んでみると、たしかにエネルギー価格高騰を追い風にしてはいるのですが、プーチンが大統領であった8年間に、ロシアという国はすっかり変貌し、豊かで成長力に富み、世界情勢に影響を与える大国になっているようでした。
それは、プーチンの風貌と経歴から想像されるような恐怖国家ではありません。
この本では、ロシアが進もうとしている道を見出し、その背後に存在するゲームのルールを読み解くという方法を使っています。著者が描き出すロシアのゲームのルールとはどんなものでしょうか。ここでは箇条書きでピックアップしてみます。
○ ロシア政治に関与するアクターに課せられた不文律は、政治的野心を抱かず、ただ実務的に職務をこなすということである。
○ 外交では、米国一極主義を排し、自らの対外政策を「多極主義」というゲームのルールに従い、中国及びインドとの協力の強化や、これまでロシアとの利害関係が薄いと見られていた地域への積極的なアプローチを行い、国際社会での存在感を高めている。
○ 経済分野では「正しく納税せよ」という基本ルールに従いながら、国家権力側の意図を読み取りながら経済活動を進めることが求められる。「納税し、合法的にビジネスを行い、政治的野心を持たなければ自由に活動して構わない」
○ エネルギー分野、特に化石燃料資源は「戦略的分野」として特別な扱いを受け、「資源は国家のもの」というルールが機能する。
○ ロシア国家の一体性、国民性の統合を目指す上での軸となるゲームのルールは、「優先的国家プロジェクト」と宗教(ロシア正教)である。
プーチン大統領(当時)は、憲法が定めた制度が大統領としての行動原理であること、ルールや手続きに沿った統治を心がけ、そして実践していることを繰り返しアピールする大統領でした。
ロシア憲法は大統領の三選を禁じています。2期目末期の大統領後継問題において、プーチンは憲法改正という荒療治を行わず、大統領職をメドヴェージェフに移譲しました。そして、ロシア国民との関係において「発言にぶれのない、首尾一貫したリーダー」というイメージを植え付けます。
プーチンは「国民との対話」で優れた能力を発揮しました。2~3時間にわたり、あらゆる政治課題についてカンニングペーパーを見ることなく答え続けることができます。G8の首脳の中でこのレベルのパフォーマンスをできるのはプーチン一人であった、としています。
プーチン大統領時代は、プーチンが一人だけで最終決定を行っており、メドヴェージェフ大統領時代は2人だけで最終決定を行っています。そして二人ともきわめて口の堅い男たちなので、側近を通じてロシアの政策決定過程を分析することは不可能となりました。
外交においてロシアは多極主義を目指しています。
イラク戦争に際しては、ロシアは安保理においてアメリカのやり方に対峙したわけですが、その後のイラク戦争の推移の結果、ロシアは賭に勝ったことになります。勝利の報酬は、国際政治におけるロシアの地位の向上でした。
プーチンの二期目において、プーチンは成長著しいロシアの強いリーダーとして行く先々で厚遇されました。
グルジアとの武力衝突では、日本の新聞紙上ではロシアを非難する論調ではありましたが、現時点で状況はロシアにとって決して不利ではなく、最近の展開を見る限り、時間はここでもロシアに味方しているといいます。
サハリン2
ソ連政府による国際入札の結果、1994年にロイヤル・ダッチ・シェルと三井物産、三菱商事の三者がロシア政府と協定を締結しました。出資比率は英蘭シェルが55%、三井物産25%、三菱商事20%です。ところが2006年9月、ロシア政府は環境アセスメントの不備を指摘し、突然開発の中止命令を発出しました。2007年4月、ロシア・天然資源省はサハリンエナジーの環境是正計画を承認。ロシアガスプロムがサハリンエナジーの株式の50%+1株を取得し、英蘭シェルが55%から27.5%-1株に、三井物産25%から12.5%、三菱商事20%から10%に減少となりました。
著者の武田氏はさまざまな人にサハリン2についてヒアリングしましたが、聞けば聞くほど何が真実だったのかわからなくなるということです。
『そこで本書では結果だけに注目してあえて単純化し、「外国企業が100%の権益を占める」というプロジェクトをロシアから消し、新しいゲームのルールを確立するための一件だったと整理することにする。』「ロシア領内にある限りはロシア企業が最低でも50%+1株を獲得するべきである」というルールです。
さて、本書を通じて「ロシアと日本外交」についての指針が欲しかったのですが、残念ながらそのような観点での論述がありません。やはり現職の外務官僚として、その点は刊行物で公開することのできない領域だったのでしょうか。
北方領土問題と日本外交でも書いたように、日本の官邸と外務省による対ロシア外交は瀕死の状態にあるように見えます。そんな中、本書の著者である武田善憲氏が力を発揮することは可能なのでしょうか。現在の役職を見る限り、対ロシア外交の第一線にいらっしゃるわけではなさそうです。
今日はその話ではなく、ロシアについてです。
 | ロシアの論理―復活した大国は何を目指すか (中公新書)武田 善憲中央公論新社このアイテムの詳細を見る |
先日のメドヴェージェフ・ロシア大統領の北方領土訪問の衝撃があったことから、タイムリーな本になりました。
著者の武田善憲氏は、現役の外務官僚で、1973年生まれ、本の後付では「外務省軍縮不拡散・科学部軍備管理軍縮課課長補佐」とあります。
ロシアを専門とする外務官僚として、ロシアを分析することを専門としているようです。専門家として知り得た事実のうち、外交秘密に属しない部分をピックアップして新書にしたのでしょう。
プーチンが大統領になった当初は、そのこわもての容姿とKGB出身という経歴やチェチェン戦争を主導したという事実から、ロシアは恐い国になるのではないかとの先入観を抱いていました。また、エネルギー価格の高騰で一時は成長著しかったものの、経済危機後は成長も鈍化しているのではないかと勝手に想像していました。
しかしこの本を読んでみると、たしかにエネルギー価格高騰を追い風にしてはいるのですが、プーチンが大統領であった8年間に、ロシアという国はすっかり変貌し、豊かで成長力に富み、世界情勢に影響を与える大国になっているようでした。
それは、プーチンの風貌と経歴から想像されるような恐怖国家ではありません。
この本では、ロシアが進もうとしている道を見出し、その背後に存在するゲームのルールを読み解くという方法を使っています。著者が描き出すロシアのゲームのルールとはどんなものでしょうか。ここでは箇条書きでピックアップしてみます。
○ ロシア政治に関与するアクターに課せられた不文律は、政治的野心を抱かず、ただ実務的に職務をこなすということである。
○ 外交では、米国一極主義を排し、自らの対外政策を「多極主義」というゲームのルールに従い、中国及びインドとの協力の強化や、これまでロシアとの利害関係が薄いと見られていた地域への積極的なアプローチを行い、国際社会での存在感を高めている。
○ 経済分野では「正しく納税せよ」という基本ルールに従いながら、国家権力側の意図を読み取りながら経済活動を進めることが求められる。「納税し、合法的にビジネスを行い、政治的野心を持たなければ自由に活動して構わない」
○ エネルギー分野、特に化石燃料資源は「戦略的分野」として特別な扱いを受け、「資源は国家のもの」というルールが機能する。
○ ロシア国家の一体性、国民性の統合を目指す上での軸となるゲームのルールは、「優先的国家プロジェクト」と宗教(ロシア正教)である。
プーチン大統領(当時)は、憲法が定めた制度が大統領としての行動原理であること、ルールや手続きに沿った統治を心がけ、そして実践していることを繰り返しアピールする大統領でした。
ロシア憲法は大統領の三選を禁じています。2期目末期の大統領後継問題において、プーチンは憲法改正という荒療治を行わず、大統領職をメドヴェージェフに移譲しました。そして、ロシア国民との関係において「発言にぶれのない、首尾一貫したリーダー」というイメージを植え付けます。
プーチンは「国民との対話」で優れた能力を発揮しました。2~3時間にわたり、あらゆる政治課題についてカンニングペーパーを見ることなく答え続けることができます。G8の首脳の中でこのレベルのパフォーマンスをできるのはプーチン一人であった、としています。
プーチン大統領時代は、プーチンが一人だけで最終決定を行っており、メドヴェージェフ大統領時代は2人だけで最終決定を行っています。そして二人ともきわめて口の堅い男たちなので、側近を通じてロシアの政策決定過程を分析することは不可能となりました。
外交においてロシアは多極主義を目指しています。
イラク戦争に際しては、ロシアは安保理においてアメリカのやり方に対峙したわけですが、その後のイラク戦争の推移の結果、ロシアは賭に勝ったことになります。勝利の報酬は、国際政治におけるロシアの地位の向上でした。
プーチンの二期目において、プーチンは成長著しいロシアの強いリーダーとして行く先々で厚遇されました。
グルジアとの武力衝突では、日本の新聞紙上ではロシアを非難する論調ではありましたが、現時点で状況はロシアにとって決して不利ではなく、最近の展開を見る限り、時間はここでもロシアに味方しているといいます。
サハリン2
ソ連政府による国際入札の結果、1994年にロイヤル・ダッチ・シェルと三井物産、三菱商事の三者がロシア政府と協定を締結しました。出資比率は英蘭シェルが55%、三井物産25%、三菱商事20%です。ところが2006年9月、ロシア政府は環境アセスメントの不備を指摘し、突然開発の中止命令を発出しました。2007年4月、ロシア・天然資源省はサハリンエナジーの環境是正計画を承認。ロシアガスプロムがサハリンエナジーの株式の50%+1株を取得し、英蘭シェルが55%から27.5%-1株に、三井物産25%から12.5%、三菱商事20%から10%に減少となりました。
著者の武田氏はさまざまな人にサハリン2についてヒアリングしましたが、聞けば聞くほど何が真実だったのかわからなくなるということです。
『そこで本書では結果だけに注目してあえて単純化し、「外国企業が100%の権益を占める」というプロジェクトをロシアから消し、新しいゲームのルールを確立するための一件だったと整理することにする。』「ロシア領内にある限りはロシア企業が最低でも50%+1株を獲得するべきである」というルールです。
さて、本書を通じて「ロシアと日本外交」についての指針が欲しかったのですが、残念ながらそのような観点での論述がありません。やはり現職の外務官僚として、その点は刊行物で公開することのできない領域だったのでしょうか。
北方領土問題と日本外交でも書いたように、日本の官邸と外務省による対ロシア外交は瀕死の状態にあるように見えます。そんな中、本書の著者である武田善憲氏が力を発揮することは可能なのでしょうか。現在の役職を見る限り、対ロシア外交の第一線にいらっしゃるわけではなさそうです。