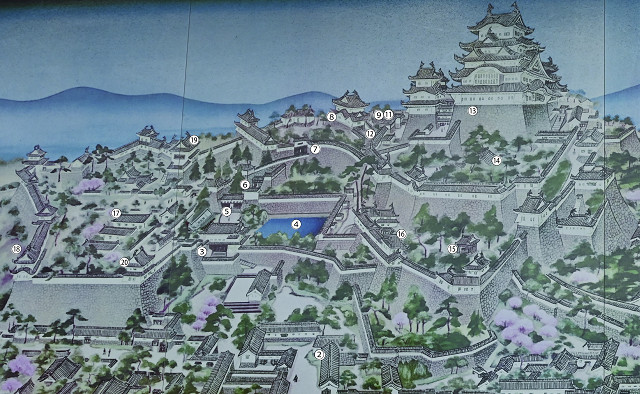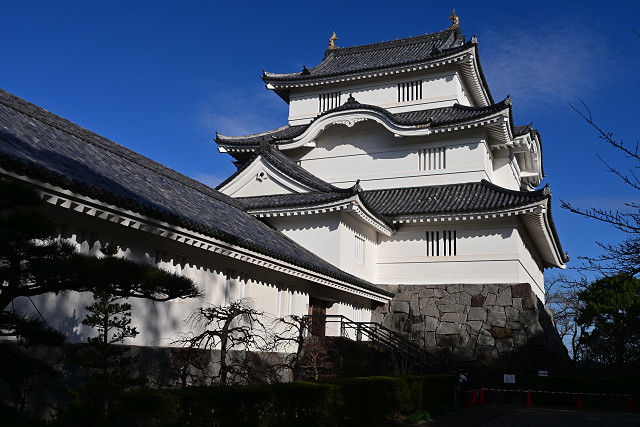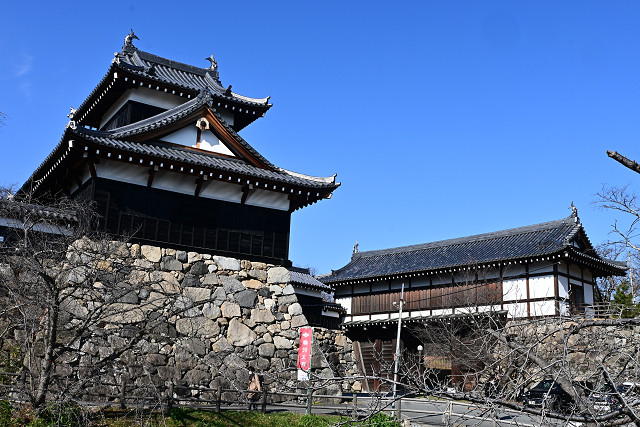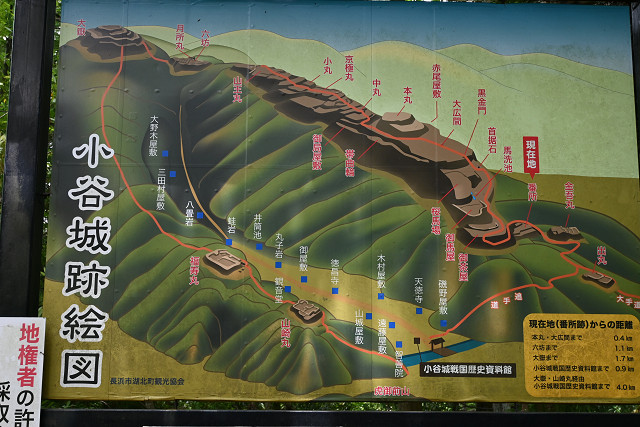ジェイソン・ファゴン著「コードブレイカー――エリザベス・フリードマンと暗号解読の秘められし歴史」

この本の主役は、エリザベス・スミス・フリードマン(1892-1980)と、その夫のウィリアム・フリードマンです。
第2次大戦の開始当時から、アメリカは、交戦国であるドイツの外交暗号(エニグマ)を解読し、日本の外交暗号(パープル)を解読していました。一方、ドイツも日本も、アメリカの暗号を解読できておらず、また自分たちの暗号がアメリカに解読されていることに気づきませんでした。
アメリカにおける、エニグマの解読とパープルの解読に最も貢献したのが、2人の個人、エルザベス・スミス・フリードマンとウィリアム・フリードマンであった、というのです。その詳細が今回の書籍に克明に記されています。
このカップルは、夫と妻の二人一組で、言うなれば家族経営の暗号解読局として機能するようになっていきました。コンピュータが存在しない時代、二人は鉛筆と紙、そして自分の頭を頼りにしていました。
エリザベスとウィリアムのフリードマン夫妻は30年間にわたり、子ども二人を育てながら、二つの大戦時にやりとりされた何千もの通信文を解読し、密輸ネットワークや、ギャング、組織犯罪、外国の軍隊、ファシズムについて秘密のほころびを探り当てて突破しました。二人はまた、暗号学(クリプトロジー)なる新たな技術を考案し、暗号作製の手法を一変させました。夫妻の慧眼から得られた成果は今日でも、巨大な政府機関から、インターネット上の個人のごく小さな活動に至るありとあらゆることの根底に潜んでいます。
夫の方のウィリアム・フリードマンは、インテリジェンス史研究家から尊敬を集めるようになりました。国家安全保障庁(NSA)の父としても広く知られています。
一方、妻のエリザベスの知名度は、優れた才能を持ち多大な貢献をしたにもかかわらず格段に低いです。エリザベスが行った仕事が暗号解読に関するものであり、守秘義務を負って公表することができなかったこと、そしてFBIのJ・エドガー・フーバーが、エリザベスの貢献を横取りしてFBIの成果に見せかけてしまったためです。
1976年、エリザベスはNSAから派遣されたインタビュアー、ヴァージニア・ヴァラキのインタビューを受けました。エリザベスが84歳のときです。これが、エリザベスの業績が公に広く知られるきっかけになったようです。
エリザベスの保守的な父親は、エリザベスの大学進学に反対していました。エリザベスは学費は自分で払うと宣言して大学に進学しました。
1915年当時の教育を受けたアメリカ人女性ができる仕事といえば、せいぜい高校や小中学校で教えるくらいのものでした。女は、教師をして、子どもを産み、退職して、人生を終えるものでした。しかしエリザベスは、リスクを伴うものに情熱がかき立てられます。
一度は郡立高校の校長代理として赴任しますが退職し、両親の家にも長居できず、荷物をまとめてシカゴ行きの列車に乗り込みました。頭を使うことが必要な仕事を求めましたが、シカゴの職業紹介所職員からはそのような仕事の口はありませんとの答が返ってきました。
シカゴのニューベリー図書館に所蔵された、シェイクスピアのファースト・フォリオという稀覯本に彼女は関心を抱いていました。この図書館に出かけたことが、フェイビアンに出会うきっかけでした。
フェイビアンは大金持ちの事業家で、リバーバンクに研究所を開設していました。その研究所では、多くのテーマの研究が行われており、ミセス・ギャラップが、シェイクスピアの戯曲の作者はじつは哲学者のフランシス・ベーコンであり、その証拠のメッセージが戯曲の中に埋め込まれている、という仮説で研究を進めていました。ミセス・ギャラップは若いエネルギーと鋭い目をもった助手を求めていました。23歳のエリザベス・スミスはその助手の仕事に就きました。
ギャラップ夫人によると、ニューベリー図書館が所蔵するシェイクスピアのファースト・フォリオの文字の形の中に、秘められたメッセージが埋め込まれており、ギャラップ夫人はその秘密をすでに解き明かしているといいます。エリザベスの仕事は、ギャラップ夫人の手法を用いて既存の研究結果を再現することです。
ウィリアム・フリードマンは若い遺伝学者であり、リバーバンクのフリードマンの研究所に住み着いて研究をしていました。ギャラップ夫人の仕事も手伝っていました。
ギャラップ夫人の仕事、すなわちシェイクスピアの戯曲のなかにベーコンが仕組んだメッセージを解き明かそうとする仕事は、暗号解読と同様のスキルを必要とします。そのため、エリザベスとウィリアムは、この仕事を通じて暗号解読に必要なスキルを自然と身につけていきました。
第一次大戦の直前、通信手段として無線が用いられるようになりました。無線だと敵味方関係なく受信できるので、通信文の暗号化が必須になります。ところがアメリカには暗号解読家が数人しかおらず、そのうちの二人がエリザベスとウィリアムでした。
戦争省(現在の国防総省)は、モーボーン大佐をリバーバンクに派遣しました。モーボーンは暗号解読の実務経験がありました。モーボーンは、エリザベスとウィリアムのなかに才能の輝きを見て取りました。実際に敵国の暗号文の解読を依頼したところ、見事に解読に成功しました。その後、第一次大戦アメリカ参戦後の八カ月間、ウィリアムとエリザベスをはじめとするリバーバンクのチームが、アメリカ政府のあらゆる機関の暗号解読を行いました。暗号解読は、紙と鉛筆と二人の頭脳と、そして二人の連係プレイによってなし遂げられました。
エリザベスとウィリアムは、ストレート・アルファベット、ダイレクト・アルファベット、逆アルファベット、多アルファベット、混合アルファベットなど、数種類の換字式サイファを識別し、解読できるようになりました。書籍サイファを、その本自体が手許になくても解読できる一般的なテクニックを開発しました。二人は「柔軟な思考」「直感力」と表現しました。二人にとって直感とは、努力の末に獲得した体内コンパスのようなものでした。
その過程で得られた暗号解読に関する新たな知見は、リバーバンクから出版され、今日これらは現代暗号学の礎石と評価されています。
戦時中のある日、イギリス陸軍が開発した小型の手動式暗号機で暗号化された通信文の解読を試みました。イギリスは、この装置は解読不可能と結論づけていましたが、アメリカ側が念のために二人に解読を依頼してみたのです。二人は、絶妙の連係プレイでこの暗号を解読してしまいました。
ウィリアムはユダヤ人であり、ユダヤ教徒以外との結婚は家族全員が反対します。エリザベスはクエーカー教徒の一家でした。その障害を乗り越え、1917年、二人は結婚しました。フェイビアンの研究所にある風車が、二人の新居でした。
ウィリアムは陸軍への入隊を希望し、フェイビアンはなかなか許可しませんでしたが、戦争が終わったら戻ってくるという条件で陸軍入隊許可を与えました。そしてエリザベスを残して、フランスの戦地に赴任しました。
戦争が終結しました。
二人はリバーバンクから決別しようとしますが、フェイビアンの妨害でうまくいきません。やっとのことで逃げだし、ワシントンに向かいました。
第一次大戦後、各国の暗号の世界では、暗号文を作成する機械の必要に迫られていました。高速で、使いやすく、格段に高い安全性が確保されているという機械です。フリードマン夫妻は、ワシントンに到着するやこうした事態に放り込まれ、1921年、二人は政府機関での勤務を開始しました。
アメリカの政府部内で暗号解読を行う部局は3つ、職員は合計で50名以下でした。規模が最大なのは元陸軍中尉のハーバート・ヤードレーが率いる暗号局、その他は海軍と陸軍所属でした。その陸軍の暗号部門でフリードマン夫妻は勤務を始めました。
ウィリアムは、2機の暗号作成機械で生成した暗号の解読に成功しました。この時点では、紙と鉛筆とひらめきだけで機械を破ることがまだ可能でした。ただし、徹底した注意力と集中力を働かせる必要がありました。
ウィリアムは、当時市場で販売されていたエニグマ(ドイツ製の暗号機)の解析にも取り組んだことがありました。このときは本気で解読しようとはしていませんでした。
エリザベスは海軍の要請で勤務を始めましたが、5ヶ月勤務後に妊娠のために職を離れました。
1925年、エリザベスは沿岸警備隊の訪問を受けました。禁酒法の時代、沿岸警備隊のチャールズ・ルートは、海岸を経由して酒を密輸する船を捕まえる任を負っていました。エリザベスは、期間限定で在宅勤務なら、ということで受けます。
沿岸警備隊は財務省所管でした。財務省は法執行機関を沿岸警備隊を含めて六つ、抱えており、財務省捜査官はTメンと呼ばれていました。アル・カポネの逮捕、リンドバーグの愛児誘拐事件の犯人逮捕は、いずれもTメンによるものでした。
エリザベスは、沿岸警備隊が傍受した犯罪組織間の暗号通信文を次々に解読していきました。エリザベスは暗号通信文の解読のみならず、広範で包括的なシステムの構築に取りかかりました。エリザベスは、財務省でただひとりの上級暗号解析管、すなわち暗号解読法を知っている唯一の人間だったため、財務省内の各法執行機関に所属するTメンたちを結びつける役割を果たし始めました。
沿岸警備隊では、エリザベス一人が暗号解読を担い、3年間で酒密輸にかかわる通信文を12000通解読しました。限界を覚えたエリザベスは、暗号解読班の設置を提案しました。提案が認められ、下級暗号解読者3名と速記者2名、それにオフィスが与えられました。アメリカ史上唯一の女性が率いる暗号解読班となりました。3人の新人が暗号解読のスキルを身につけました。1932年にF・D・ルーズベルトが大統領に就任したときには、エリザベス率いるチームは、アメリカにおける掛け値なしに最高の無線インテリジェンス組織に成長していました。ここで獲得したスキルに基づき、エリザベスはのちに、ナチ・スパイの極秘ネットワークを打ち破る立役者となります。
ニューオーリンズでの刑事裁判でエリザベスが証人として公開の裁判所で証言することとなり、エリザベスは一躍時の人となりました。
このころウィリアムは、その後10年にわたって、陸軍で日本の外交暗号の解読に携わることになりました。1930年にウィリアムは陸軍の新たな暗号解読班を立ち上げ、これがのちに国家安全保障庁の中核をなすことになります。
ウィリアムはこの組織で、日本の外交暗号解読を目指すとともに、自分たちでも暗号作成機を創り出しました。
1930年ころから日本が使い始めた機械は、Angooki Taipu Aと呼ばれ、アメリカでは「レッド」のニックネームで呼ばれていました。1938年、日本はレッドを大幅に改良した高度な暗号機 Angooki Taipu Bに置き換えました。アメリカでは「パープル」と名付けました。
またウィリアムのチームは、M-134、さらに改良したSIGABAと呼ばれる暗号機を創出しました。アメリカ陸軍と海軍は第二次世界大戦中、1万台以上のシガバをあらゆる戦域に設置しました。ドイツ、イタリア、日本のいずれも、最後まで解読できませんでした。
ウィリアムの仕事は極秘であり、家に帰っても同業者である妻にすら話すことができません。ウィリアムは夜に帰宅するとほとんど何もしゃべらない生活となりました。ウィリアムの神経が病んでいきます。
ナチスドイツがボーランドに侵攻し、第2次大戦が勃発しました。
大西洋を隔てたアメリカは安全なように思われましたが、もしナチが南米を支配したら、アメリカも安全ではなくなります。
ヒトラーは、南米に工作員を送り込みました。携帯式無線機をもった新人工作員が、Uボートで海岸にたどり着いたり、飛行機から落下傘で降下したりして目的地に潜り込みました。
エリザベス・フリードマンが1940年から1945年にかけて行っていたことについては、厳重な機密指定がされ、エリザベスの死後にようやく封を解かれました。
エリザベスのチームは、財務省から依頼された暗号を解読するうちに、未登録の無線局から発信された謎めいた暗号文の存在に気づきました。暗号を解読すると、平文はドイツ語であり、位置測定からすると発信元はメキシコ、南米、アメリカにある未確認の無線局のようです。まもなく、これらの無線局はナチのスパイが設置したものだとわかりました。
エリザベスと彼女のチームは、紙と鉛筆を用いて直感と経験をもとに、この暗号を解読していくのです。著書では、その過程が詳細に示されています。
エリザベスの基本的な解読スタイルは、紙と鉛筆で試行錯誤を繰り返し、推論を立ててそれを試します。エリザベスはこれまでの25年間、何万通もの通信文を手掛ける中で、ありとあらゆる種類の暗号を解いてきたので、近道の見つけ方、つまりは文中でのパターンの見分け方を心得ていたからです。エリザベスは一種の人間コンピュータでした。
1940年、ドイツのエニグマ機で作成された暗号文に始めて遭遇したとき、エリザベスはたいして怖じ気づきはしませんでした。
エニグマ機で暗号を作成するに際し、マシンのロータの開始位置を頻繁に変更することが必要です。しかしある無線局では、送信者がまちがって同じ開始位置を使ってすべての通信文を送っていました。そのため、数多くの暗号文を縦に重ねることで、暗号を解く鍵を見つけたのです。そしてチームは、暗号の特徴がエニグマ機に似ていることに気づきました。保有していた古いエニグマの商用機で解析を始めました。そして、見たこともないエニグマ機にある3枚のロータすべての配線をなんとか解明して見せました。
ウィリアムが率いる陸軍暗号解読班では、日本の外交暗号機パープルが生成する暗号文の解読に努めていました。
『1940年9月のある日、ウィリアム・フリードマン率いる陸軍暗号解読班がいる窓のない丸天井の部屋で、所属する2人の女性暗号解読者のうちの1人、ジュネビーブ・グローチャンが自分のデスクの前に立ち、なにかを発見したかも知れません、と男たちに話しかけた。
・・・
このときグローチャンは、これまで誰も見つけられなかった2つのパターンが見えてきた、と感じていた。』
男たちはデスクのまわりに集まってきます。
『「これだ!」とローレットが叫ぶ。「これだよ! 探していたものをジーンが見つけてくれた!」』
男たちはこの発見に興奮して笑いながら飛び跳ねていましたが、ウィリアム1人はほとんど悲しげに見えました。このときすでに、ウィリアムは精神的に病んでいたのです。
グローチャンの発見から5日後、1通の通信文が始めて完全に解読されました。
『今日、暗号史の研究者は、苦難の末に成功をものにしたという点では、パープルの突破は、アラン・チューリングのひらめきによりドイツの暗号エニグマを打ち破った功績と同等の価値があるととらえている。』
ウィリアムたちは、日本の通信文を読み解くためのパープル模造機の作製に取りかかり、完成させました。
パープル暗号を解読した解読文のうちで最高機密扱いされるものをマジックと呼ぶようになりました。日本が真珠湾攻撃を敢行したとき、在米日本大使が米大統領に手渡すべき最後通牒を、その前の日の晩にルーズベルト大統領がマジックとして入手し読んでいたことは有名です。日本は戦争終結に至るまで、パープル暗号が敵方に解読されていることに全く気づきませんでした。
以下次号

この本の主役は、エリザベス・スミス・フリードマン(1892-1980)と、その夫のウィリアム・フリードマンです。
第2次大戦の開始当時から、アメリカは、交戦国であるドイツの外交暗号(エニグマ)を解読し、日本の外交暗号(パープル)を解読していました。一方、ドイツも日本も、アメリカの暗号を解読できておらず、また自分たちの暗号がアメリカに解読されていることに気づきませんでした。
アメリカにおける、エニグマの解読とパープルの解読に最も貢献したのが、2人の個人、エルザベス・スミス・フリードマンとウィリアム・フリードマンであった、というのです。その詳細が今回の書籍に克明に記されています。
このカップルは、夫と妻の二人一組で、言うなれば家族経営の暗号解読局として機能するようになっていきました。コンピュータが存在しない時代、二人は鉛筆と紙、そして自分の頭を頼りにしていました。
エリザベスとウィリアムのフリードマン夫妻は30年間にわたり、子ども二人を育てながら、二つの大戦時にやりとりされた何千もの通信文を解読し、密輸ネットワークや、ギャング、組織犯罪、外国の軍隊、ファシズムについて秘密のほころびを探り当てて突破しました。二人はまた、暗号学(クリプトロジー)なる新たな技術を考案し、暗号作製の手法を一変させました。夫妻の慧眼から得られた成果は今日でも、巨大な政府機関から、インターネット上の個人のごく小さな活動に至るありとあらゆることの根底に潜んでいます。
夫の方のウィリアム・フリードマンは、インテリジェンス史研究家から尊敬を集めるようになりました。国家安全保障庁(NSA)の父としても広く知られています。
一方、妻のエリザベスの知名度は、優れた才能を持ち多大な貢献をしたにもかかわらず格段に低いです。エリザベスが行った仕事が暗号解読に関するものであり、守秘義務を負って公表することができなかったこと、そしてFBIのJ・エドガー・フーバーが、エリザベスの貢献を横取りしてFBIの成果に見せかけてしまったためです。
1976年、エリザベスはNSAから派遣されたインタビュアー、ヴァージニア・ヴァラキのインタビューを受けました。エリザベスが84歳のときです。これが、エリザベスの業績が公に広く知られるきっかけになったようです。
エリザベスの保守的な父親は、エリザベスの大学進学に反対していました。エリザベスは学費は自分で払うと宣言して大学に進学しました。
1915年当時の教育を受けたアメリカ人女性ができる仕事といえば、せいぜい高校や小中学校で教えるくらいのものでした。女は、教師をして、子どもを産み、退職して、人生を終えるものでした。しかしエリザベスは、リスクを伴うものに情熱がかき立てられます。
一度は郡立高校の校長代理として赴任しますが退職し、両親の家にも長居できず、荷物をまとめてシカゴ行きの列車に乗り込みました。頭を使うことが必要な仕事を求めましたが、シカゴの職業紹介所職員からはそのような仕事の口はありませんとの答が返ってきました。
シカゴのニューベリー図書館に所蔵された、シェイクスピアのファースト・フォリオという稀覯本に彼女は関心を抱いていました。この図書館に出かけたことが、フェイビアンに出会うきっかけでした。
フェイビアンは大金持ちの事業家で、リバーバンクに研究所を開設していました。その研究所では、多くのテーマの研究が行われており、ミセス・ギャラップが、シェイクスピアの戯曲の作者はじつは哲学者のフランシス・ベーコンであり、その証拠のメッセージが戯曲の中に埋め込まれている、という仮説で研究を進めていました。ミセス・ギャラップは若いエネルギーと鋭い目をもった助手を求めていました。23歳のエリザベス・スミスはその助手の仕事に就きました。
ギャラップ夫人によると、ニューベリー図書館が所蔵するシェイクスピアのファースト・フォリオの文字の形の中に、秘められたメッセージが埋め込まれており、ギャラップ夫人はその秘密をすでに解き明かしているといいます。エリザベスの仕事は、ギャラップ夫人の手法を用いて既存の研究結果を再現することです。
ウィリアム・フリードマンは若い遺伝学者であり、リバーバンクのフリードマンの研究所に住み着いて研究をしていました。ギャラップ夫人の仕事も手伝っていました。
ギャラップ夫人の仕事、すなわちシェイクスピアの戯曲のなかにベーコンが仕組んだメッセージを解き明かそうとする仕事は、暗号解読と同様のスキルを必要とします。そのため、エリザベスとウィリアムは、この仕事を通じて暗号解読に必要なスキルを自然と身につけていきました。
第一次大戦の直前、通信手段として無線が用いられるようになりました。無線だと敵味方関係なく受信できるので、通信文の暗号化が必須になります。ところがアメリカには暗号解読家が数人しかおらず、そのうちの二人がエリザベスとウィリアムでした。
戦争省(現在の国防総省)は、モーボーン大佐をリバーバンクに派遣しました。モーボーンは暗号解読の実務経験がありました。モーボーンは、エリザベスとウィリアムのなかに才能の輝きを見て取りました。実際に敵国の暗号文の解読を依頼したところ、見事に解読に成功しました。その後、第一次大戦アメリカ参戦後の八カ月間、ウィリアムとエリザベスをはじめとするリバーバンクのチームが、アメリカ政府のあらゆる機関の暗号解読を行いました。暗号解読は、紙と鉛筆と二人の頭脳と、そして二人の連係プレイによってなし遂げられました。
エリザベスとウィリアムは、ストレート・アルファベット、ダイレクト・アルファベット、逆アルファベット、多アルファベット、混合アルファベットなど、数種類の換字式サイファを識別し、解読できるようになりました。書籍サイファを、その本自体が手許になくても解読できる一般的なテクニックを開発しました。二人は「柔軟な思考」「直感力」と表現しました。二人にとって直感とは、努力の末に獲得した体内コンパスのようなものでした。
その過程で得られた暗号解読に関する新たな知見は、リバーバンクから出版され、今日これらは現代暗号学の礎石と評価されています。
戦時中のある日、イギリス陸軍が開発した小型の手動式暗号機で暗号化された通信文の解読を試みました。イギリスは、この装置は解読不可能と結論づけていましたが、アメリカ側が念のために二人に解読を依頼してみたのです。二人は、絶妙の連係プレイでこの暗号を解読してしまいました。
ウィリアムはユダヤ人であり、ユダヤ教徒以外との結婚は家族全員が反対します。エリザベスはクエーカー教徒の一家でした。その障害を乗り越え、1917年、二人は結婚しました。フェイビアンの研究所にある風車が、二人の新居でした。
ウィリアムは陸軍への入隊を希望し、フェイビアンはなかなか許可しませんでしたが、戦争が終わったら戻ってくるという条件で陸軍入隊許可を与えました。そしてエリザベスを残して、フランスの戦地に赴任しました。
戦争が終結しました。
二人はリバーバンクから決別しようとしますが、フェイビアンの妨害でうまくいきません。やっとのことで逃げだし、ワシントンに向かいました。
第一次大戦後、各国の暗号の世界では、暗号文を作成する機械の必要に迫られていました。高速で、使いやすく、格段に高い安全性が確保されているという機械です。フリードマン夫妻は、ワシントンに到着するやこうした事態に放り込まれ、1921年、二人は政府機関での勤務を開始しました。
アメリカの政府部内で暗号解読を行う部局は3つ、職員は合計で50名以下でした。規模が最大なのは元陸軍中尉のハーバート・ヤードレーが率いる暗号局、その他は海軍と陸軍所属でした。その陸軍の暗号部門でフリードマン夫妻は勤務を始めました。
ウィリアムは、2機の暗号作成機械で生成した暗号の解読に成功しました。この時点では、紙と鉛筆とひらめきだけで機械を破ることがまだ可能でした。ただし、徹底した注意力と集中力を働かせる必要がありました。
ウィリアムは、当時市場で販売されていたエニグマ(ドイツ製の暗号機)の解析にも取り組んだことがありました。このときは本気で解読しようとはしていませんでした。
エリザベスは海軍の要請で勤務を始めましたが、5ヶ月勤務後に妊娠のために職を離れました。
1925年、エリザベスは沿岸警備隊の訪問を受けました。禁酒法の時代、沿岸警備隊のチャールズ・ルートは、海岸を経由して酒を密輸する船を捕まえる任を負っていました。エリザベスは、期間限定で在宅勤務なら、ということで受けます。
沿岸警備隊は財務省所管でした。財務省は法執行機関を沿岸警備隊を含めて六つ、抱えており、財務省捜査官はTメンと呼ばれていました。アル・カポネの逮捕、リンドバーグの愛児誘拐事件の犯人逮捕は、いずれもTメンによるものでした。
エリザベスは、沿岸警備隊が傍受した犯罪組織間の暗号通信文を次々に解読していきました。エリザベスは暗号通信文の解読のみならず、広範で包括的なシステムの構築に取りかかりました。エリザベスは、財務省でただひとりの上級暗号解析管、すなわち暗号解読法を知っている唯一の人間だったため、財務省内の各法執行機関に所属するTメンたちを結びつける役割を果たし始めました。
沿岸警備隊では、エリザベス一人が暗号解読を担い、3年間で酒密輸にかかわる通信文を12000通解読しました。限界を覚えたエリザベスは、暗号解読班の設置を提案しました。提案が認められ、下級暗号解読者3名と速記者2名、それにオフィスが与えられました。アメリカ史上唯一の女性が率いる暗号解読班となりました。3人の新人が暗号解読のスキルを身につけました。1932年にF・D・ルーズベルトが大統領に就任したときには、エリザベス率いるチームは、アメリカにおける掛け値なしに最高の無線インテリジェンス組織に成長していました。ここで獲得したスキルに基づき、エリザベスはのちに、ナチ・スパイの極秘ネットワークを打ち破る立役者となります。
ニューオーリンズでの刑事裁判でエリザベスが証人として公開の裁判所で証言することとなり、エリザベスは一躍時の人となりました。
このころウィリアムは、その後10年にわたって、陸軍で日本の外交暗号の解読に携わることになりました。1930年にウィリアムは陸軍の新たな暗号解読班を立ち上げ、これがのちに国家安全保障庁の中核をなすことになります。
ウィリアムはこの組織で、日本の外交暗号解読を目指すとともに、自分たちでも暗号作成機を創り出しました。
1930年ころから日本が使い始めた機械は、Angooki Taipu Aと呼ばれ、アメリカでは「レッド」のニックネームで呼ばれていました。1938年、日本はレッドを大幅に改良した高度な暗号機 Angooki Taipu Bに置き換えました。アメリカでは「パープル」と名付けました。
またウィリアムのチームは、M-134、さらに改良したSIGABAと呼ばれる暗号機を創出しました。アメリカ陸軍と海軍は第二次世界大戦中、1万台以上のシガバをあらゆる戦域に設置しました。ドイツ、イタリア、日本のいずれも、最後まで解読できませんでした。
ウィリアムの仕事は極秘であり、家に帰っても同業者である妻にすら話すことができません。ウィリアムは夜に帰宅するとほとんど何もしゃべらない生活となりました。ウィリアムの神経が病んでいきます。
ナチスドイツがボーランドに侵攻し、第2次大戦が勃発しました。
大西洋を隔てたアメリカは安全なように思われましたが、もしナチが南米を支配したら、アメリカも安全ではなくなります。
ヒトラーは、南米に工作員を送り込みました。携帯式無線機をもった新人工作員が、Uボートで海岸にたどり着いたり、飛行機から落下傘で降下したりして目的地に潜り込みました。
エリザベス・フリードマンが1940年から1945年にかけて行っていたことについては、厳重な機密指定がされ、エリザベスの死後にようやく封を解かれました。
エリザベスのチームは、財務省から依頼された暗号を解読するうちに、未登録の無線局から発信された謎めいた暗号文の存在に気づきました。暗号を解読すると、平文はドイツ語であり、位置測定からすると発信元はメキシコ、南米、アメリカにある未確認の無線局のようです。まもなく、これらの無線局はナチのスパイが設置したものだとわかりました。
エリザベスと彼女のチームは、紙と鉛筆を用いて直感と経験をもとに、この暗号を解読していくのです。著書では、その過程が詳細に示されています。
エリザベスの基本的な解読スタイルは、紙と鉛筆で試行錯誤を繰り返し、推論を立ててそれを試します。エリザベスはこれまでの25年間、何万通もの通信文を手掛ける中で、ありとあらゆる種類の暗号を解いてきたので、近道の見つけ方、つまりは文中でのパターンの見分け方を心得ていたからです。エリザベスは一種の人間コンピュータでした。
1940年、ドイツのエニグマ機で作成された暗号文に始めて遭遇したとき、エリザベスはたいして怖じ気づきはしませんでした。
エニグマ機で暗号を作成するに際し、マシンのロータの開始位置を頻繁に変更することが必要です。しかしある無線局では、送信者がまちがって同じ開始位置を使ってすべての通信文を送っていました。そのため、数多くの暗号文を縦に重ねることで、暗号を解く鍵を見つけたのです。そしてチームは、暗号の特徴がエニグマ機に似ていることに気づきました。保有していた古いエニグマの商用機で解析を始めました。そして、見たこともないエニグマ機にある3枚のロータすべての配線をなんとか解明して見せました。
ウィリアムが率いる陸軍暗号解読班では、日本の外交暗号機パープルが生成する暗号文の解読に努めていました。
『1940年9月のある日、ウィリアム・フリードマン率いる陸軍暗号解読班がいる窓のない丸天井の部屋で、所属する2人の女性暗号解読者のうちの1人、ジュネビーブ・グローチャンが自分のデスクの前に立ち、なにかを発見したかも知れません、と男たちに話しかけた。
・・・
このときグローチャンは、これまで誰も見つけられなかった2つのパターンが見えてきた、と感じていた。』
男たちはデスクのまわりに集まってきます。
『「これだ!」とローレットが叫ぶ。「これだよ! 探していたものをジーンが見つけてくれた!」』
男たちはこの発見に興奮して笑いながら飛び跳ねていましたが、ウィリアム1人はほとんど悲しげに見えました。このときすでに、ウィリアムは精神的に病んでいたのです。
グローチャンの発見から5日後、1通の通信文が始めて完全に解読されました。
『今日、暗号史の研究者は、苦難の末に成功をものにしたという点では、パープルの突破は、アラン・チューリングのひらめきによりドイツの暗号エニグマを打ち破った功績と同等の価値があるととらえている。』
ウィリアムたちは、日本の通信文を読み解くためのパープル模造機の作製に取りかかり、完成させました。
パープル暗号を解読した解読文のうちで最高機密扱いされるものをマジックと呼ぶようになりました。日本が真珠湾攻撃を敢行したとき、在米日本大使が米大統領に手渡すべき最後通牒を、その前の日の晩にルーズベルト大統領がマジックとして入手し読んでいたことは有名です。日本は戦争終結に至るまで、パープル暗号が敵方に解読されていることに全く気づきませんでした。
以下次号