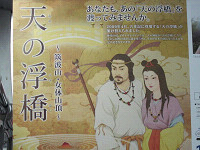12月29日の日経朝刊によると、日本郵政の斉藤次郎社長は28日の定例記者会見で、郵便貯金の預入限度額(1千万円)について、政府に見直しを求める考えを示しました。
郵政民営化見直しがどのような方向に向かうのか、現在のところ、まだ明らかになっていません。取り敢えず、郵政民営化法で株式の売却(民営化)期限が法定化されていたのに対し、日本郵政株式売却凍結法によって売却を凍結することまで決まりました。
凍結したまま国有状態としておくのか、所定の割合を国有化したままで残りを売却するのか、時期は遅れるけれども結局は全株売却して民営化するのか、闇の中です。
国有状態におかれるのであれば、株式会社とはいえ国民は「潰れない会社」と信頼するでしょう。破綻しそうになったら税金を投入するであろうことは容易に予想できます。新銀行東京のようなものです。
通常の銀行であれば、破綻したら預金のうち1千万円以上の部分はペイオフで戻ってきません。1行あたりの預金残高を何とか1千万円以下に抑えようと努力します。それに対しゆうちょ銀行が国有のままで預入限度額が1千万円以上になるのだったら、預金者は当然ながらゆうちょ銀行に1千万円以上のお金を預けることになるでしょう。
そのような論理で銀行界から反論が出ることがわかっている中、斉藤社長はなぜ上記のような発言を記者会見でしたのでしょうか。
比較的最近、新聞のインタビュー記事で斉藤社長は、「民営化しないわけではない」というような発言をしていました。その記事を読んだ限りでは、今回の株式売却凍結法成立で一時凍結はしたが、時期を遅らせるだけでいずれ株式を売却して民営化する、というように読み取れました。
しかし、郵政民営化見直しは、決して日本郵政社長が行うものではありません。あくまで政府が計画を作り、法律改正によって実現するものです。一番の旗振りは言わずと知れた亀井静香郵政担当大臣です。
斉藤社長の思惑と、政府・特に亀井静香大臣の思惑とはどのように一致しているのでしょうか。
郵政民営化見直しがどのような方向に向かうのか、現在のところ、まだ明らかになっていません。取り敢えず、郵政民営化法で株式の売却(民営化)期限が法定化されていたのに対し、日本郵政株式売却凍結法によって売却を凍結することまで決まりました。
凍結したまま国有状態としておくのか、所定の割合を国有化したままで残りを売却するのか、時期は遅れるけれども結局は全株売却して民営化するのか、闇の中です。
国有状態におかれるのであれば、株式会社とはいえ国民は「潰れない会社」と信頼するでしょう。破綻しそうになったら税金を投入するであろうことは容易に予想できます。新銀行東京のようなものです。
通常の銀行であれば、破綻したら預金のうち1千万円以上の部分はペイオフで戻ってきません。1行あたりの預金残高を何とか1千万円以下に抑えようと努力します。それに対しゆうちょ銀行が国有のままで預入限度額が1千万円以上になるのだったら、預金者は当然ながらゆうちょ銀行に1千万円以上のお金を預けることになるでしょう。
そのような論理で銀行界から反論が出ることがわかっている中、斉藤社長はなぜ上記のような発言を記者会見でしたのでしょうか。
比較的最近、新聞のインタビュー記事で斉藤社長は、「民営化しないわけではない」というような発言をしていました。その記事を読んだ限りでは、今回の株式売却凍結法成立で一時凍結はしたが、時期を遅らせるだけでいずれ株式を売却して民営化する、というように読み取れました。
しかし、郵政民営化見直しは、決して日本郵政社長が行うものではありません。あくまで政府が計画を作り、法律改正によって実現するものです。一番の旗振りは言わずと知れた亀井静香郵政担当大臣です。
斉藤社長の思惑と、政府・特に亀井静香大臣の思惑とはどのように一致しているのでしょうか。