今年の「麻布学」についての港区市民大学全6回の5回目。4回目と6回目は所用で欠席。つまり最後なのだが、個人的には最も期待していた回である。
実は、数年前から「赤い靴はいてた女の子、岩崎きみちゃん」について、その実在性と欠落している歴史について追いかけていた。わずか9歳で亡くなった「きみちゃん」の終焉の地が、この鳥居坂教会の孤児院である「永坂孤女院」であったこと。彼女の一時的養父母だったメソジスト派の宣教師ヒューエット牧師。そして今、青山墓地の鳥居坂教会の共同墓地に名を刻んでいること。いずれにしても、すべての秘められた謎は、この鳥居坂教会、そして関連する東洋英和女学院のルーツと深く関連があると考えられるのである。講師は、この東洋英和の伊勢紀美子先生。インサイダーである。
講義をまとめる前に、メソジストについて、以前、調べていた内容と若干異なっていると感じた部分がある。大勢に影響がある話ではないが、以前の調査では、メソジストはカナダ、アメリカ北西部を布教の中心にしていたものの、三派に分裂、その後、北米大陸ではさらに多くの分派活動があり、それぞれ対立構造にあったものの、日本では、かろうじて分裂を免れていたというような状況だったと思うが、それについては触れられなかった。(話が複雑すぎるからだろうか)
一応、簡単に1824年にカナダ・メソジスト監督教会が米国から分離したところから始まる。つまり、日本に来たメソジストの始まりは米国ではなくカナダだったということ。それによる特殊性を考慮しなければならない、ということらしい。つまり、日本進出の後発性とカナダの特殊事情(封建的)ということだそうだ。
まず、日本進出の後発性だが、すでに他の派が各地でキリスト教の布教を進めていた後から割り込もうというのだから、窮屈だった。切支丹禁制の高札が撤去されたのは、岩倉使節団の結果の一つだが、この1873年から布教を開始しようとしたが、ビジネスと同じで、既に出遅れである。他派はフライングでどんどん前にいた。結果として、進出しようとしたのが、北海道、東京、長野、北陸、そして静岡だそうだ。北海道はこれからの開拓地であり、東京は人口の集まる首都。そして長野は善光寺、北陸は永平寺という仏教心の強いエリアで他派が回避していた地区。では、静岡は何?ということには、裏日本史があった。
静岡には、明治になったころ、徳川幕府関連の幕府官僚たちが身を寄せていた。大将の慶喜は「洋風かぶれ」だったが、官僚たちは、結構、幕府再興を狙っていたらしいのだ。そのため、まずは、外国語の習得が重要と、外国人教師を招いて英会話に励んでいたらしいのだ。そこに目をつけたのが、日本における布教の父、D・マグドナルド氏。静岡に英語学校兼教会を建てる。そして、10年が経ち、もはや幕府再興など雲散霧消。やっと東京・麻布周辺の土地を確保し、首都攻略を始める。
当時は、「布教と教育と福祉」というのがメソジストの三本の柱だったそうで、それぞれ「鳥居坂教会」「東洋英和」「孤児院」というのが対応していたそうだ。そこへ来日していたのが、宣教師ということで、特にカナダ出身の女性宣教師が多かったそうだ。それも20歳代の独身女性。というのもわけがあって、当時、カナダはまだヴィクトリア朝の傘下で、まったくの古い体制で、既婚女性は働いてはいけないことになっていた。そのため、独身女性の働き場所としては、宣教師というのは一般的には魅力的な高給だったそうだ。
当時の条件は高学歴、かつ高教養で、家政学、保健学、芸術、語学、特殊技能などに長け、かつキリスト教に熱心で、どんな場所でも嫌といわずに働かなければならなかったそうだ。3年の任期の途中で辞めるというと、出張旅費や手当ての多くが没収されたそうだ。蟹工船みたいな話だ。そして、今では、カナダ国内で「差別問題」と言われているのが、当時の布教活動で、特に日本には、教会内の「Aクラスの人材」を派遣していたのに対し、海外からカナダに移民で入ってくる人たち向けには「Bクラスの人材」を、そして先住民族の布教には「Cクラスの人材」を使っていて、このCクラスの人たちが、先住民のこどもたちを無理矢理に親から引き離し、教会に住み込ませて洗脳したりしたそうだ。
この宣教師のランクは給料格差にもなっていて、AクラスとCクラスでは1.5倍の給与格差があったそうだ。まあ、ビジネスの世界でも新規開発には優秀な人材を用いるのが普通だから、あまり違和感はないが、ありがちな話だ。
 そして、話を一気に飛ばして、「きみちゃん」のいた永坂孤女院の件だが、1894年に開設されている。木造二階建て。その後、1908年に、この建物の1階が日曜学校になり、2階が孤女院になっている。というと2階に詰め込んだように感じるが、1904年に周辺に二ケ所の新設孤児院を造っているので、それなりの計画の一環だったのだろう。そして、講義の時に配られたペーパーには、1908年に撮影された、孤女院とその孤児たち一同の写真が写っていた。
そして、話を一気に飛ばして、「きみちゃん」のいた永坂孤女院の件だが、1894年に開設されている。木造二階建て。その後、1908年に、この建物の1階が日曜学校になり、2階が孤女院になっている。というと2階に詰め込んだように感じるが、1904年に周辺に二ケ所の新設孤児院を造っているので、それなりの計画の一環だったのだろう。そして、講義の時に配られたペーパーには、1908年に撮影された、孤女院とその孤児たち一同の写真が写っていた。
ところが、・・
一方、「きみちゃん」の短い人生を辿ると、1902年7月15日に静岡で生まれ、その後、函館でヒューレット宣教師夫妻の養女になり、夫妻が米国に帰還する際、何らかの理由で日本に残り、この永坂孤女院に預けられたのが、1908年と言われている。そして3年後、1911年9月15日、9歳で他界。
ということは、当日、配られたペーパーの中の写真のコピーには「きみちゃん」が写っている可能性もあるわけだ。写真の服装からすると、春か秋と思われる。
そして、これらの資料類のほとんどは、「鳥居坂教会百年史」という書籍の中にあるそうなのだが、既にその書物が、「国会図書館」または「都立中央図書館」に存在していることを突き止めているのである。
ところで、鳥居坂教会の関連の学校と言うと、東洋英和以外にも東京女子大や麻布学園がある。特に、近来、東大進学御三家として有名な麻布中高学校。男子校である。麻布学園は、ある理由で、この鳥居坂系のグループと袂を分かち独立したそうである。「主義の違い?」
その件について、伊勢先生は、「学内でタブーとされている理由であるものの、地元と共生するためには克服すべき問題なので、あえて触れてみた」と言われていた。「問題のような性格のもの」とも言われていた。
しかし、「問題のような性格のもの、に触れてみた」と言われても、部外者の私には、何のことやら、さっぱりわからないのである。「地元との共生」と言われても抽象的過ぎる。「身分の低い人(入学時寄付金の少ない人)は女子大に入れない」という時代があったのだろうか。それなら「偏差値130以下は麻布中学に入れない」というのと同じようなものじゃないかとも思うし、・・・
やはり、とりあえず「鳥居坂教会百年史」を紐解かなければならないのかな。
↓GOODなブログと思われたら、プリーズ・クリック

↓BADなブログと思われたら、プリーズ・クリック

実は、数年前から「赤い靴はいてた女の子、岩崎きみちゃん」について、その実在性と欠落している歴史について追いかけていた。わずか9歳で亡くなった「きみちゃん」の終焉の地が、この鳥居坂教会の孤児院である「永坂孤女院」であったこと。彼女の一時的養父母だったメソジスト派の宣教師ヒューエット牧師。そして今、青山墓地の鳥居坂教会の共同墓地に名を刻んでいること。いずれにしても、すべての秘められた謎は、この鳥居坂教会、そして関連する東洋英和女学院のルーツと深く関連があると考えられるのである。講師は、この東洋英和の伊勢紀美子先生。インサイダーである。
講義をまとめる前に、メソジストについて、以前、調べていた内容と若干異なっていると感じた部分がある。大勢に影響がある話ではないが、以前の調査では、メソジストはカナダ、アメリカ北西部を布教の中心にしていたものの、三派に分裂、その後、北米大陸ではさらに多くの分派活動があり、それぞれ対立構造にあったものの、日本では、かろうじて分裂を免れていたというような状況だったと思うが、それについては触れられなかった。(話が複雑すぎるからだろうか)
一応、簡単に1824年にカナダ・メソジスト監督教会が米国から分離したところから始まる。つまり、日本に来たメソジストの始まりは米国ではなくカナダだったということ。それによる特殊性を考慮しなければならない、ということらしい。つまり、日本進出の後発性とカナダの特殊事情(封建的)ということだそうだ。
まず、日本進出の後発性だが、すでに他の派が各地でキリスト教の布教を進めていた後から割り込もうというのだから、窮屈だった。切支丹禁制の高札が撤去されたのは、岩倉使節団の結果の一つだが、この1873年から布教を開始しようとしたが、ビジネスと同じで、既に出遅れである。他派はフライングでどんどん前にいた。結果として、進出しようとしたのが、北海道、東京、長野、北陸、そして静岡だそうだ。北海道はこれからの開拓地であり、東京は人口の集まる首都。そして長野は善光寺、北陸は永平寺という仏教心の強いエリアで他派が回避していた地区。では、静岡は何?ということには、裏日本史があった。
静岡には、明治になったころ、徳川幕府関連の幕府官僚たちが身を寄せていた。大将の慶喜は「洋風かぶれ」だったが、官僚たちは、結構、幕府再興を狙っていたらしいのだ。そのため、まずは、外国語の習得が重要と、外国人教師を招いて英会話に励んでいたらしいのだ。そこに目をつけたのが、日本における布教の父、D・マグドナルド氏。静岡に英語学校兼教会を建てる。そして、10年が経ち、もはや幕府再興など雲散霧消。やっと東京・麻布周辺の土地を確保し、首都攻略を始める。
当時は、「布教と教育と福祉」というのがメソジストの三本の柱だったそうで、それぞれ「鳥居坂教会」「東洋英和」「孤児院」というのが対応していたそうだ。そこへ来日していたのが、宣教師ということで、特にカナダ出身の女性宣教師が多かったそうだ。それも20歳代の独身女性。というのもわけがあって、当時、カナダはまだヴィクトリア朝の傘下で、まったくの古い体制で、既婚女性は働いてはいけないことになっていた。そのため、独身女性の働き場所としては、宣教師というのは一般的には魅力的な高給だったそうだ。
当時の条件は高学歴、かつ高教養で、家政学、保健学、芸術、語学、特殊技能などに長け、かつキリスト教に熱心で、どんな場所でも嫌といわずに働かなければならなかったそうだ。3年の任期の途中で辞めるというと、出張旅費や手当ての多くが没収されたそうだ。蟹工船みたいな話だ。そして、今では、カナダ国内で「差別問題」と言われているのが、当時の布教活動で、特に日本には、教会内の「Aクラスの人材」を派遣していたのに対し、海外からカナダに移民で入ってくる人たち向けには「Bクラスの人材」を、そして先住民族の布教には「Cクラスの人材」を使っていて、このCクラスの人たちが、先住民のこどもたちを無理矢理に親から引き離し、教会に住み込ませて洗脳したりしたそうだ。
この宣教師のランクは給料格差にもなっていて、AクラスとCクラスでは1.5倍の給与格差があったそうだ。まあ、ビジネスの世界でも新規開発には優秀な人材を用いるのが普通だから、あまり違和感はないが、ありがちな話だ。
 そして、話を一気に飛ばして、「きみちゃん」のいた永坂孤女院の件だが、1894年に開設されている。木造二階建て。その後、1908年に、この建物の1階が日曜学校になり、2階が孤女院になっている。というと2階に詰め込んだように感じるが、1904年に周辺に二ケ所の新設孤児院を造っているので、それなりの計画の一環だったのだろう。そして、講義の時に配られたペーパーには、1908年に撮影された、孤女院とその孤児たち一同の写真が写っていた。
そして、話を一気に飛ばして、「きみちゃん」のいた永坂孤女院の件だが、1894年に開設されている。木造二階建て。その後、1908年に、この建物の1階が日曜学校になり、2階が孤女院になっている。というと2階に詰め込んだように感じるが、1904年に周辺に二ケ所の新設孤児院を造っているので、それなりの計画の一環だったのだろう。そして、講義の時に配られたペーパーには、1908年に撮影された、孤女院とその孤児たち一同の写真が写っていた。ところが、・・
一方、「きみちゃん」の短い人生を辿ると、1902年7月15日に静岡で生まれ、その後、函館でヒューレット宣教師夫妻の養女になり、夫妻が米国に帰還する際、何らかの理由で日本に残り、この永坂孤女院に預けられたのが、1908年と言われている。そして3年後、1911年9月15日、9歳で他界。
ということは、当日、配られたペーパーの中の写真のコピーには「きみちゃん」が写っている可能性もあるわけだ。写真の服装からすると、春か秋と思われる。
そして、これらの資料類のほとんどは、「鳥居坂教会百年史」という書籍の中にあるそうなのだが、既にその書物が、「国会図書館」または「都立中央図書館」に存在していることを突き止めているのである。
ところで、鳥居坂教会の関連の学校と言うと、東洋英和以外にも東京女子大や麻布学園がある。特に、近来、東大進学御三家として有名な麻布中高学校。男子校である。麻布学園は、ある理由で、この鳥居坂系のグループと袂を分かち独立したそうである。「主義の違い?」
その件について、伊勢先生は、「学内でタブーとされている理由であるものの、地元と共生するためには克服すべき問題なので、あえて触れてみた」と言われていた。「問題のような性格のもの」とも言われていた。
しかし、「問題のような性格のもの、に触れてみた」と言われても、部外者の私には、何のことやら、さっぱりわからないのである。「地元との共生」と言われても抽象的過ぎる。「身分の低い人(入学時寄付金の少ない人)は女子大に入れない」という時代があったのだろうか。それなら「偏差値130以下は麻布中学に入れない」というのと同じようなものじゃないかとも思うし、・・・
やはり、とりあえず「鳥居坂教会百年史」を紐解かなければならないのかな。
↓GOODなブログと思われたら、プリーズ・クリック

↓BADなブログと思われたら、プリーズ・クリック













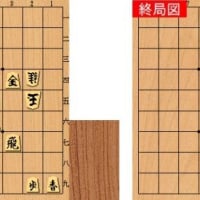




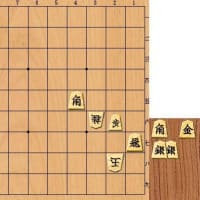


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます