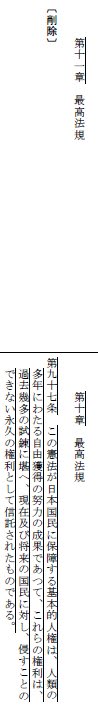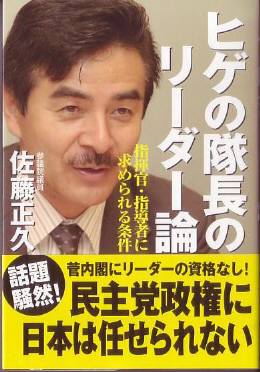結論--住民による自治基本条例の意義を理解して、自民党改憲草案を見ても、あなたは自民党候補に投票しますか?
投票するなら、以下は読まずにページを閉じた方が時間の節約。
しかし、ふるさと山梨を考え、山梨らしさを大事にするあなたは、自民党安倍政権にそれを潰されても良いと思っていますか? なるほど自分さえゼニを稼げれば憲法もふるさと山梨も関係ないか。
7月20日から全国ロードショーが始まった 「風立ちぬ」 のスタジオジブリが、小冊子『熱風』7月号特集 緊急PDF配信 を始めています。
◇ 憲法を変えるなどもってのほか ~ 宮崎 駿さん (映画監督 みやざき・はやお)
◇ 9条 世界に伝えよう ~ 鈴木敏夫さん (映画プロデューサー すずき・としお)
◇ 戦争は怖い ~ 中川李枝子さん (児童文学作家 なかがわ・りえこ)
◇ 60年の平和の大きさ ~ 高畑 勲さん (アニメーション映画監督 たかはた・いさお)
以上4編が収録され、巻末に丁寧な[編集部注]があり、PDFファイルで28ページ、853 KBです。
ダウンロードは無料、配信期間は8月20日18時まで、「無断転載を禁止します。」 の公開です。
◇ 地域の若者と共に政治に関心を持っておられる全国の皆さん、他山の石、以て玉を攻く可し・・・2013年7月20日付け、棄権を煽る地方紙
◇ 私の巡回先ブログ、「国民の生活が第一は人づくりにあり」・・・2013年7月20日付け、若者の投票参加が君たちの将来を希望に変える・21日は投票で若者の意思を表現しよう (記事中のリンク集に私の記事も入れて戴きトラックバックが着信、こういうブロガーさんを私はネティズンと呼ぶ)
甲府市自治基本条例を制定しました
甲府市自治基本条例 平成19年6月21日
条例第21号
私たちのまち甲府市は、あふれる光と清らかな水に恵まれた甲府盆地にあり、先人は、輝かしい歴史を築きあげ、多彩な地域の文化を育んできました。
いま、人と人、人と自然が共生し、平和で住みよいまちとして発展させ継承していくために、私たちは、自律した自治のあり方を見据え、そのしくみをより確固たるものとしなければなりません。
私たちは、主体的に生き、人を思いやる心を大切にし、市民と市議会と市長をはじめ市政を執行するものとの協働により、公正で平等な地域社会をつくり、市民の福祉の増進を図って、次の世代に引き継いでいきます。
私たちは、甲府市民としての誇りと責任をもち、ここに、甲府市自治基本条例を制定します。
【前文の解釈】
① 前文は、この条例の制定の趣旨、目的、基本原則などを述べるもので、本文と一体をなすものとして本文各条項の解釈基準となるものです。
② 自治基本条例は、甲府市の最高規範として、自治の理念や基本原則などを定める重要な条例であり、それらを明らかにするために前文を置きました。
③ 甲府市は、山岳地域をはじめとする美しい自然に恵まれ、県庁所在都市の中で全国一の日照時間を誇る光が甲府盆地に降り注ぎ、金峰山を源流とする豊かで清らかな水は、荒川として市内を流れています。また、盆地に点在する古墳や遺跡、市内各地で伝承されてきた民俗行事など、人々は輝かしい歴史と彩りの文化を育んできました。
④ 「自律した自治」とは、自ら決定した規範等に従って行動し、その結果について自ら責任を負う自治をいいます。
⑤ 「甲府市市民憲章」の「この甲府の市民であることに誇りと責任を感じ」の趣旨を踏まえ、市民、市議会、市長等が協働して起草した甲府市自治基本条例を制定することを謳っています。
甲府市自治基本条例は現行憲法の前文に表現された理念がベースにあったはずです。
しかし、⑤ に私は引っ掛かります。
甲府市市民憲章制定経過 『昭和39年9月市役所において、甲府青年会議所の主催による市長をかこむ懇談会が開催され、その席上、青年会議所より市民の道徳心を高め、社会共同意識を高揚して明るく豊かな甲府市をつくるために、本市に市民憲章を制定してはどうだろうか、との提案がなされました。』 以下略しますのでソースを確認してください。
(甲府市民の皆さんには申訳ないが、私はここに書かれたような発想による提案を好みません、最初に市民憲章を見た時の違和感の理由が経緯を確認して分かったのです)
自治基本条例の市民検討会で「市民憲章を踏まえて」という意見があったかどうかは知りません、私が出席した時の会合では無かった、あれば私はその時に内容と制定経緯を確認していたはずで、それがいつもの私のスタンスですから。
自治基本条例の解釈に市民憲章を引用したのは、自治基本条例が市民の責任や義務を定義しているとの解釈を普遍化する。意図的ではないにせよ、解説文作成者(おそらく甲府市の公務員)の脳裏にはそういう観念が染み込んでいることを示します。
都留市自治基本条例」ができました!
都留市自治基本条例 平成20年12月24日条例第39号
都留市自治基本条例も、現行憲法の前文に表現された理念がベースにあったはずです。
しかし、都留市のページにある「前文解釈」でも、責任と義務を負っているとの文言があります、自治基本条例前文にはそういう「強い言葉」は使われていません。
考え方を確認し、納得し、心に感じてそれを実現・実行していこうと考えるものです。義務だ責任だというものは、それぞれの個別テーマの法令規則で事細かに決められていく、その大前提が基本条例(憲法)前文だと私は考えています。
思い出して自分の古い記事を確認しました。自治基本条例市民案の説明会 「前文の原案」 で次のように書きました・・・
あの日のテーブルごとの話し合いでは、私は提案(エ)を推薦したと記憶しています。理由は条例の前文はいつの時代に読んでも、その時にマッチする基本的な考え方を述べておくだけで良い。書かれていることが制定の時代と直結していると後世の人々には違和感が生じるだろう、ということです。
しかし、甲府の歴史も地勢もまだよく知らない私としては、これらの前文を読むだけで甲府市が分かってくるような気がしますから、その事は素晴らしいものと思います。また、そのような前文は後にこの自治基本条例を読む人々が、市民は制定に際し、その時代の中で何を想い考えてこれを決めたのかが読み取れるということでもある訳です。
そのような歴史性のある前文というのも悪くはないですが、それらを踏まえた歴史を超えた一つの軸を明確にすることに前文の意義があるように考えています。全ての人々の「協働と参画によって、公正で平等な社会の仕組みを次の世代につなげていく社会の実現」、それは日本の政治体制が変わらない限り普遍のものであると考えています。
今、私が自民党改憲草案を読む時の感じ方は、この当時と変わりありませんね、私はブレない(^o^)
しかし、その日本の政治体制が変わろうとしているのが、安倍晋三一族による改憲策動です。
自民党の日本国憲法改正草案が成立した時、甲府市自治基本条例の前文も条項も「解釈」が変るか、あるいは「改正」されることを想定するのは当然です。
「日本国憲法に反した自治基本条例はけしからん!」 と政府、総務省、警察庁、マスコミ・・・もしかすると国防軍憲兵隊まで、総掛かりで動きだすでしょう。
甲府市議会議員の誰かが提言したように、自治体は自治会(町会)への市民加入義務条例を制定し、市民相互監視システムの「隣組」が確立する。権力者が期待してきたシステムです。
国防軍に志願入隊する若者を隣組全員で日の丸の小旗を振って送り出す。
(甲府市自治会連合会は既に行政の飼犬ですから、市民監視システムの役目も担っている? だから選挙運動にも強い?)
◇ 自民党の活動 > コラム > 「憲法改正草案」を発表
◇ 政策 > 政策トピックス > 日本国憲法改正草案
(どちらもPDFファイルは同じです。前文は次の通り)
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。
日本国憲法 【前文】
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
私は身近に知っている甲府市自治基本条例を引き合いに出して書きましたが、北海道ニセコ町に始まった自治基本条例制定は全国的に広がっています。まちづくり基本条例という名称もありますが、基本的には地域自治のあり方を住民自身が決めているものです。環太平洋経済連携協定(TPP)もそれに影響するであろう事は既に沢山の記事があります。
国の形が変わろうとする参院選の結果が安倍政権大勝で終れば、自分達の街の姿も変えてしまう、そこまで考えねばならない一票の価値です。