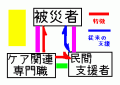2013/04/19 記
--------------
父の兄の入院する病院に行く準備をしていると、母から面会謝絶との話で従兄弟のところに連絡を取る。丁寧に見舞いを遠慮するようにと断られた。昔、父が信じる宗教をゴリ押しした経過が今もなお響いている。
JR相模原の塾の方に、到着が夜になると連絡をしてしまっていたために時間が空いて、返却日が迫っていた寒川町立図書館に出かけ、書籍の更新をしておいた。
通信の寄稿依頼の応答がなく、大船渡の元看護師さんが震災後、仮設生活のスナップを撮っていたので、依頼をかけたが力作という写真が、背景のわからない家族写真だった。息子さんは陸前高田にいて助かった。家族揃っての写真には、万感の思いがあるのはわかる。私が人の営みの写真をと言ったのがいけないのだが、第三者がこの写真を見ても、意味が通じない。恐縮しつつ、転載は遠慮させてもらった。
私は民宿の親父さんや、学校の先生に情報ルートを作って帰ってきたが、地元感覚とのずれに悩んでいる。ひとつは着眼点の差、もうひとつは地元の、外部のない視点だ。そんなことは誰でも知っているということが、湘南にいる私にはわからない。ずいぶんと日が経って、雑誌の記事の1行に疑問を持ち、問いかけたところ、話は既に完結していたという歯がゆさだ。陸前高田市のオンデマンド・バスの話などがその例だろう。
私は次の訪問の際、地元タクシー協会に、高齢者と障がい者の通院・遠隔地入院移送の交通費見積もりを打診してこようとしていた。これは医療費控除の対象になるが、早急の資金立ては自己負担となる。当座この部分について、基金的活動ができないものかと考えていたからだ。しかし、オンデマンド・バスの実施は、車を提供した**君のメルマガからも、民宿の親父さんからも全く情報がなかった。親父さんと話をしてみると、特定の地域に運行されるのであって、自分の地域ではないこと、その話はみんなが知っていることではないかというのだった。この情報網の粗さでは、活動をたちあげることはできない。私たち非被災地の人間が欲している情報という発想自体が異星人の言動のように響いてしまう。これは閉じたコミュニティに生きる者の特徴なのだが、私は被災地を往復しないと、関係が閉じてしまうという焦りのなかにいる。
私が作りたいと考えている「私的民間交流の育成」につながる民泊活動と家族付き合いの種まきも、私が陸前高田で準備すれば、それは南三陸でも可能なことであって、お膳立ては常に木っ端舟の状態にある。誰をで合わせたらいいのだろうかと考える。可能性の残っている者は、相模原の塾の成人クラスの面々だろう。難しい。方法はないかとあがいている。
しかしなあ、いまどきVサインはないだろうと、元看護師さんのスナップを眺めて、柏手を打って消去した。ごめん。
------
日本リハビリテーション協会の冊子「ノーマライゼーション」の中に出てくる仮設生活者の方と連絡がとれないか打診をしている。仲介依頼は難しいので、対象者をしぼって、湘南に招待できないか探っている。特に発達障がいや、精神障がいの困難がつかめる情報はないかと思っているが、招待する湘南側が連携できない状況にあるから、懇談の場へのセットをどうしていくか、私のやり方は「歩きながら考える」だから、すくむ足を踏み出している。
<気になる記事>
-----------------
●「津波被災の9学校 ストレス症状顕著 仙台市教委調査」
●「NPOが無償貸与 移動診療車到着 岩手県立高田病院」
非被災地からの医療・保健支援は、結局は寄付なのだろうか。手立てを考えねば…。
-------
夜間傾聴:なし
(校正1回目済み)
p.s.山田町++さんと話す。
--------------
父の兄の入院する病院に行く準備をしていると、母から面会謝絶との話で従兄弟のところに連絡を取る。丁寧に見舞いを遠慮するようにと断られた。昔、父が信じる宗教をゴリ押しした経過が今もなお響いている。
JR相模原の塾の方に、到着が夜になると連絡をしてしまっていたために時間が空いて、返却日が迫っていた寒川町立図書館に出かけ、書籍の更新をしておいた。
通信の寄稿依頼の応答がなく、大船渡の元看護師さんが震災後、仮設生活のスナップを撮っていたので、依頼をかけたが力作という写真が、背景のわからない家族写真だった。息子さんは陸前高田にいて助かった。家族揃っての写真には、万感の思いがあるのはわかる。私が人の営みの写真をと言ったのがいけないのだが、第三者がこの写真を見ても、意味が通じない。恐縮しつつ、転載は遠慮させてもらった。
私は民宿の親父さんや、学校の先生に情報ルートを作って帰ってきたが、地元感覚とのずれに悩んでいる。ひとつは着眼点の差、もうひとつは地元の、外部のない視点だ。そんなことは誰でも知っているということが、湘南にいる私にはわからない。ずいぶんと日が経って、雑誌の記事の1行に疑問を持ち、問いかけたところ、話は既に完結していたという歯がゆさだ。陸前高田市のオンデマンド・バスの話などがその例だろう。
私は次の訪問の際、地元タクシー協会に、高齢者と障がい者の通院・遠隔地入院移送の交通費見積もりを打診してこようとしていた。これは医療費控除の対象になるが、早急の資金立ては自己負担となる。当座この部分について、基金的活動ができないものかと考えていたからだ。しかし、オンデマンド・バスの実施は、車を提供した**君のメルマガからも、民宿の親父さんからも全く情報がなかった。親父さんと話をしてみると、特定の地域に運行されるのであって、自分の地域ではないこと、その話はみんなが知っていることではないかというのだった。この情報網の粗さでは、活動をたちあげることはできない。私たち非被災地の人間が欲している情報という発想自体が異星人の言動のように響いてしまう。これは閉じたコミュニティに生きる者の特徴なのだが、私は被災地を往復しないと、関係が閉じてしまうという焦りのなかにいる。
私が作りたいと考えている「私的民間交流の育成」につながる民泊活動と家族付き合いの種まきも、私が陸前高田で準備すれば、それは南三陸でも可能なことであって、お膳立ては常に木っ端舟の状態にある。誰をで合わせたらいいのだろうかと考える。可能性の残っている者は、相模原の塾の成人クラスの面々だろう。難しい。方法はないかとあがいている。
しかしなあ、いまどきVサインはないだろうと、元看護師さんのスナップを眺めて、柏手を打って消去した。ごめん。
------
日本リハビリテーション協会の冊子「ノーマライゼーション」の中に出てくる仮設生活者の方と連絡がとれないか打診をしている。仲介依頼は難しいので、対象者をしぼって、湘南に招待できないか探っている。特に発達障がいや、精神障がいの困難がつかめる情報はないかと思っているが、招待する湘南側が連携できない状況にあるから、懇談の場へのセットをどうしていくか、私のやり方は「歩きながら考える」だから、すくむ足を踏み出している。
<気になる記事>
-----------------
●「津波被災の9学校 ストレス症状顕著 仙台市教委調査」
●「NPOが無償貸与 移動診療車到着 岩手県立高田病院」
非被災地からの医療・保健支援は、結局は寄付なのだろうか。手立てを考えねば…。
-------
夜間傾聴:なし
(校正1回目済み)
p.s.山田町++さんと話す。