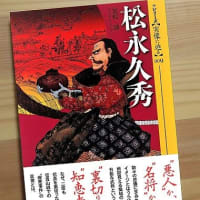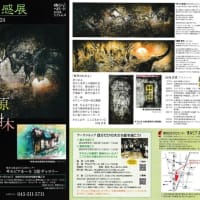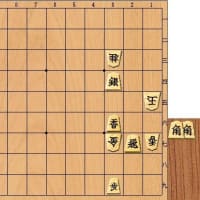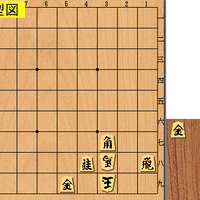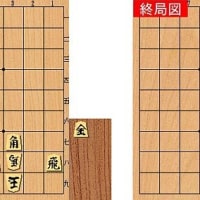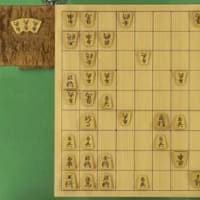2週間ほど前、2日ほど寝込んでしまったのだが、回復中に読んだ小冊子『川柳と浮世絵で楽しむ江戸散歩』が良かった。「たばこと塩の博物館」から出されていて、2007年の江戸講座で使われたようだ。
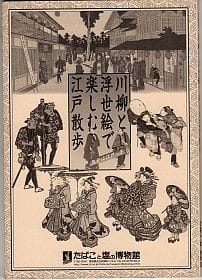
全187句のうち、以下の3句が現在の東京につながるので紹介してみたい。
辻番でこっそり鴨の葵坂
現在の道路だと六本木通りと外堀通りの交差する場所が「溜池交差点」であり、そこには大きな溜池があった。溜池と江戸城外堀とは葵坂でつながっていて、そこには幕府の番所があった。古事だが1651年に起きた慶安の役で由井正雪の手下として参加した丸橋忠弥が、江戸城襲撃計画のため江戸城の堀に石を投げて水深を測量したといわれる。外堀警備は本来重要な役目だった。
ところが100年下った頃は、太平の世の中。番所の役人は、ご禁制の鴨猟をこっそり行って、番所で鴨鍋にして食しているという句である。事実はいかに、ということ。鴨鍋仲間に幕閣を引きこんでいたのかもしれない。
橋杭で国と国とを縫い合わせ
これも解説がないと意味がわからない。場所は両国。JRの両国駅の北側には国技館がある。この駅と国技館の西側はすぐ隅田川だがJRの南側にかかる橋が『両国橋』、東側にいくと、荒川があり、さらに東に行くと江戸川があり、その先は千葉県だ。隅田川、荒川間が江東区で荒川、江戸川間が江戸川区だ。
ところが、江戸時代が始まった頃は、隅田川の東側はすべて千葉県(下総国)だった。(今でも千葉県っぽいところもあるが)
ことがあったのは明暦の大火。「振袖火事」とも言われるが、真相は不明のままだ。人口百万都市で十万人が亡くなったともいわれる。原因の一つに、隅田川に橋が不足していたことがいわれる。五街道の千住大橋だけが隅田川の橋で、江戸防衛のため他に橋がなかった。ということで橋を架けるとともに江東地区の開発が行われた。
ということで、橋杭は両国橋のことを指し、武蔵と下総の国境に橋があったという句なのだが、順序で言うと、橋ができたのが先で、江戸が広がったのが後で、その間は30年ほど。川柳ブームは、もっと後なので、過去の話がネタになっている。裏を読めば、川向うの人たちを差別する句なのかもしれない。
新宿のこどもは早く背が伸び
新宿は甲州街道の最初の宿場で、都心から近すぎるが、その次は高井戸なので、そこが長すぎる。新たに宿場が作られた。交通の要所で馬が行きかう物流の町だったようだ。馬が行きかうと発生するのが「馬糞」。馬は草食動物だから犬猫とはことなってバサバサしていて、踏んだからといって大惨事にはならない。
江戸時代には、「馬糞を踏むと背が伸びる」と言われていたそうで、これも新宿住民を笑い者にしようという句だ。
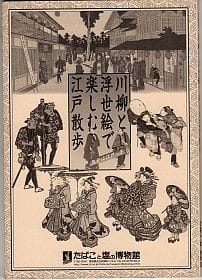
全187句のうち、以下の3句が現在の東京につながるので紹介してみたい。
辻番でこっそり鴨の葵坂
現在の道路だと六本木通りと外堀通りの交差する場所が「溜池交差点」であり、そこには大きな溜池があった。溜池と江戸城外堀とは葵坂でつながっていて、そこには幕府の番所があった。古事だが1651年に起きた慶安の役で由井正雪の手下として参加した丸橋忠弥が、江戸城襲撃計画のため江戸城の堀に石を投げて水深を測量したといわれる。外堀警備は本来重要な役目だった。
ところが100年下った頃は、太平の世の中。番所の役人は、ご禁制の鴨猟をこっそり行って、番所で鴨鍋にして食しているという句である。事実はいかに、ということ。鴨鍋仲間に幕閣を引きこんでいたのかもしれない。
橋杭で国と国とを縫い合わせ
これも解説がないと意味がわからない。場所は両国。JRの両国駅の北側には国技館がある。この駅と国技館の西側はすぐ隅田川だがJRの南側にかかる橋が『両国橋』、東側にいくと、荒川があり、さらに東に行くと江戸川があり、その先は千葉県だ。隅田川、荒川間が江東区で荒川、江戸川間が江戸川区だ。
ところが、江戸時代が始まった頃は、隅田川の東側はすべて千葉県(下総国)だった。(今でも千葉県っぽいところもあるが)
ことがあったのは明暦の大火。「振袖火事」とも言われるが、真相は不明のままだ。人口百万都市で十万人が亡くなったともいわれる。原因の一つに、隅田川に橋が不足していたことがいわれる。五街道の千住大橋だけが隅田川の橋で、江戸防衛のため他に橋がなかった。ということで橋を架けるとともに江東地区の開発が行われた。
ということで、橋杭は両国橋のことを指し、武蔵と下総の国境に橋があったという句なのだが、順序で言うと、橋ができたのが先で、江戸が広がったのが後で、その間は30年ほど。川柳ブームは、もっと後なので、過去の話がネタになっている。裏を読めば、川向うの人たちを差別する句なのかもしれない。
新宿のこどもは早く背が伸び
新宿は甲州街道の最初の宿場で、都心から近すぎるが、その次は高井戸なので、そこが長すぎる。新たに宿場が作られた。交通の要所で馬が行きかう物流の町だったようだ。馬が行きかうと発生するのが「馬糞」。馬は草食動物だから犬猫とはことなってバサバサしていて、踏んだからといって大惨事にはならない。
江戸時代には、「馬糞を踏むと背が伸びる」と言われていたそうで、これも新宿住民を笑い者にしようという句だ。