何年か前、岡山県で少し働いていた期間があり、その後も時時行っていたのだが、そろそろいかなくなりそうなので、最後かもしれない機会に謎を残しておきたくないという横柄な気持ちで、「各県謎解き散歩シリーズ」の一冊を開いたのだが、まったく謎だらけだ。岡山にいたころに散策するべきだった。
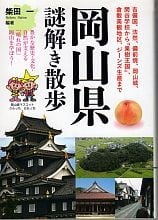
どちらかというと、歴史上の謎が多く、解決されていないことが多い。一回(1000字程度)で書ききれないような気がする。
1. きび団子
きび団子といえば桃太郎だが、桃太郎伝説に登場するのは「黍団子」。きびという穀物の粉を団子にしたもので、日本菓子歴史の最初の1ページに登場するような(本当だよ)和菓子だ。桃太郎と言えば、岡山県といわれ、大和朝廷と出雲勢力が死闘を行ったときに大和朝廷側の将軍だったと言われる(あくまで岡山県人の主張)。さらに岡山は古来から「吉備の国」と言われていた。「黍」なのか「吉備」なのか。
定説では古来ではなく、1856年に廣栄堂の先祖が考案したそうだ。ブームが起きたのは日清日露戦争で出兵していた兵士が帰ってくるのが隣の広島にある宇品港だったそうだ。そこに社長が乗りこんで、日本各地へ帰る兵士に「鬼退治団子」として売りさばいたことによるそうだ。つまり「黍」をかたった「吉備団子」ということだそうだ。
2. 岡山城と後楽園の奇妙な関係
岡山城は、秀吉の全国制覇が終わった後、宇喜多家を城主として築城されている。奇妙なことに川を西の防御線として東側には防御能力なく西側に半円形の敷地に天守閣や執務や居住のための建物がある。秀吉は宇喜多家を西の毛利からの攻撃耐えられるように設計する一方で、宇喜多家が寝返れば、一気に攻めつぶせるようにしていたと思われる。
一方、後楽園は日本三名園と言われる。江戸時代のほとんどの時期は池田家が治めていて、池田氏によって整備された。美しく、大きいのだが、なんとなく平らな感じがある。岡山城の欠落している東側の半円を埋めているようにも思われる。現地の解説では、幕府のお庭番(スパイ)が後楽園に来ることを警戒していたのは、殿が庭いじりの趣味で遊んでいると思われないため、となっているが、全く理由が違うという説があるようだ。つまり、徳川と戦う時には、たちまちのうちに東側も城塞として使えるようにということだ。ヘリ空母と言いながら、いざとなれば戦闘機が離発着できるような形にしているようなものだ。戦時中もそういう商船もあった。
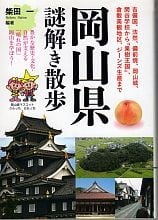
どちらかというと、歴史上の謎が多く、解決されていないことが多い。一回(1000字程度)で書ききれないような気がする。
1. きび団子
きび団子といえば桃太郎だが、桃太郎伝説に登場するのは「黍団子」。きびという穀物の粉を団子にしたもので、日本菓子歴史の最初の1ページに登場するような(本当だよ)和菓子だ。桃太郎と言えば、岡山県といわれ、大和朝廷と出雲勢力が死闘を行ったときに大和朝廷側の将軍だったと言われる(あくまで岡山県人の主張)。さらに岡山は古来から「吉備の国」と言われていた。「黍」なのか「吉備」なのか。
定説では古来ではなく、1856年に廣栄堂の先祖が考案したそうだ。ブームが起きたのは日清日露戦争で出兵していた兵士が帰ってくるのが隣の広島にある宇品港だったそうだ。そこに社長が乗りこんで、日本各地へ帰る兵士に「鬼退治団子」として売りさばいたことによるそうだ。つまり「黍」をかたった「吉備団子」ということだそうだ。
2. 岡山城と後楽園の奇妙な関係
岡山城は、秀吉の全国制覇が終わった後、宇喜多家を城主として築城されている。奇妙なことに川を西の防御線として東側には防御能力なく西側に半円形の敷地に天守閣や執務や居住のための建物がある。秀吉は宇喜多家を西の毛利からの攻撃耐えられるように設計する一方で、宇喜多家が寝返れば、一気に攻めつぶせるようにしていたと思われる。
一方、後楽園は日本三名園と言われる。江戸時代のほとんどの時期は池田家が治めていて、池田氏によって整備された。美しく、大きいのだが、なんとなく平らな感じがある。岡山城の欠落している東側の半円を埋めているようにも思われる。現地の解説では、幕府のお庭番(スパイ)が後楽園に来ることを警戒していたのは、殿が庭いじりの趣味で遊んでいると思われないため、となっているが、全く理由が違うという説があるようだ。つまり、徳川と戦う時には、たちまちのうちに東側も城塞として使えるようにということだ。ヘリ空母と言いながら、いざとなれば戦闘機が離発着できるような形にしているようなものだ。戦時中もそういう商船もあった。









