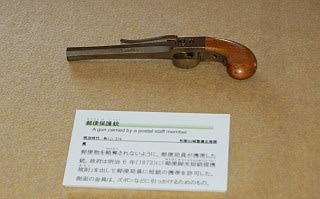千葉県の中南部(上総国)は丘陵地帯が広がっている。といって高い山があるわけでもないが、あまり人が住んでいない場所が多い。千葉県は海岸の近くは住みやすいわけで、あえて丘陵地帯の奥に住む人は少ないのだが、なぜか規模の小さな城跡が多い。
というのも室町時代の中期になると関東は群雄割拠となり、上総でまず根を下ろしたのが真里谷(まりやつ)武田氏。武田信長という強そうな人物が、1456年に真里谷の地に真里谷城を定めた。どうして、こんなに人里離れたところに城を作ったのかは謎だが、単純に推測すると、人が住んでいなかったからといえるのではないだろうか。どうみても山林で、付加価値があるわけではない。21世紀前半の我々だって行くのが大変だ。鉄道駅からは3キロだが、道は曲がりくねった上り坂。ナビ付の車でも道幅が気になる道だ。

実は、近くのゴルフ場によく行くのだが、最近、途中の道が混むため、いつもよりも30分前に出ると、1時間以上前に着きそうだったので、ちょっとだけ道を変えれば行ける。しかし、事前にネット上の経験談を読むと、登ってから降りるまで45分だが、足が滑りやすいので注意が必要と、転倒した人からの忠告が書かれていた、つまり登り始めると、ゴルフには間に合わない。どこかでUターンが必要になる。

ということで、入り口にあたる「木更津市青少年キャンプ場」の駐車場に辿り着くが、そこには残念な表示板があった。つまりキャンプ場は休場中なので中に入らないようにということ。もっとも誰もいないのは明白なのだが、他人の敷地に無断侵入すればいいのだが、何しろ、滑って転ぶと谷底ということになりかねない。
全体の雰囲気を感じたので、いきなり下城ということになる。
なお、この地は戦国時代の終わりごろには北条氏と里見氏が争うことになり、多くの血が流れることになる。
無断侵入して崖から落ちてもキャンプ地が休場していれば、発見する者もいないはず。500年以上前の無名の戦死者と枕を並べることになる。100年後に考古学者に発見され、「室町時代には虫歯の治療も行われていた」という論文が発表されるだろうか。
というのも室町時代の中期になると関東は群雄割拠となり、上総でまず根を下ろしたのが真里谷(まりやつ)武田氏。武田信長という強そうな人物が、1456年に真里谷の地に真里谷城を定めた。どうして、こんなに人里離れたところに城を作ったのかは謎だが、単純に推測すると、人が住んでいなかったからといえるのではないだろうか。どうみても山林で、付加価値があるわけではない。21世紀前半の我々だって行くのが大変だ。鉄道駅からは3キロだが、道は曲がりくねった上り坂。ナビ付の車でも道幅が気になる道だ。

実は、近くのゴルフ場によく行くのだが、最近、途中の道が混むため、いつもよりも30分前に出ると、1時間以上前に着きそうだったので、ちょっとだけ道を変えれば行ける。しかし、事前にネット上の経験談を読むと、登ってから降りるまで45分だが、足が滑りやすいので注意が必要と、転倒した人からの忠告が書かれていた、つまり登り始めると、ゴルフには間に合わない。どこかでUターンが必要になる。

ということで、入り口にあたる「木更津市青少年キャンプ場」の駐車場に辿り着くが、そこには残念な表示板があった。つまりキャンプ場は休場中なので中に入らないようにということ。もっとも誰もいないのは明白なのだが、他人の敷地に無断侵入すればいいのだが、何しろ、滑って転ぶと谷底ということになりかねない。
全体の雰囲気を感じたので、いきなり下城ということになる。
なお、この地は戦国時代の終わりごろには北条氏と里見氏が争うことになり、多くの血が流れることになる。
無断侵入して崖から落ちてもキャンプ地が休場していれば、発見する者もいないはず。500年以上前の無名の戦死者と枕を並べることになる。100年後に考古学者に発見され、「室町時代には虫歯の治療も行われていた」という論文が発表されるだろうか。