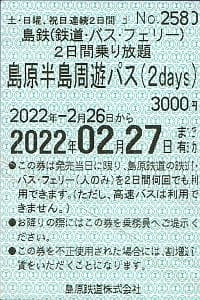佐久島の東港から西港に向かって歩き、さらに小さな森を抜けると新谷海岸に出る。海の向こうにいくつかの起伏のある陸地が見える。一見すると島々のように見える。

ところが、島々のように見えるのは渥美半島で、ここで見ている方が島なのだから、倒錯的だ。さらに問題は新谷海岸の砂。「紫の砂浜」と言われるそうだ。日本ではここだけ。
どういうことかというと、砂に交じってムール貝の貝殻が細かく砂状に広がっていて、これが紫に見える原因だそうだ。特に夕方には紫度が高まるそうだ。
実際には「紫と言われれば、そう見えなくもない」という感じだった。秋なのに30度近い日だったし、紫外線にあたると黒く変色する眼鏡をかけていたからあまり映えなかったかもしれない。この砂浜の紫の砂は「恋愛に効く」といわれているそうだが、「効く」というのはどういうことだろうか。「効く」は「病気に効く」とか「ブレーキが効く」というような場合に使うのだが、「恋愛」にはどのように効くのだろうか。いずれにしても砂を薬の用に飲まないと効かないのだろうか。

そして近くにあるのが平子古墳群。5つの古墳が集まっている。佐久島にはなんと40以上の古墳があるそうだ。それも多くは単独配置でさらに横穴型。平子古墳群はめずらしく5つの古墳があり、当時の平均年齢を考えれば5個というのは100年ほどの間に古墳を作るほどの実力者の家系がいたということになる。

実際。佐久島だけではなく伊勢湾の出口や三河湾の出口の島にも古墳がある。本来は地元の高校や大学が調査しそうなものだが、高校も大学もこの島にはない。古墳への神秘的な森の小径の整備は地元中学生の手入れだそうだ。案外、島の住民の先祖かもしれない。

そしてとうとう島とお別れ。西港の岸壁には人懐こい猫が待ち受けていた。近づいてき何か人の声のような鳴き声(というか喋り声)を出して話しかけてきた。あいにくネコ語は少ししか理解できないのだが、「この島に飽きた。本土に連れてってくれ」ということらしい。
連れていくことはできそうだが、そもそもネコ語が間違っているかもしれない。

ところが、島々のように見えるのは渥美半島で、ここで見ている方が島なのだから、倒錯的だ。さらに問題は新谷海岸の砂。「紫の砂浜」と言われるそうだ。日本ではここだけ。
どういうことかというと、砂に交じってムール貝の貝殻が細かく砂状に広がっていて、これが紫に見える原因だそうだ。特に夕方には紫度が高まるそうだ。
実際には「紫と言われれば、そう見えなくもない」という感じだった。秋なのに30度近い日だったし、紫外線にあたると黒く変色する眼鏡をかけていたからあまり映えなかったかもしれない。この砂浜の紫の砂は「恋愛に効く」といわれているそうだが、「効く」というのはどういうことだろうか。「効く」は「病気に効く」とか「ブレーキが効く」というような場合に使うのだが、「恋愛」にはどのように効くのだろうか。いずれにしても砂を薬の用に飲まないと効かないのだろうか。

そして近くにあるのが平子古墳群。5つの古墳が集まっている。佐久島にはなんと40以上の古墳があるそうだ。それも多くは単独配置でさらに横穴型。平子古墳群はめずらしく5つの古墳があり、当時の平均年齢を考えれば5個というのは100年ほどの間に古墳を作るほどの実力者の家系がいたということになる。

実際。佐久島だけではなく伊勢湾の出口や三河湾の出口の島にも古墳がある。本来は地元の高校や大学が調査しそうなものだが、高校も大学もこの島にはない。古墳への神秘的な森の小径の整備は地元中学生の手入れだそうだ。案外、島の住民の先祖かもしれない。

そしてとうとう島とお別れ。西港の岸壁には人懐こい猫が待ち受けていた。近づいてき何か人の声のような鳴き声(というか喋り声)を出して話しかけてきた。あいにくネコ語は少ししか理解できないのだが、「この島に飽きた。本土に連れてってくれ」ということらしい。
連れていくことはできそうだが、そもそもネコ語が間違っているかもしれない。