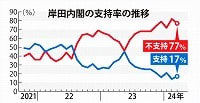2024年3月21日 中国新聞「広場」掲載
岩国市の岩国病院が6月末で産科病棟を閉じ、分娩の受け入れをやめるという9日付山口総合面の記事を読んで驚いた。医療スタッフの確保が難しくなったのが主な理由とある。少子化対策が問われるこの時期に残念でならない。
1884年に創立された歴史ある病院で、わが家に近くお世話にもなっている。その岩国病院など産科がある市内の民間の2医療機関に対し、市が2024年度から補助金を出すという記事を先日読んだばかりだ。それだけに驚きが増す。
国は少子化対策として児童手当や出産・子育て応援給付金といった子どもや親に対する支援の拡充は進めている。だが、子どもを産む環境が整っていなければ少子化は止まらない。それには産科の支援も欠かせないが、対策は進んでいるのか。
岩国病院に行くと、いつも妊婦の方を見かける。院内には生まれた子どもの顔写真も掲示されていて、ほほ笑ましい。この病院の子どもへの思いが絶えることがないように、関係者の努力をお願いしたい。
(今日の575) うぶ声の聞こえし廊下笑みを呼ぶ
岩国市の岩国病院が6月末で産科病棟を閉じ、分娩の受け入れをやめるという9日付山口総合面の記事を読んで驚いた。医療スタッフの確保が難しくなったのが主な理由とある。少子化対策が問われるこの時期に残念でならない。
1884年に創立された歴史ある病院で、わが家に近くお世話にもなっている。その岩国病院など産科がある市内の民間の2医療機関に対し、市が2024年度から補助金を出すという記事を先日読んだばかりだ。それだけに驚きが増す。
国は少子化対策として児童手当や出産・子育て応援給付金といった子どもや親に対する支援の拡充は進めている。だが、子どもを産む環境が整っていなければ少子化は止まらない。それには産科の支援も欠かせないが、対策は進んでいるのか。
岩国病院に行くと、いつも妊婦の方を見かける。院内には生まれた子どもの顔写真も掲示されていて、ほほ笑ましい。この病院の子どもへの思いが絶えることがないように、関係者の努力をお願いしたい。
(今日の575) うぶ声の聞こえし廊下笑みを呼ぶ