本書は、「本」であるが、カテゴリーで言うと「書評」ということになる。書評ということは、加藤氏以外の方の主に近現代史の研究書について、手短かに紹介しているわけで、ここで私がその書評としての本の書評を書くというのは、いかにも重ね着的になってしまう。

著者は安倍政権によって学術会議から追放されたことで有名だが、専門は1930年代の日本歴史。要するに戦争に突入するときの経緯などに詳しい。本書にはやはりその時代を中心として活躍した人の著書や、それらの人を研究した研究書が書評の対象になっている。
全57冊を「国家」「天皇」「戦争」「歴史」「人物と文化」という5章にわけている。
そもそも、日本は戦争で負けたわけなのだから、良きにつけ悪くにつけそういう大失敗に学ぶ必要はあるのだが、氏は思想家ではなく歴史家であるのだから90年前とは異なる政治状況の研究者を現在の政権が毛嫌いしたのはなぜなのだろうと考えながら氏の書評を読んだのだが、特に特定の方向の思想に傾いているようにも読めない。
ただ、取り上げた書籍のそれぞれの著者の目線の違いによって、歴史と言うのは大きく異なるものになるという点は何回か記されている。
ところで学術会議については、政府から独立した立場で運営するべきという意見が強まっているようだが、そういう当たり前の方向に進むはじめたのも、例の暗殺事件からの一連の方向転換なのだろう。

著者は安倍政権によって学術会議から追放されたことで有名だが、専門は1930年代の日本歴史。要するに戦争に突入するときの経緯などに詳しい。本書にはやはりその時代を中心として活躍した人の著書や、それらの人を研究した研究書が書評の対象になっている。
全57冊を「国家」「天皇」「戦争」「歴史」「人物と文化」という5章にわけている。
そもそも、日本は戦争で負けたわけなのだから、良きにつけ悪くにつけそういう大失敗に学ぶ必要はあるのだが、氏は思想家ではなく歴史家であるのだから90年前とは異なる政治状況の研究者を現在の政権が毛嫌いしたのはなぜなのだろうと考えながら氏の書評を読んだのだが、特に特定の方向の思想に傾いているようにも読めない。
ただ、取り上げた書籍のそれぞれの著者の目線の違いによって、歴史と言うのは大きく異なるものになるという点は何回か記されている。
ところで学術会議については、政府から独立した立場で運営するべきという意見が強まっているようだが、そういう当たり前の方向に進むはじめたのも、例の暗殺事件からの一連の方向転換なのだろう。












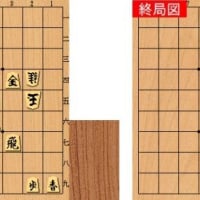




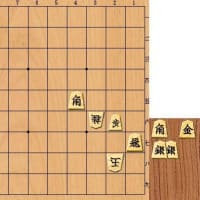


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます