電脳六義園通信所別室
僕の寄り道――電気山羊は電子の紙を食べるか
【八月の落とし物】
【八月の落とし物】

静岡県清水エスパルス通り。
この通り沿いの商店主に陽気なブロガーがおり、いろいろと遠回りに縁があるので、どんな人が書いてるんだろうと店の前を通ったら本人らしき人がいた。
当たり前の話だ。
誰かの落とし物で鼻眼鏡をしたパルちゃん。
妙に似合うのが何ともおかしくてまるで本人の持ち物みたいだ。
いかにもエスパルス通りらしくて微笑ましい。
◉
▼八月末日
確か司馬遼太郎さんが
町というものは泊まってしまうと情が移ると
どこかに書かれていたような気がするけれど、
僕はどんな町でもぶらりと電車から降りたって
ラーメンを一杯食べてしまうと
なぜか昔から縁のあった町のように思えてしまい、
心より胃袋のほうが情的なのかもしれない。

八月末日、午前11時33分。
新富士駅停車中の新幹線こだま542号東京行き車窓にて。
この街に降りたったら訪ねてみたいラーメン屋を
何年か前に何軒か聞いてメモしてあるのだけれど
まだ一度も下車したことがない。
▼放牧豚
仕事で農業系の出版社に行ったら
打ち合わせテーブルの上に
宮城県の農家がつくった
「放牧豚ソーセージ」が届いたらしく
社内試食用におかれていた。
わざと目にとまるように物欲しげに眺めながら
ダメ押しで写真を撮ったりしていたら
「どうぞ食べてみてください」
と声がかかった。ラッキー!

「美味しいです」
と答えてウソはないけれど
放牧豚だから美味しいとわかるためには
ソーセージソムリエと呼ばれるくらいにならないと無理だ。
放牧豚ロースのスライスをフライパンでサッと焼いて
生醤油をつけて炊きたてご飯と一緒に食べたら
きっと放牧豚ならではの美味しさがわかるのではないかと思うけれど
良く歩いている牛の肉は硬いと言うから
放牧豚もソーセージにでもしないと硬いのかな。
▼梨と辛味
昔、飲み友だちと仕上げに食べた冷麺に
梨が浮かんでいたのを思い出して
短冊切りにした梨をハクサイキムチとあえてみたらとても美味しい。
韓国には梨の実入りのキムチが存在するという。
母は昔から辛味調味料が好きで
唐辛子も露店で調合して貰うのが好きだった。
新潟名物『かんずり』や大分名物『ゆずこしょう』を
「あんた、これたべたことある?」
と嬉しそうに食べさせてくれたのも母なら
「さいきんはこれなしじゃだめ」
と言ってタバスコを生まれて初めて教えてくれたのも辛い物好きの母だった。
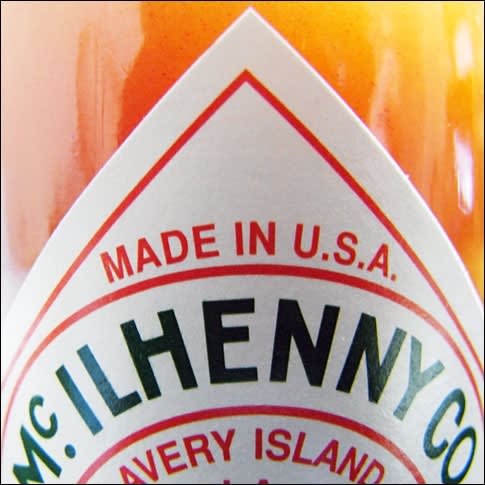
最近はタバスコは当然として『かんずり』や『ゆずこしょう』までも
大きなスーパーに行けばたいがい売られているけれど、
食欲がなくなって何も食べられなくなった母に
「おかあさん、これつかったことある?」
と教えたら大喜びして食が弾んだ沖縄名物『コーレーグース』は
まだスーパーには定着していないので残念。
▼栞のテーマ
この夏は新潮文庫ばかりを読んでおり、
新潮文庫は感心にちゃんと栞(しおり)としていまだにリボンがついている。
この紐状の栞のことを業界ではスピンといい
「今度の本スピンつけますけど色は何色にしますか?」
と出版社から問い合わせがあることがある。

▲スピンの見本帳
なぜリボン状の栞をスピンと呼ぶかについては諸説あり、
諸説を突き詰めたところで業界の現場からでた
不思議な日本語の謎ときは真相に迫れないことが多い。
真相に迫れない曖昧な領域をテーマにした議論に加わるのが苦手で
どうして苦手かを説明するのも難しいというのが
曖昧なことをあえて議論することの魔だと思う。
▼寅と歌子のいる駒込駅
映画「男はつらいよ」第9作「柴又慕情」(昭和47)で
寅が独身時代の歌子に出会ったのは北陸金沢だった。

第13作「寅次郎恋やつれ」(昭和49)で
夫と死別した歌子と思いがけず再会したのは2年後の津和野だった。

そしてまた寅と歌子が駒込駅で再会していた。
▼地球屋
地球屋という文字を見て少しドキッとした。
インターネットで検索すると
地球屋は飲食店の名としてたくさんヒットする。

この地球屋も食べ物屋かと思い
何を食べさせる店かなと
横の玄関に回って店内を見たら
本当に地球自体を小さな単位で切り売りしているのでもっとびっくりした。
▼古書の値段
古本というのは見返し部分に
手書きの価格が書かれていていくらで買ったかわかるものがある。
平凡社選書の上製本で井上鋭夫という人が書いた
『山の民・川の民――日本中世の生活と信仰』
という本は古本の売値900円だったことがわかる。

以前から読みたいと思っていたので東大正門前の古本屋で
見つけたときは嬉しくて
値段も見ないでレジにもって行ったのを覚えている。
定価1600円の本が900円なので安かったと思うのだけれど
古本屋の達人である友人に言ったら笑っていた。
▼ビールと忘れ物
見慣れないCDが出てきたので何かと思ったら
いつだったかヱビスビールを買った際に
CMのサウンドトラックを集めた非売品を貰ったのをかろうじて思い出した、

YEBISU THE HOP CM Tunes Collection といい「第三の男」を
高田漣(ワイゼンボーン)、近藤房之助(クロマチックハーモニカ)、
クラムボン(マンドリン/ボーカル/ボンゴ)、畠山美由紀/青柳拓次(ボーカル/アコーディオン)、
マイク眞木(ウクレレ付きギター)、HER SPACE HOLIDAY(ボーカル/鉄琴)
がカバーしたオムニバスになっている。
ああこんなCMがあったなぁと微かに思い出したけれど
放映直後に聞いていたらもう少し泡立ちがよかったのかもしれない。
▼モートル
東京下町の工業地帯にはモートルの店がある。
静岡県清水で瓦製造業を営んでいた祖父母の家の
作業場の隅にも一台大きなモートルがあった。
毎朝電気のスイッチを入れると大きな音を立てて始動し
天井に渡された長い鋼鉄製シャフトが回転し
そのシャフトに長いベルトを掛けたり外したりして
さまざまな瓦製造器具を動かすのだった。

たった一台のモートルは何人分にもあたる大切な労働力であり
農家でいえば使役のための牛馬のようなものであり、
モートルが壊れたときはこういう店に入院させて直していた。
▼新規開店
新規開店で午後3時にまだ行列のあった札幌ラーメンチェーン店の
数軒先でもうひとつ新規開店があった。
とっさにシャッターを切ったらなぜか盛大にブレている。

通りすがりにちらっと見たら鯛焼きと焼き団子の店らしい。
この前まで行列のあった隣の10円まんじゅうに客の姿はない。
ラーメン屋にしても鯛焼き団子屋にしても行列が消えたあと
また近所に新規開店の行列ができて
客に忘れ去られる日がくるのではないかという恐怖を実感しているかもしれない。
▼すり身揚げの名前
北区西尾久の『九州屋』。
福岡県久留米市出身の友人は魚のすり身揚げを「てんぷら」と呼んでいた。
神田神保町の居酒屋の名物オヤジは「つけあげ」と呼んでいた。
東京では魚のすり身を油で揚げたものを「さつまあげ」と呼ぶが、
この店ではそれを「あげかまぼこ」と呼ぶらしい。

Wikipediaによると中部地方ではそれを「はんぺん」と呼ぶとあるが郷里はどうだろう。
中部地方の清水では「はんぺん」といえば黒はんぺんのことを指す。
興津に黒はんぺんを揚げたものを名物にしている魚屋があり、
黒はんぺんを揚げると味は薩摩揚げそのものだが「あげはんぺん」と呼んでいる。
【ダメ押し的おまけ】
清水では黒はんぺんにパン粉をまぶして揚げたものは「はんぺんふらい」と呼んでいるが
はんぺんフライにソースをかけたのを食べながらビールが飲みたいなぁと思う。
▼狐と鍵
お稲荷さんの狐がどうして蔵の鍵をくわえているのか
見るたびに気になっていた。

北斗七星は世界中でいろいろなカタチにたとえられるけれど
日本では蔵の鍵のカタチとして見られたそうで
その北斗七星は狐の守護星なのだという。
▼川崎屋食品店
東京都荒川区「はっぴいもーる熊野前」にて。
昭和三十年代の食品店というのは
東京でも郷里静岡県清水でもこういう顔をしていた。
東京下町ではこういう店に「三河屋」の屋号が多く
酒や味噌醤油のある食料品店を
たとえ店名が三河屋でなくともなぜか三河屋と呼んでいた。

「一般的には醸造されたものを扱う店(一般に酒屋と呼ばれる)の俗称である。酒などを扱うことから、ジュースなどの清涼飲料水、牛乳などの飲料全般、調味料、乾物などの食品を扱う店も多い。1960年代まで、味噌や醤油といった食品は現今のようなパッケージではなく、店内に樽が置かれてその都度量り売りがされていたのも特徴である。」「その由来は江戸時代の十組問屋に起因する。味噌、醤油等を江戸市中で扱っていた組合であるが、組合には醸造業の盛んな三河出身者が多かった為、各々が三河の入った看板を掲げ、これが庶民の代名詞となった。」(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
東京の三河屋はやがて小さなスーパーマーケットになって
大手との競争に敗れて消えていったものもあるし、
命脈を保ってセブンイレブンになったものもあったように思う。
▼墜落現場
東京都荒川区東尾久。
わが国初めての航空機事故である
杉野治義陸軍工兵中尉(27)の殉難を記録した石碑がある。

この墜落現場は当時は一面の水田だったというが
今は「はっぴいもーる熊野前」という商店街になっている。

今から20年以上も前、「天才・たけしの元気が出るテレビ」の
商店街復興プロジェクトとして
顔がビートたけし、からだが猫の
奇っ怪な招き猫が飾られて話題になった商店街。
| « 前ページ |





