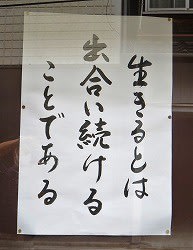我が家の夏が完全に終わった。そんな大それたことではないがひどい曇天の朝、朝顔が一輪咲いた。それは絡んだ蔓のトップで真上を向いたていた。10輪くらいから1輪2輪と咲く数が少なくなってきていたので、もしや最後の一輪かと撮っておいた。それは予想通りの咲終わりで、最初の開花から108日目の朝だった。
今夏は記録に残る、経験がない、そんな異常な暑さで熱中症を患う人も多かった。また、新型コロナウイルス禍で夏の各種行事は中止が続いた。子どもらの楽しみな夏の移動はストップした。高校生の夏の全国大会は姿を変えこじんまり開催となった。盆の民族大移動見送りで関係の深い産業が大巾減収となった。
そんな中で、我が家の朝顔も暑さが堪えたのか一時疲れ気味になった。咲き終わった蔓を切り取ってみろ、という教えを実行すると気持ちのせいか元気回復となり、その終焉は初めに記した通りになった。毎朝、前日咲いて役目を終えしぼんだ花を取り除いていた。取り除きながらその数を確かめたある日は何と150個だった。
朝顔について私のブログの影響を受け「この夏は朝顔を育ててみました! 日々の成長ぶりに愛着がわきました。どこにも出掛けない夏でしたが、おかげさまで楽しく過ごせました♪ ありがとうございました」と、在京の人からコメントをもらった。10本ほどの苗から伸びた蔓はどのくらい伸びていたのだろう、そんなことを思いながら後片付けをした。ちょっと広がった空間に夏の煩悩が抜けていった。