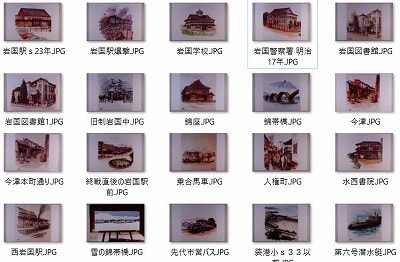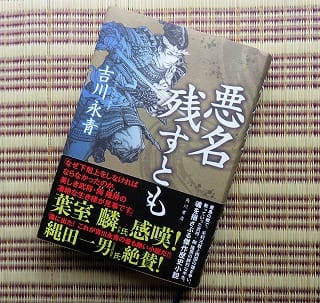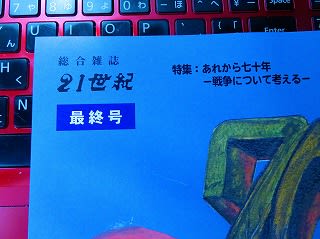活気を失って寂しく成るさまを「火の消えたような」と言う。車で動き回る知人は表通りばかり走る。その表通りに並行する道路、その昔は銀座通りとも呼び賑わった商店街、そこを久しぶりに通り感じたことは「火の消えた通り」だったと話す。
呉服屋、本屋、靴屋、時計店、美容院、果物屋、ガラス店、家具店、薬屋、散髪屋、陶器店、自転車屋、履物屋、布団屋、傘屋など、子どものころの記憶にはあるが、今は撤退や閉じてしまった店の数々を知っているだけに、知人の昔ながらの表現に改めて納得する。商店街の中央に小さいけれど銀行の支店もあった。
「3月末を持ちまして閉店いたします。長らくごひいきになりありがとうございました」と店頭に閉店の挨拶が張り出された。少ない人通りに拍車がかかる。最近70年続いた店を閉めた同期の話だと、大型店の品質に勝る商品も個人商店という区分けで商売にならない、と悔しい胸の内を話してくれた。
そんな通りのある家の玄関先に、早春の花木として、梅と同じに庭や生け花に重宝される山茱萸(さんしゅゆ)の黄色い花が玄関横に活けられている。ここの家はかっては大きな店構えだった。山茱萸の花は別名「春黄金花(はるこがねばな)」と呼ばれ早春にふさわしい花という。行きかう人は少ないが、足を止めて眺め笑みして去る人に活けた人の思いが伝わる。人情が残る通りの昼下がりだった。