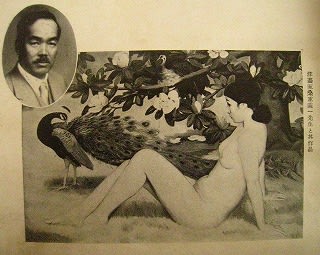岩国特産品の一つに「岩国れんこん」がある。おさらいをしてみよう。室の木の篤農・村本三五郎が、岡山から備中種を持ちかえり、これを門前の石代に植えたのが始まり、これから広がり門前バスといった。1811(文化8)年に藩営として始まった。(岩国検定テキスト参照)。この歴史あるレンコンは子どものころからおかずとして食べている。
噛み切るときほっこりとし、噛むとしゃきしゃきとする歯触りは何とも言えない。レンコン自体の澱粉質の粘りで糸を引くこともよく知られている。産地としては全国5位までに入る。レンコンの穴数は一般的には8つといわれるが、岩国れんこんは外周の穴数が一つ多い。藩主・吉川家の家紋にも似ており地元の自慢でもある。
レンコンの穴は何のためにあるか、その問答はべつの機会にする。岩国のレンコン田で有名な尾津地区で珍しいレンコンが話題になっている。それは、なんと穴が23個もあるものが収穫された。写真で見ると楕円形の外周に17個、中央部に直線状に6個、人工的に細工したかのように美しい。専門家は「10個はたまにあるが20個以上は聞いたことがない」という。
盆前のハスの花の出荷に続いて、これから歳暮時期に向けて重労働といわれるレンコン堀が始まる。レンコンは「見通しがいい」ということから縁起物として贈答やおせち料理に使われる。23個もあれば明るい向こう側が見えるかもしれない。それを、知ってか知らずか、レンコン田は収穫される前の静か休息の時を過ごしている。