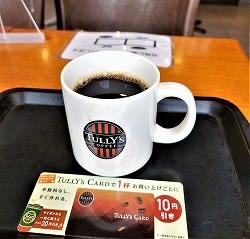丁寧にいえば「お昼ごはん」、昼飯や昼食ともいう。また、弁当ともいう。小学校低学年初めころは、今のように立派で豪華なものではないが、アルミの弁当箱に詰めていた。途中から給食が始まり、卒業まで弁当といえば遠足か運動会くらいになった。竹の皮にむすびを包むこともあった。
中学と高校では給食は無く弁当を6年間持参した。高校を卒業、給与をもらい始めても弁当持参は続く。3交替という勤務、当時はほかの手段は思い浮かばなかった。そこでは、今では若い人に敬遠される仲間意識、この醸成に役立った。そこでの社会経験に富んだ会話は面白かったことを思い出す。
工場の福利施策充実の一環で食堂が完成、そこから配送弁当方式が採用され希望者は交替でも暖かい弁当が食べれた。何歳になっても食べることに旺盛でないと活力が乏しくなる。高齢層に深入りするにつれそう感じる。過ぎたるは何とか、そこだけは心掛けて口にする。
今日、注文してあるからということで久しぶりコンビニ弁当を食べた。量も味も丁度良かった。スーパーで並ぶ店の弁当、時には全国駅弁売り、どれも見た目は買ってもらえる、という作り方で手にしたくなるように作られている。弁当持参、だんだんに影が薄くなっていくように思えるが、家族の絆、職場仲間とのふれあいなどに活かされる食べ物、そんなことを思いながら箸を運んだ。
(今日の575) 幕の内力士が食べりゃ何個いる