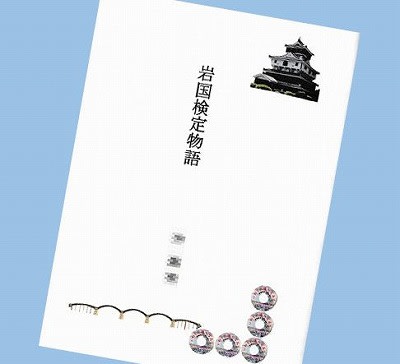下駄箱を掃除していた妻が「まだ履きます?」と取り出したのは下駄、何十年も仕舞われたままになっていた、というか、その存在を忘れていた。ということは浴衣を着て外出してないということだ。浴衣を着たら下駄を履く、この気づきは古い人間そのままらしい。今の人らは浴衣に「スニーカー」「つっかけ」「サンダル」などが主流という。もしかして下駄が履けないのかもしれないと思い直す。
下駄は「鼻緒があり底部に歯という凸部のある日本の伝統ある履物。凸部は地面に接しそのため雨の日には足の濡れを防ぐ。鼻緒を通す3つの穴を眼と呼ぶそうだ。絵文字の顔を逆にした形で足をのせるのが悪い気がする。足の親指と人差し指の間に鼻緒を挟んで履く。人差し指と中指の間に挟む履き方もあったそうだ。下駄は草履とは違い乾いた心地い良音をたてる。
下駄と出た時「カランコロンと下駄で行く」という錦帯橋にまつわる短いフレーズを思い出した。もしやと、1972(昭和47)年11月出版(岩国図書館発行)の「岩国の昔話と歌謡」を繰ってみると載っていたのが次の歌。歌に記憶は無いがどこかで聞いた短いフレーズが耳に残っていたのだろう。下駄で錦帯橋を渡った記憶はないが、カランコロンという音の表現が何ともいえない和の情感を誘う。サーサは人を誘い促す語という。
「からんころん節」 作詞:野口雨情、 作曲 岡村素芳、 編曲 吉田矢健治(岩国市出身)
♪ ハア 誰に逢うやら あの錦帯橋を カランコロンと下駄で行く カランコロンと サーサ橋の上
ハア 立つは河霧 あの岩国ゃ夜明け 山は城山 ほのぼのと カランコロンと サーサ橋の上
ハア 錦川すじ あの鮎は瀬をのぼる 流すいかだは 瀬を下る カランコロンと サーサ橋の上
ハア 錦川原も あのまだ夜は夜中 鳴いてくれるな川千鳥 カランコロンと サーサ橋の上
ハア 吉香公園 あの中国一の 春は桜の花となる カランコロンと サーサ橋の上 ♪