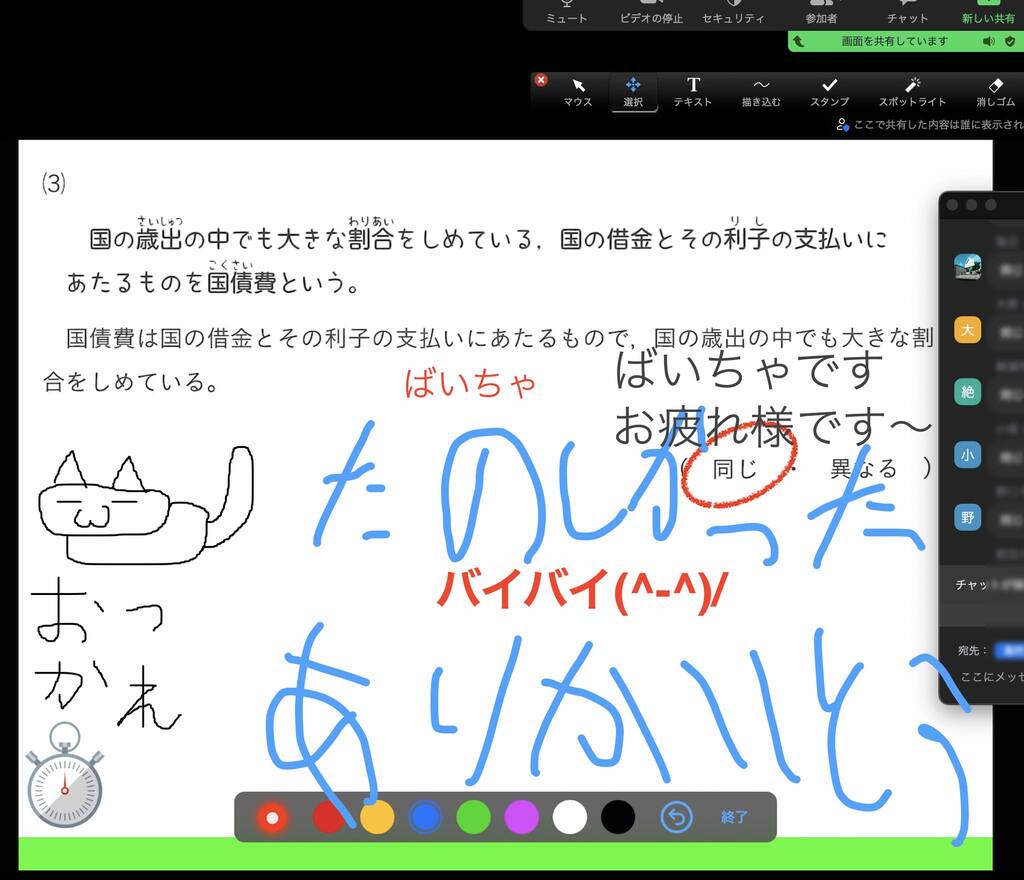なんと今年で22年度目ですよ。
前職で11年務めて、独立してから11期目なので、ちょうど半々になる。
前職で11年務めて、独立してから11期目なので、ちょうど半々になる。
中日の涌井より長いよ。ヤクルト石川や西武中村には1年負けるか。
バンド活動の傍ら、とりあえず、キライじゃない仕事で食いつなぐか…
バンド活動の傍ら、とりあえず、キライじゃない仕事で食いつなぐか…
なんて思いながら気軽にバイト始めたのが、まさかこんなに続くとは。
あまつさえ独立して自分の教室まで構えていようとは。
「人生は第二希望でうまく行く」
そんな言葉をどこかで聴いたことがある。
大谷翔平や藤井聡太にあきらめざるを得なかった第一希望があるとは思えないが、
大谷翔平や藤井聡太にあきらめざるを得なかった第一希望があるとは思えないが、
古くは馬場が(ホントに古いな!)巨人の投手だったのが、
風呂場での転倒事故をきっかけにプロレス入り。
猪木も移住先のブラジルで陸上選手だったのが、
そこで力道山にスカウトされ…と、それなりの説得力も感じられなくもない。
そういや、大むかし僕は関西在住で、灘が第一志望ということになっていた。
けれど、それは親父がそう言ったからであって、
僕の心はとうに、近所のとある大恩人のおかげで、120%麻布だった。
麻布に合格をもらった瞬間、もう東京に引っ越す気満々で、
ウキウキ荷造りなんか始めちゃってたし、
その後(当時は麻布が2月、灘は3月だった)の受験勉強にはまったく身が入らず、
灘は見事に落ちた。
それを完全に見越していた塾の恩師は、教室の空気を弛ませる僕を、
麻布合格のその日に「退塾」にしたが、慧眼だったとしか言いようがない(笑)。
考えてみれば、大袈裟ではなく僕の人生の転機は「塾」にあった。
窮屈な小学校に屈託していた僕を、
自由で寛容な最高にフィットした中高に送り出し、
大袈裟ではなく人生を啓いてくれたのは塾だった。
僕の塾講師としての原点はまさにここで、
僕の塾講師としての原点はまさにここで、
「公立小中学校の、管理ありきで理不尽な環境にアジャストできずに苦しんでいる子に、環境さえ変えればいくらでも世界は開けることを教え、後押ししたい」
という思いはずっと変わらない。
ただ、始めたときはまさかこんなに続くなんて思ってもみなかった。
自分はメジャーなアーティストになるんだからと、
無理に自分に思いこませていたようなところもあった。
むしろそれを真面目なカタギ暮らしができないことの言い訳にして、
三十までは本当に無責任に好き勝手に生きていた。
そうなることを完全に見越していた大学時代の彼女は、
卒業とともに僕を「整理」したが、これまた慧眼だったと言うほかない(笑)。
そんな僕だけれど、塾の仕事は始めてみると実に楽しくて、真面目に勤めた。
もともと教育には興味があったし、子供の相手をするのも好きだった。
世話焼きで、子供を喜ばせるのが好きで、
子供と一緒になって大人の文句を言うのも好きで、
大人の振りかざす「あたりまえ」が嫌いで、それでいて妙に一本気だったりもして。
仕事が仕事に思えないほどに楽しく、生徒も保護者も喜んでくれてやりがいがあった。
ちょうどその頃、バンドではおよそ褒められる・認められるようなことがなくなり、
もう何かというと貶されてばかりだったので、モチベーションは逆転。
30歳を機に正式に転職を決める。
のちにいわゆる「会社の会社たる所以」に辟易して離職はするが、
現場のやりがいとはまったく別のこと。
なんせ飽きっぽいことでは人後に落ちない僕が、こんなに長く続けられているのだ。21年だ。バンドですら7年半で瓦解したというのに。
してみると、実は第二希望なんかではなかったのかもしれぬ、と思い至る。
第一希望はバンドでの成功…かのように「思いこんでいた」だけで、
自分でも気づかなかったけれど、実は自分の適性だとか得手不得手もコミで考えると、
こちらが真の第一希望だったのかもしれないという気さえしてくる。
自分で自分自身を見誤っていたのだろう。
実力や人気がということ以上に、自分が本当にそれを好きなのかどうかという点を。
人生はわからないもんだ。
結婚だって子供だって、自分には向いていないと思いこんでいた。
極めて平凡な、ごくあたりまえにある幸福が、
自分にとってこんなにも大切なものだなんて、まったく想像していなかった。
つくづく、自分を一番知るものは、いまの自分ではないのだなあ。
かといって誰に聞けばいいのかもわからないが。
「士は己を知るもののために死す」というが、
それだけ自分の適性を見抜いてくれる存在は貴重だということか。
いずれにせよ、数年あるいは数十年経てば、
自身でもしみじみと実感できるときが来るのよね。
あれは正解だった、これは誤りだった、
今さら何を言ってももう遅いけど、という時期になって。ああ人生。
幸いにも、なんとなく正解だったかな?と振り返れる程度には、
充実した塾講師人生だったと思う。
加えて最近で、良い意味で肩の力が抜けてきた感じもする。
かつては教え子たちに思い入れが強くて、よく言えば熱量高めの、
悪く言えば肩入れしすぎて独善的な傾向があったようにも思う。
昨年春に送り出した卒業生たちは傑物揃いで、
小4からずっと可愛がってきた、とても思い入れのある代だった。
才気にあふれ、慕ってもくれる彼らの目標を叶えたいと、
僕も全身全霊で取り組んだし、彼らも十二分に応えてくれた。
そして僕の教室史上最強といってもいいくらいの実績も出た。
そんな彼らを送り出したあと、燃え尽きたような感覚もありつつ、
それでもいつもと同じ春を迎えて、ふっと力が抜けた気がする。
別にその後の生徒たちがどうでもよくなったわけではなくて。
過程についても結果についても、ようやくフラットに受け止められるようになった。
変に他人に期待しすぎる悪い癖が抜けた。
期待なんてものは自分勝手なもので、百害あって一利なしだ。
それを表に出すまいと、いままではフラットにしなきゃしなきゃと、
意識して抑え込んでいたような感じがあった。
年齢のせいか、キャリアのせいかわからないけど、
自然と落ち着けたような境地にいま、僕はいる。
やはり、ベストよりもベター、
第一志望ではなく第二志望くらいの気の持ちようがいいのかもしれぬ。
力みまくって、期待して、落胆して、歯を食いしばって立ち上がって…
それもまた人間くさい熱量に溢れていて悪くはないけれど、
来年五十になる僕が、二十代・三十代の頃と同じ方法論でいいはずはない。
…なんて言いながら、ふと気がつくとまた入れ込んで熱くなっているのだろうなあ。
身に染みついたものはそう簡単に変わらないし、
自分で言うほど自分は自分をわかっちゃいない。
結局変わらずに、喜怒哀楽のわかりやすい、
「教師のガラじゃ〜ない〜、カネ〜のためだ〜と言いながら〜、子供相手に〜人の道〜、人生などを説く〜男」として、
一言も二言も多い塾講師のままかもしれない。
あっさりと辞めて、まったく別のことを始めてたりして。
よくコンサル的な文脈で「10年後の自分を思い描く」的なことがいわれるが、
僕はそれが何ひとつ当たったことがない。
生まれてこの方、まさかまさかの連続。
10年先などわかるわけないし、
当たり外れ以外の副次的な効果とされるものも含めて、
そんなこと考えるだけ無駄だとさえ思う。
むしろ先の読めない人生だったことを誇りに思うくらいだ。
大谷翔平の未来予想ツリーなんかも、案の定もてはやされているけれど、
稀に見る大成功者の手法を後付け気味に猿真似したって、
自己満足以外には何も得られない。
むしろ凡人は失敗に学ぶべきで、その点僕は反面教師たちのおかげで、
たとえば犯罪やら薬物やらといった、決定的に道を踏み外すようなことはなかった。
ベストでなくとも、その時々のベターの積み重ねでいい。
取り返しのつかないような、ワーストにさえならなければいい。
それくらいの気の持ちようがいい。
子供たちにもそう教えてやりたいと思う。
さて、僕の10年後は。
元気に家族と仲良く生きていられさえすれば、それで充分だけどね。
ベターな健康への小さな努力の積み重ね、これを目標にしようかな。