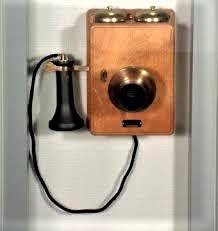記憶から消えかかりそうなポッケトベル、略して「ポケベル」と呼んだ。今風に言えばスマートホンを「スマホ」、携帯電話端末を「ガラケー」と呼ぶ。これはガラバコス化した端末の通称になった。ガラバコス化した理由は、国内で生産された携帯は機能や性能があまりに独特で世界基準から外れ海外進出が困難だったという。
携帯電話の無い時代、会社からの緊急呼び出し、あるいは社外にいる同僚に至急な連絡事項が発生した時などに、あらかじめ設定している固定電話に掛けたりかけさせたりする約束で持っていた。何度か受信したり発信したが、ゴルフ場は山間地のためか応答の無いこともあり気があせった記憶はあるが、当時は便利な連絡手段だったが、携帯電話に変わりベルトからさよならした。
そんな思い出あるポケベルが今日でいよいよサヨナラという。現在は関東地区で1500人の利用者数というが、これからの通信連絡手段をどうされるのだろうか、人ごとではあるが気に掛かる。現役時代、夜は枕元に置いて寝たことを思い出す。固定電話に連絡するより、情報を本人に届けるには確実な手段だった。
ポケベルが高校生など若い世代の連絡手段して重宝されたという。言葉を数字に置き換えて楽しんだそうだ。「0833はお休み」「10105は今どこ」「49は至急」などスマホの化け文字と変わらない使われ方に、若い人らの感覚はいつの時代も変わらないようだ。また一つの時代が終わり5Gの時代に入る。さてスマホはどんな進化を見せるのだろう。