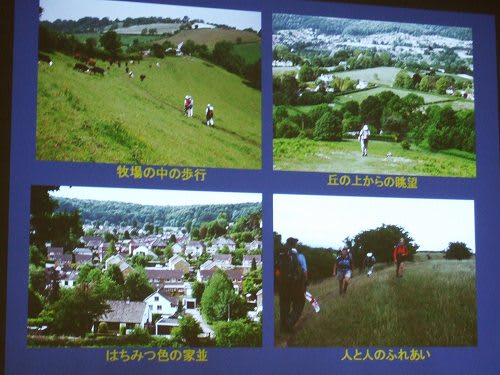今日で、今年も半分経過してしまいました。最近は1週間が
すぐに来て、ひと月があっという間に過ぎてしまいます。
========================

2006年11月25日(土)朝、高知県土佐市の浦ノ内湾東端
に面した民宿土佐を出て、宇佐大橋を渡って36番青龍寺(しょ
うりゅうじ)へ向かいました。
青龍寺でのお参りを済ませ、預けた荷を受け取るため民宿に
戻ります。
行くときは薄暗かった宇佐大橋もすっかり明るくなっていま
した。橋の上から見る浦ノ内湾には、釣り船らしい小舟がたく
さん浮かんでいます。

戻り終えて西側から見る宇佐大橋。この橋は欄干が低くて、
何だか海に落ちそうに感じましたが、お遍路をされた方、いか
がでしたか。

民宿で、預けたザックを受け取り、今回は初めての浦ノ内湾
北岸沿いの県道23号を西に向かいます。
高知県水産試験場の先、灰方崎を回ると、小さい港に漁船が
数隻並んでいました。

県道はこの先、コの字形の湾を下から右へ回るようにして、
対岸へと進みます。
コの字形の湾の最奥部、浦ノ内灰方からは、対岸の山が波
間に影を落としているノが見られます。

湾の一番北側にある浦の内小の近くには、何の養殖か分かり
ませんが、いかだが浮かんでいました。

浦ノ内湾の西端に出て、さらに仏坂を越えて洲崎港に下り、
須崎市の市街地を抜けました。
道の駅「かわうその里すさき」の先から高みに上がり、2つ
のトンネルを抜けると、南側の湾が見下ろせます。

この日の宿は、ここを下って間もない、JR土讃線安和(あわ)
駅に近い民宿あわでした。
翌日は集中豪雨の中、国道56号を走るトラックにさんざん水
しぶきを浴びながら37番岩本寺宿坊にたどりつきました。
次の11月27日(月)、岩本寺を出て半日余り、伊予木川沿い
を下って黒潮町(旧大方町)に入りました。
佐賀の町並みを抜けると、「鹿島が浦」と呼ぶ湾を半円形に
上がって行きます。

このあたり一帯は、「幡多十景」と呼ぶ景勝地で、土佐佐賀
大規模公園佐賀地区。この先に、湾を見下ろす遊歩道もついて
います。
すぐ近くからは北に、いま通過してきた佐賀の町並みが見下
ろせました。

眼下に見えるのは、幡多十景の気持ちよい展望。

波洗う岩礁の上には、釣り人もいるようです。

国道56号を進むのですが、歩道もあり、天気も回復し、
このあたりは、気持ちよい展望を楽しみました。

この日は黒潮町の民宿日の出泊。翌11月28日(火)も、
好天の朝を迎えました。
その名のとおり、民宿日の出から見る太平洋の日の出です。

日の出から10分ほどの6時58分に、民宿日の出を出発
しました。民宿から間もない、浮鞭(うきぶち)海岸です。

この日は四万十川を渡り、人気の民宿・久百々(くもも)を
目指しました。 (続く)
すぐに来て、ひと月があっという間に過ぎてしまいます。
========================
2006年11月25日(土)朝、高知県土佐市の浦ノ内湾東端
に面した民宿土佐を出て、宇佐大橋を渡って36番青龍寺(しょ
うりゅうじ)へ向かいました。
青龍寺でのお参りを済ませ、預けた荷を受け取るため民宿に
戻ります。
行くときは薄暗かった宇佐大橋もすっかり明るくなっていま
した。橋の上から見る浦ノ内湾には、釣り船らしい小舟がたく
さん浮かんでいます。

戻り終えて西側から見る宇佐大橋。この橋は欄干が低くて、
何だか海に落ちそうに感じましたが、お遍路をされた方、いか
がでしたか。

民宿で、預けたザックを受け取り、今回は初めての浦ノ内湾
北岸沿いの県道23号を西に向かいます。
高知県水産試験場の先、灰方崎を回ると、小さい港に漁船が
数隻並んでいました。

県道はこの先、コの字形の湾を下から右へ回るようにして、
対岸へと進みます。
コの字形の湾の最奥部、浦ノ内灰方からは、対岸の山が波
間に影を落としているノが見られます。

湾の一番北側にある浦の内小の近くには、何の養殖か分かり
ませんが、いかだが浮かんでいました。

浦ノ内湾の西端に出て、さらに仏坂を越えて洲崎港に下り、
須崎市の市街地を抜けました。
道の駅「かわうその里すさき」の先から高みに上がり、2つ
のトンネルを抜けると、南側の湾が見下ろせます。

この日の宿は、ここを下って間もない、JR土讃線安和(あわ)
駅に近い民宿あわでした。
翌日は集中豪雨の中、国道56号を走るトラックにさんざん水
しぶきを浴びながら37番岩本寺宿坊にたどりつきました。
次の11月27日(月)、岩本寺を出て半日余り、伊予木川沿い
を下って黒潮町(旧大方町)に入りました。
佐賀の町並みを抜けると、「鹿島が浦」と呼ぶ湾を半円形に
上がって行きます。

このあたり一帯は、「幡多十景」と呼ぶ景勝地で、土佐佐賀
大規模公園佐賀地区。この先に、湾を見下ろす遊歩道もついて
います。
すぐ近くからは北に、いま通過してきた佐賀の町並みが見下
ろせました。

眼下に見えるのは、幡多十景の気持ちよい展望。

波洗う岩礁の上には、釣り人もいるようです。

国道56号を進むのですが、歩道もあり、天気も回復し、
このあたりは、気持ちよい展望を楽しみました。

この日は黒潮町の民宿日の出泊。翌11月28日(火)も、
好天の朝を迎えました。
その名のとおり、民宿日の出から見る太平洋の日の出です。

日の出から10分ほどの6時58分に、民宿日の出を出発
しました。民宿から間もない、浮鞭(うきぶち)海岸です。

この日は四万十川を渡り、人気の民宿・久百々(くもも)を
目指しました。 (続く)