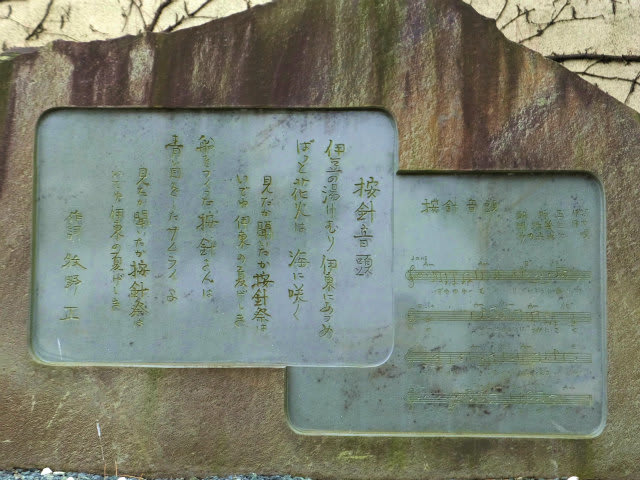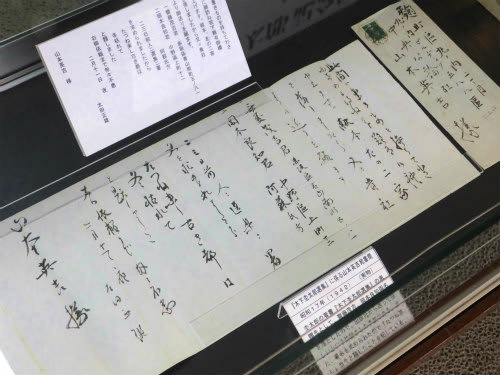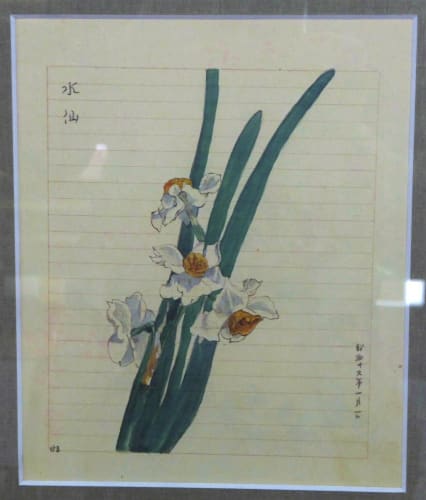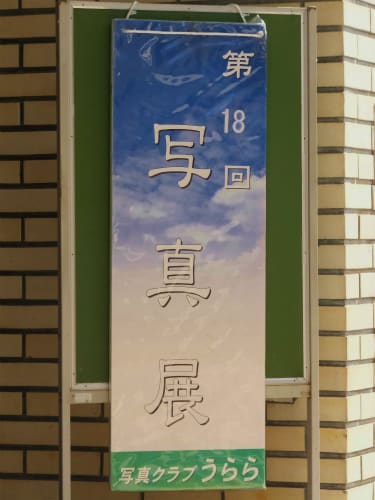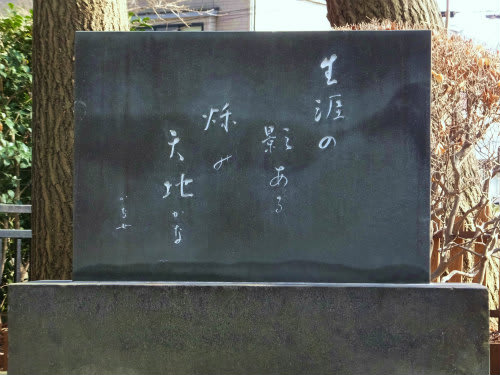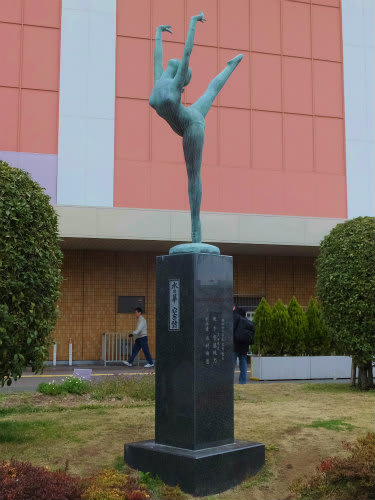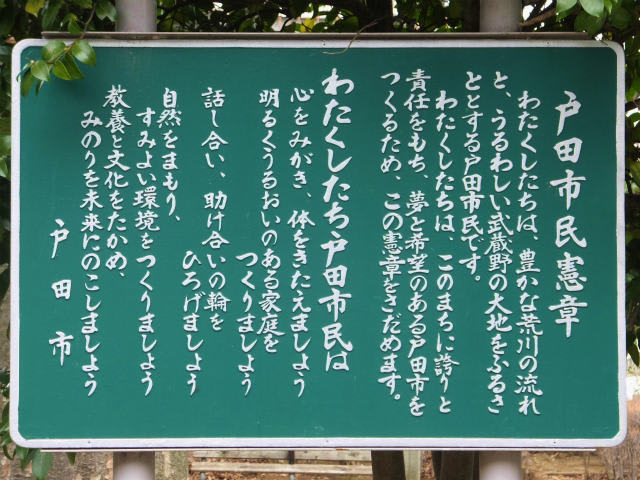2015年3月30日(月)
そろそろ樹齢150年の金仙寺(こんせんじ)のシダレザクラが見頃になったかなと、
今日は市内ウオーキングの距離を少し伸ばして、市の西郊、三ヶ島地区の金泉寺まで出か
けました。
早稲田大学所沢キャンパスの入り口付近にも、シダレザクラの古木のある寺、常楽院が
あるので、まずはそちらに立ち寄ってみたら、もう少しで満開というところでした。


早稲田大学所沢キャンパスの北側を回り、その西側台地にあるのが金仙寺です。石段を
上がって行くと、まず目に付いたのは左手のハクモクレンの高木。

市内のほかのところは、ハクモクレンは盛りを過ぎているのですが、ここはちょうど見
頃でした。

本堂の前のシダレザクラも、間もなく満開というところ。明後日からは曇や雨模様の予
報からすると、今日明日が眺めるには一番よいかもしれません。




シダレザクラの下にも、色々な草花が植えられていて、花を競っていました。
まずはショカッサイ。

ハナニラもあちこちにありました。

東側のがけ際では、ミツマタなど4色の花の饗宴。

この位置からは3色


クリスマスローズも何色かの花が咲いています。


もう一度シダレザクラを見上げて。


ソメイヨシノはまだ5分咲き前後でしょうか。

本堂の西に回ると、墓地の隅ではハナモモの若木が満開に。

その先の畑は、いろいろな花が植えられていて、見頃の花がたくさん見られます。

わが家の庭にも咲いているムスカリ。

毎年描かれる花文字。今年は「〇(まる)い心で」と描かれているようです。

そばのハナモモ。

この細い枝に咲く花はなんだろう?

寺の駐車場の南側斜面。

本堂の左手には、もっと色濃いミツマタがあったのですが、今年は無くなっていました。

寺の西側の高台は、比良の丘という好展望地ですが、ここにはいろいろな花が咲き競っ
ています。

真っ赤で色鮮やかなのはボケの群落。

桃はいろいろな花が並んでいます。



まさに花の饗宴。





レンギョウ



この木だけ、やわらかな若葉の彩りを見せていました。

金仙寺の西側入り口付近に戻ります。

北側の道路に回ると、本堂裏手には少しだけでしたがカタクリが。


黄色い花のカタクリは初めて見ました。

もう一度境内に戻り、サクラの花を見上げて。



十分眺めたので帰路につくことに。わが家からは往復12㎞の市内ウオーキングでした。
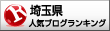 埼玉県 ブログランキングへ
埼玉県 ブログランキングへ

にほんブログ村
そろそろ樹齢150年の金仙寺(こんせんじ)のシダレザクラが見頃になったかなと、
今日は市内ウオーキングの距離を少し伸ばして、市の西郊、三ヶ島地区の金泉寺まで出か
けました。
早稲田大学所沢キャンパスの入り口付近にも、シダレザクラの古木のある寺、常楽院が
あるので、まずはそちらに立ち寄ってみたら、もう少しで満開というところでした。


早稲田大学所沢キャンパスの北側を回り、その西側台地にあるのが金仙寺です。石段を
上がって行くと、まず目に付いたのは左手のハクモクレンの高木。

市内のほかのところは、ハクモクレンは盛りを過ぎているのですが、ここはちょうど見
頃でした。

本堂の前のシダレザクラも、間もなく満開というところ。明後日からは曇や雨模様の予
報からすると、今日明日が眺めるには一番よいかもしれません。




シダレザクラの下にも、色々な草花が植えられていて、花を競っていました。
まずはショカッサイ。

ハナニラもあちこちにありました。

東側のがけ際では、ミツマタなど4色の花の饗宴。

この位置からは3色


クリスマスローズも何色かの花が咲いています。


もう一度シダレザクラを見上げて。


ソメイヨシノはまだ5分咲き前後でしょうか。

本堂の西に回ると、墓地の隅ではハナモモの若木が満開に。

その先の畑は、いろいろな花が植えられていて、見頃の花がたくさん見られます。

わが家の庭にも咲いているムスカリ。

毎年描かれる花文字。今年は「〇(まる)い心で」と描かれているようです。

そばのハナモモ。

この細い枝に咲く花はなんだろう?

寺の駐車場の南側斜面。

本堂の左手には、もっと色濃いミツマタがあったのですが、今年は無くなっていました。

寺の西側の高台は、比良の丘という好展望地ですが、ここにはいろいろな花が咲き競っ
ています。

真っ赤で色鮮やかなのはボケの群落。

桃はいろいろな花が並んでいます。



まさに花の饗宴。





レンギョウ



この木だけ、やわらかな若葉の彩りを見せていました。

金仙寺の西側入り口付近に戻ります。

北側の道路に回ると、本堂裏手には少しだけでしたがカタクリが。


黄色い花のカタクリは初めて見ました。

もう一度境内に戻り、サクラの花を見上げて。



十分眺めたので帰路につくことに。わが家からは往復12㎞の市内ウオーキングでした。
にほんブログ村